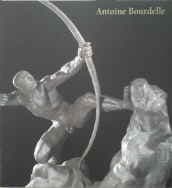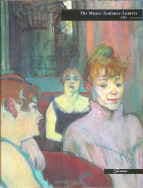明けましておめでとうございます。

2019年1月1日 (7:55)我が家のベランダから撮影の初日の出
160. アルガルベ地方小さな旅日記
例年ならクリスマスにあわせてアルガルベ旅行をするところだが、今年は少し早めた日程になった。元々は油彩を描くためのモティーフを求めてポルトガル全国至る所に出掛けてはスケッチを描いてきた。年間50枚ほどの油彩を描くためのエスキースであるからそれ程は必要ではなかった。それでも長年にわたってのスケッチ、それが800枚1000枚と溜まっていく。
数年前に思い立ってスケッチに淡彩を施し『ポルトガル淡彩スケッチ』というブログを始めた。それと一緒にメモ程度の日記を掲載している。これは毎日であるから、帰国で居ない時、旅行で居ない時は除いても年間200枚程のスケッチを掲載していることになる。それが先日で1600枚を超え2018年大晦日で1668景となった。
当初は油彩用に描いたスケッチを描き直して淡彩を施していただけが、それでは間に合わなくなってしまって、今は淡彩スケッチを描くためのスケッチが必要ということになっている。
今までもおおよそ他人の行かないところまで貪欲に足を延ばし描いてきた。でもまだまだ行っていないところも多いし、一度は描いたところでも立ち位置を1メートル2メートルずらすと、もう違う絵が出来上がってくる。
2018年12月20日(木曜日)濃霧のち晴れ。降水確率4%。
朝食を済ませ8:30出発。少し通勤ラッシュ。濃霧。天気予報を見てからホテルの予約を入れたのだが、予報に濃霧までは予測がなかった。先日からフロントガラスが曇る。設定が旨く出来ていないか、排気口にゴミが詰まっているのか。或いは故障か。フロントには風が出ているのに曇る。弱いのだろうか?濃霧はいっそう強くなったり、弱くなったりでグランド―ラあたりまで。グランド―ラのリードゥルでトイレ休憩。
ミモザの少し手前の松の大木にコウノトリが集団で巣を架けているのを以前から見ていたのだが、一瞬で通り過ぎてしまい、一度は停車して写真を撮りたいと思っていた。それがこの程、クルマ助手席の窓からの撮影が実現。

01.松の大木はコウノトリの集合住宅
ミモザのドライブイン『サン・セバスチャン』でコーヒー休憩。コーヒーx2=1,40€。バカラウ・コロッケx2=2,60€。合計=4€。ヴィザカードで支払い。ヴィザは5ユーロからとのことで、5ユーロのレシートで1ユーロの現金でお釣りをくれる。このドライブインは例年クリスマス・プレセピオが飾られていて見るのを楽しみにしている。今年のものは昨年のよりは少し小規模だが可愛らしい。

02.ドライブインのプレセピオ
もう既にアルガルベ地方、メッシ―ネスのドライヴイン・ガスステーション『ペトロソル』で昼食。豚ステーキのタマネギソース和え、ポンフリ、サラダ=7€。バカラウ・ブラス、サラダ=7€。ノンアルコールビールx2=2€。フルーツサラダx2。合計=16€。
アルブフェイラの『リードゥル』で今夜のツマミの買い物、茹で蟹(サパテイラ・グランデ)9,99€。チョリソパン=0,79€。ピザパン=0,79€。箱入り赤ワイン1Lt=0,95€。リンゴ800g=0,99€。ミネラルウオーター(ルーソ)1,5Lt=0,57€。合計=14,08€。
帰る日(22日)にリスボンの中華食品店『陳氏超級市場』のアルブフェイラ支店で買い物をして帰ろうと場所を確かめに行く。住所付近には『陳氏超級市場』はなかったが別の中華食品店があった。多分『陳氏超級市場』は撤退して他の人が経営を引き継いだのだろう。置いてある商品はだいたい同じ、ついでにツマミなどを買う。レシートを貰っていないのか、失ったのか、支払金額不明。おおよそ6~7€。
ホテルに14:30に到着。フロントにはチェックインする人で5~6組の列。部屋はA503。海も見えて良い部屋だが東向き。荷物を置き、ビーチを散策。泳いでいる少年もいた。ビーチのバーでビール、生ビールx1。ノンアルコールビールx1。合計=4€。別の道、ホテル・モニカ・イザベルの方からホテルに帰る。テニスコートの横で灌木に地味な黄色の5~6弁花。これは初見花。ホテルの正面入り口付近はブルー系のイルミネーションで飾られている。駐車場の10株程の椰子の木にもらせん状にイルミネーション。椰子の株元にはポインセチア。入り口を入るとプレセピオ。
部屋のテレビで先日のセトゥーバル対ブラガの試合を観ながら蟹を食べる。映画は映らない。部屋は寒くて、暖房を入れ、風呂に2回入り、毛布を掛ける。星空、多くの漁火。ファーロ空港に降り立つ飛行機のライトが見える。そして潮騒の音。
2018年12月21日(金曜日)晴れ。降水確率0%。

03.ホテルの部屋からの日の出
朝は真正面から日の出。7:50頃に朝食サロンに。初めは空いていたがやがて満席に。殆どが英語。ウエイトレスも英語。たっぷりと食べ、たっぷりと飲む。
9:00出発。やはり『ズー・マリーン』は冬休み。寄り道スケッチをしながらサグレス岬を目指す。でもポルトガルの沿岸線はどこも都会化或いはリゾート化され、絵になるところは少ない。日本でいう寒漁村というイメージはない。寒村は内陸部にあり、僕のモティーフはそちらの方が多い。
途中パールシャルという町に立ち寄り、少しスケッチをし『デ・ボーラ』でトイレ。ついでに店内見学、買い物。紙ナプキン=0,59€。シャンプー750ml=0,99€。ベニテングタケとマツカサのクリスマス・リース用飾り=7,99€。合計=9,57€。
街を出ようとすると踏切線路、そして駅が見える。引き返し駅へ、撮影。丁度列車が到着、数人が乗り降り。ファーロとラーゴスを結ぶ線で1日に往復14本があるらしい。駅舎はレストランになっていて、コーヒーを飲む。コーヒーx2=2€。
ラーゴスの手前でアンタの標識があったので行ってみた。綺麗に整備された『アンタ遺跡』で入場料が1人2€x2=4€。カタログ=1€。カタログも葡語の他に英語、仏語、独語、西語と揃っていた。初めて見る形のアンタだ。他にも2組3人の見学者。オリーブの木に小さな実が一杯成っていて道にもたくさん落ちていた。誰も収穫しないのか?勿体ない。
サグレスの魚競り市場のレストランを目指したが休み。その手前のレシデンシアルのレストランも閉まっている。ベリッチェ岬のレストランも定休日。日本では金曜日は来ン曜日とか言って、お客は少なく定休日にしているところが多いとのことだが、ポルトガルでも金曜日はどうも定休日が多いようだ。
アルガルベ地方では例年のクリスマス時期には既にアーモンドの花が咲いているのだが、今回は2~3日早いだけなのに一輪も見られない。
サグレス岬の駐車場付近で野の花観察。やはりヴィオラ・ペルシシフォリア(桃葉スミレ)は咲いている。ロブレア・マリティマ(スイート・アリッサム)やアレクリン(ローズ・マリー)もたくさん咲いている。この岬のアレクリンは濃色が多い。しかし目新しい花はなし。
ビラ・ド・ビスポの方角に帰ろうとすると『漁師の食堂』の看板。そちらに行ってみたがやはり定休日。その先にもう一軒レストランの看板。たくさんの商用車が路上駐車をしている。これは期待が出来ると入ってみる。入り口の黒板に今日のメニューは鶏の炭火焼き。冷蔵ショーケースには新鮮な鯵。これで決まり。鶏の炭火焼き=7,00€。鯵の炭火焼き=8,00€。生ビール=1,00€。ノンアルコールビール=1,50€。デザート2,5x2=5€。合計=22,50€。デザートを食べ終える頃には既に3時を回っていたので、ウエイターの小父さんはすぐに会計のレシートを持ってきた。「デスカフェイナードも注文しようと思っていたのに」と言うとデスカフェイナードを持ってきたが「もうレシートを切ってしまったのでコーヒー代金はいらない」という。なかなか良い店が見つかった。鯵などは新鮮で大きいのが7尾も付いていた。食べ切れないので持って帰ったが、ホテルでも食べられず冷蔵庫に入れておいて結局自宅まで持って帰った。日本人らしきカップルが居たが話はしなかった。旅行者だろうか?
ホテルに帰る途中、ラゴアのジュンボGSでガソリンを満タンに。24,12Ltx1,369=33,02€。クルマの正面に大きな満月。ホテルに戻ったのは暗くなってから。部屋のテレビは映画もなし、サムスンで薄型テレビに代わっていたが画像が乱れ見にくい。エアコンの温度を上げる。
2018年12月22日(土曜日)晴れ。降水確率0%。
7:50から朝食。今朝もたっぷりと食べ、たっぷりと飲む。アルブフェイラ出発前に中華食品で豆腐などの生ものも含め、買い物をして帰る予定なので、ホテルの冷蔵庫で1,5リッターのミネラルウオーター2本を昨夜から凍らせておいた。
ホテルを9:00出発、チェックアウト時に鍵のデポジット10€を受け取り、先日撮った花を朝の光で撮る。
アルブフェイラ、ベラ・ヴィスタ地区の中華食品店『Folhas Queridas愛の葉っぱ』へ。土曜日の朝だからか、中国人常連客で賑わっていた。大根2,02kgx1,95=3,94€。白菜0,8kgx1,95=1,56€。即席ラーメン(出前一丁)0,60x6=3,60€。焼きそば乾麺418g=1,95€。餃子皮200g=2,50x2=5,00€。醤油(万家香)1Lt=3,50x2=7,00€。豆腐500g=1,30x2=2,60€。牡蠣油907g=4,95€。キッコーマン醤油1Lt=7,25€。油揚げ=2,80€。合計=40,65€。サーヴィスで凝った来年のカレンダーをくれたが、見にくくて恐らく使えない。凍らせた水と一緒に必要な食料、それに鯵を保冷バッグに。
当初はヴィラ・レアル・デ・サント・アントニオで話題のプレセピオを見学して、カストロ・マリム経由で帰る予定だったが、少々疲れたのでIC1で。スケッチをするつもりですぐに横道にそれた。それたすぐにはいい場所があったが、その後はなかなかスケッチの出来るような村はなく、代わりにアルブツス・ウネドが綺麗に群生しているところで撮影が出来る。

04. アルブツス・ウネド(イチゴの木)の白い花と赤い果実。この赤い実から特産の焼酎ができる。
途中風変わりな標識、ヘリコプターとタンクローリーが水を汲める場所。小さな池があった。こんな水溜り程度の池でもヘリコプターで水が汲めるのだ。2018年8月に1週間燃え続けたモンシックの山火事もここからそれ程遠くはない。そう言えばその時のモンシックの山火事でユーカリと共にこのアルブツス・ウネドの木がたくさん燃えてしまった、とニュースは伝えていた。赤く熟した実を口に含んでも甘酸っぱくて美味しいのだが、赤い果実は蒸留酒の原料となり、アルコール度数46度もの強い酒になり、アルガルベ地方の特産品ともなっている。

05.水汲み場の標識
いっぱいの朝露を受けて、エリカ・アルボレアも咲き始めていた。それとカモミールとアブラナ科の小さな花が一面に花盛り。この辺りは低地なのか湿度が高い。
あちこちにため池がある。その先の地道を奥へ奥へと行くとやがて行き止まり。イギリス人のコミュンがあった。こんな奥地の古民家を買って、キャンピングカーも交えてイギリス人が数家族で暮らしているのだ。イギリスなどと比べると物価は安いし、暖房費はいらない。余程過ごしやすいのだろうと思う。それに加え、英語を話すポルトガル人は増えている。
道は水没して行き止まりになっていたので元来た道を引き返し、舗装道路を行く。行くがスケッチの出来そうな村には行き当らず、お腹も空き始めたので、アルモドバール方面行きの道に出る。ようやく店が1軒。クルマが停まっていた食堂風の店に入ったが「昼食はやっていない。3キロ先にあります」とのことで3キロ先の食堂に入る。ほぼ満席。空いていた入り口付近の席へ。黒豚のステーキx2。ポンフリ、サラダ、ノンアルコールビールx2。デスカフェイナードx2。合計=16€。この辺りはどこも安い。黒豚のステーキが2枚ずつもついてこの価格。
アルモドバールはつい先日もスケッチをしたところだが、再度歩き回ってスケッチ。少し大きな町ともなると、どこもクリスマス・イルミネーションの飾り付けがあり、スケッチの邪魔になるが、仕方がない。
アルモドバールに着くまでに思った以上に難行したので、IP2に乗って、べ―ジャ経由で帰ることにした。
西日はすぐに沈み、空一面に広がった夕焼けが美しい。美しい夕焼け空を楽しみながらゆっくりクルマを走らせたいところだが、他のクルマの流れに沿って、それ程広くもない道路を100キロ前後での運転。やはりフロントガラスが曇り始めたが、左側の吹き出し口のスイッチがオフになっていた様で逆にすると、曇りはほぼなくなる。
フェレイラ・デ・アレンテージョからカナル・カベイラそしてIC1に入りグランド―ラ。グランド―ラの『コンチネンテ』でトイレ休憩。夕方のコンチネンテは買い物客で一杯。カフェに席が空いたのでデスカフェイナードx2。パスティス・デ・ナタx1。「コンチネンテのカードをお持ちですか?」で出す。合計=1,60€。
家に帰りついたのが19:30頃だったか。いつもの駐車スペースは塞がっていて隣のマンションの前へ。買って帰った中華食品などを冷蔵庫に入れ、風呂に入り、テレビの映画も観ないでぐっすりと眠る。
帰った翌日はアルガルベで買って来たベニテングタケのクリスマス・リースの追加をぶら下げ、ボーロ・レイ(ポルトガルのクリスマスケーキ)にアルブツス・ウネドの焼酎をたっぷりと振り掛けクリスマス気分を味わうこととなった。
ちなみにボーロ・レイを食べる日は1月6日である。
あまり描くところがないように思った旅だが、それでもスケッチブックの1冊が埋まってしまった。VIT
「ポルトガル淡彩スケッチ・サムネイルもくじ」
https://blog.goo.ne.jp/takemotohitoshi/e/b408408b9cf00c0ed47003e1e5e84dc2