1979年(43年前)の大河「草燃える」の主人公は、源頼朝と北条政子です。頼朝は途中で亡くなるので、後半は政子が主人公なのですが、この政子、さほど政治的ではありません。色々な歴史的事件(頼家殺害、実朝暗殺)については「政子は知らなかった」とされます。となると政子の名で幕府を動かしていた北条義時が「実質上の主人公」になっていきます。松平健さんが演じました。
1979年、私はまだ子供で、見てはいましたし、非常に強い関心を持ったのも覚えているのですが、内容をはっきりと理解したわけではなかったと思います。その後総集編がDVDになって、「なるほどこういう作品だったのか」と気が付きました。一言でいうと、単純ですが「素晴らしい作品」です。大河の中でも筆頭格の作品だと個人的には思います。
言葉遣いがとても平易です。現代語に近い。当時はそれで多少批判されたようです。でも「分かりやすい」わけです。さらに現代語を話すことによって、感情が豊かに表現できているとも感じます。最後の最後に北条政子はこう思います。「一生懸命やってきて、幕府も安定したけれど、気が付くと、夫もいない、子供も死んだ。孫もみんな死んだ。私は一人だ」(正確ではありません)。そして政子の「むなしげな顔のアップ」で「完」となります。平曲が流れています。「諸行無常」を平家だけでなく、頂点を極めた北条政子にも当てはめているのです。
ただなんといっても絶妙なのは「北条義時の変化」です。登場時はまさに「好青年の典型」なのです。虫も殺せないような男です。優しいし、賢くもある。松坂慶子さん演じる「初恋の人」をひたすら慕う純粋な男でもあります。それが最後は権力の権化となります。そしてこういう認識を語ります。
「おれは今になって、俺の兄貴が考えていたことが分かってきた。源氏の旗揚げ、あれは源氏の旗揚げではなかった。俺たち坂東武者の旗揚げだったのだ。あくまで源氏は借り物。となれば、俺たち坂東の武者の中で、一番強い者が権力を握る。それは当然のことなのだ。俺はよくやっている。十郎、誉めてくれないか」
この「十郎」というのは源氏に恨みをもつ伊東家の侍で、第四の主人公と言える人物です。若い頃は荒んでいて、平氏について敗れ、とうとう強盗でも殺人でも強姦でもなんでもありの悪となります。が、北条義時の変化とクロスするように更生していき、最後は平曲を語る琵琶法師となります。
話を戻すと、子供の私が一番衝撃を受けたのが「源氏の旗揚げではない」というセリフでした。「鎌倉幕府を作ったのは源氏でも、源頼朝でもなく、坂東の武者たちである」、こう考えると、源氏将軍がすぐに死に絶えても、鎌倉幕府が存続した理由が、合理的に説明できるような気がしました。「歴史の解釈」というものに生まれて初めて興味をもったわけです。
現在、歴史家の中には「歴史は解釈不要であり、偶然の集積である」という人もいます。でもそれじゃあ「つまらないし、学ぶ気にもなれないな」というのが素人である私の感想です。「歴史の解釈」は面白いし、必要だと私は思います。同時に「私の解釈は絶対的に正しい」と思わないことも、また必要だと思います。
1979年、私はまだ子供で、見てはいましたし、非常に強い関心を持ったのも覚えているのですが、内容をはっきりと理解したわけではなかったと思います。その後総集編がDVDになって、「なるほどこういう作品だったのか」と気が付きました。一言でいうと、単純ですが「素晴らしい作品」です。大河の中でも筆頭格の作品だと個人的には思います。
言葉遣いがとても平易です。現代語に近い。当時はそれで多少批判されたようです。でも「分かりやすい」わけです。さらに現代語を話すことによって、感情が豊かに表現できているとも感じます。最後の最後に北条政子はこう思います。「一生懸命やってきて、幕府も安定したけれど、気が付くと、夫もいない、子供も死んだ。孫もみんな死んだ。私は一人だ」(正確ではありません)。そして政子の「むなしげな顔のアップ」で「完」となります。平曲が流れています。「諸行無常」を平家だけでなく、頂点を極めた北条政子にも当てはめているのです。
ただなんといっても絶妙なのは「北条義時の変化」です。登場時はまさに「好青年の典型」なのです。虫も殺せないような男です。優しいし、賢くもある。松坂慶子さん演じる「初恋の人」をひたすら慕う純粋な男でもあります。それが最後は権力の権化となります。そしてこういう認識を語ります。
「おれは今になって、俺の兄貴が考えていたことが分かってきた。源氏の旗揚げ、あれは源氏の旗揚げではなかった。俺たち坂東武者の旗揚げだったのだ。あくまで源氏は借り物。となれば、俺たち坂東の武者の中で、一番強い者が権力を握る。それは当然のことなのだ。俺はよくやっている。十郎、誉めてくれないか」
この「十郎」というのは源氏に恨みをもつ伊東家の侍で、第四の主人公と言える人物です。若い頃は荒んでいて、平氏について敗れ、とうとう強盗でも殺人でも強姦でもなんでもありの悪となります。が、北条義時の変化とクロスするように更生していき、最後は平曲を語る琵琶法師となります。
話を戻すと、子供の私が一番衝撃を受けたのが「源氏の旗揚げではない」というセリフでした。「鎌倉幕府を作ったのは源氏でも、源頼朝でもなく、坂東の武者たちである」、こう考えると、源氏将軍がすぐに死に絶えても、鎌倉幕府が存続した理由が、合理的に説明できるような気がしました。「歴史の解釈」というものに生まれて初めて興味をもったわけです。
現在、歴史家の中には「歴史は解釈不要であり、偶然の集積である」という人もいます。でもそれじゃあ「つまらないし、学ぶ気にもなれないな」というのが素人である私の感想です。「歴史の解釈」は面白いし、必要だと私は思います。同時に「私の解釈は絶対的に正しい」と思わないことも、また必要だと思います。











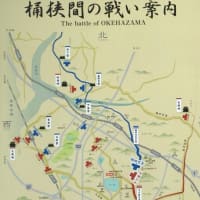


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます