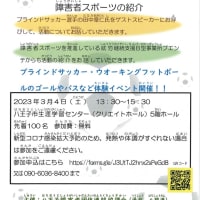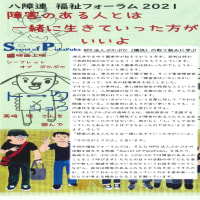八障連通信292号をアップします。
八障連通信292号PDF版はこちら
ここからは、八障連通信292号の本文です。
例会報告
9月18日の例会では、前半は第三者評価を行っている、「にほんの福祉ネット」の三谷氏から、事業所の特徴と、最近の第三者評価の傾向などを説明して頂きました。後半は10月16日(木)に行われる、「障害者福祉課長との懇談会」でのテーマについて、話し合いました。
例会の参加団体のなかには、すでに第三者評価を受けた事業所と、これから受ける事業所からの参加者が、それぞれ半数ずつ、いらっしゃった事で、第三者評価に対してのイメージや捉え方について、多くの意見や感想が飛び交い、貴重な意見交換の場となりました。(次ページに当日報告された「第三者評価」のレジメを掲載したのでご参照ください) 10月16日の「福祉課長との懇談会」では、取り上げるテーマとして、①重度の人たちの通所先が経営困難に陥っている現状や、会員団体の共通課題として、家賃補助(日中活動系施設等運営安定化補助金・日中活動系サービス推進事業補助金)の現状維持について、②計画相談事業が推進されていない現状と課題、③障害者雇用枠の市職員採用試験において、点字での試験が受けられない事への問いかけ、④中核都市になるに至って、差別禁止条例などの位置づけについての行政側の見解、の4点を決めました。最後に、11月8日に行う、知的事業所向けの学習会「日中支援から生活支援へ」での、当日の進め方や役割分担について話し合いました。また、11月20日の市議との懇談会でのテーマについては、福祉課長との懇談会の様子から、全体で共有できるテーマを見つけていく方向性とし、次回の臨時運営委員会議で決める事としました。<文責/川出>
事務局通信
今年度も早くも半期を過ぎ、下半期に入りました。去る8月にお送りした通信290号に年会費の請求と振込用紙を同封しました。会計担当者からの報告では、既に半数以上の会員が納入済みとのことでした。ご協力ありがとうございました。また、未納の会員には引き続き早めの納入をお願い致します。ご存知のように八障連は補助・助成金はどこからも受けて無く、ほぼ会員からの会費のみを頼りに運営されております。改めて、ご理解とご協力をお願い致します。尚、振り込まれる際に法人名または個人名のみの明記での納入がたまにあります。個人賛助会員または事業所を持たない団体を除いて、特に複数の事業所で登録している法人については、会計・事務局で判断に迷うケー
スもありますので、法人名・事業所名併記での納入をお願い致します。<文責/夛田>
10月・11月の予定
第3回 八王子差別禁止条例イベント「みんなでつくろう!やさしさあふれるわが街を」
10月11日(土)13時30分~16時 クリエイト5階
障害者福祉課長との懇談会10月16日(木)18時~20時 市役所(後に23日に変更しました)
八障連臨時運営委員会 10月30日(木) 18時~20時 クリエイト
6法人共催 講演会 「障害のある人もない人もみんないきいき暮らせるまちづくり」
11月1日(土)14時~16時 東浅川保健福祉センター
八障連主催 知的事業所向け企画
11月8日(土)13時~16時クリエイト
市議会議員との懇談会
11月20日(土)18時~20時クリエイト
例会企画報告
9月18日の例会企画として、「福祉サービス第三者評価」を実施している評価機関・株式会社にほんの福祉ネットの三谷さんより、「第三者評価」を活用するためのお話を伺いました。当日提出されたレジメ(の概要)を掲載しますのでご一読頂き、各々の評価に基づいて活用して頂ければ幸いです。(なお掲載にあたり、編集上の理由で一部レジメ内容を変更していますのでご了承ください)
第三者評価を前向き・未来志向の視点で活用していただくために
株式会社にほんの福祉ネット
私どもは、施設運営・現場での支援・経営支援・研修・評価などの経験を有するメンバーを核として、平成19年度より福祉サービス第三者評価を実施しております。評価の実施に際しては、事業所の「ありたい姿」の実現に向けた取り組みの実現に向けた支えとなるべく、運営や現場、評価などの経験を背景に、訪問調査における聞き取り、対話を大切にしております。
また、利用者本位の支援に向けた取り組みの見直し・改善、いずれにいたしましても、前向きな取り組みのためには「やる気」や「活力」が根底で必要となるため、埋もれている「強み」を表に出すことや、職員の「報われた」という思いに資すること、それらを可能な限り成果物に反映させることに努めております。
1)概要
第三者評価とは、よりよい事業所にしていくために、事業所と評価機関が協同して点検を行い、改めて現状を認識し組織の活性化につなげつつ、課題の設定や課題解決のためのプロセスの明確化を図る一連の作業を言います。都の評価制度に則りつつ、①評価事業における当社の方針に基づき、②都内での活動実績、および③評価者の専門性を生かしつつ、事業をめぐる動向を踏まえて事業所の自主性を後押しする評価を実施します。
ア)評価事業における方針
①報われる評価による活力の促進
強み・埋もれた力の明確化、「認められる」「報われる」仕掛けなどにより、今後の取り組みのため
の活力につなげます。
<評価項目に基づく評価者との対話は、事業所(職員)の特徴を顕在化・意識下させ、強
みや課題の発見・再認識につながりえます。 >
②改善点・課題点=理念・目標と現状との差=今後取り組んでいくこと
事業所理念、事業所の考える「ありたい姿」をもとに、今後取り組んでいくべき事柄など、将来に
対する視界の明確化をお手伝いいたします。
イ) 略
ウ) 評価者の専門性の還元
現場での支援や運営、高齢・障害の各分野におけるケアマネジメント、地域交流、都内のみなら
ず全国各地における研修など、評価者各自が磨いてきた専門性を、「調査」という名のコミュニケ
ーションを通して、事業所に還元します。 (詳細はhttp://www.nihon-fukushi.net/参照)
2)使用調査票に見る当社方針の実践 - 「前向き・未来志向の評価」「事業所の自主性を後押し
する評価」
ア) 職員アンケート、自由記述における前向きな声、建設的な声、参画意識などを引き出す工夫
当社版
貴事業所の特によいと思う点 あなたの働く事業所の良い点(組織・事業所・専門機関・働く場所として)
貴事業所の特に改善したいと思う点 組織として今後取り組んでいきたいこと、今後力を入れていきたい取組み
特色
貴事業所の特によいと思う点 専門職集団、公的制度に基づく施設、地域における福祉の専門機関、職場環境など、多様な面から見た組織の状態を把握する
貴事業所の特に改善したいと思う点 「〇〇が出来ていない」で終わるのではなく、「だからどうしていきたいか」という回答を引き出す
イ)「利用者調査」「家族アンケート」:自由意見における前向きな声、建設的な提案などを引き出す工夫
当社版
日頃お感じになっている当事業所に対するご意見・ご要望など、ご自由にお書きください。
当事業所を利用することで助かっていること、「良かった」と思えた場面などがあればお聞かせください。
今後も当事業所を利用するにあたり、「こうしてほしい」「こうであってほしい」といった期待があればお聞かせください。
特色
日頃お感じになっている当事業所に対するご意見・ご要望など、ご自由にお書きください。
まずは認める
そのうえで前向きな提案を引き出す
《以下略》
連載コラム 『日々のなかから、、』 <できる・できない> Vol.31 事務局長 杉浦 貢
小中学校の二学期が始まってしばらく経ちますが、そろそろ私にとっては、一年で一番忙しい時期に差しかかります。それというのも、10~11月は、学校訪問が集中する時期だからです。学校を訪れる際に最大の難関になるのが、移動です。京王、西東京といった路線バスを使用する頻度が一番高いのですが、最近はほぼ全ての車体がスロープバスになっているので、昔のようにバス停で待っていても車いすを無視して通り過ぎる、居なかったことにされるなど、乗車拒否されることも無くなりました。
では何が難関かといえば、バス停の方に少々問題があることが多いのです。バス停の場所が、住宅街の狭い歩道の上にあったり、歩道そのものの舗装が均一でなかったりで、スロープが充分に延ばせなかったり、スロープ板がデコボコしたりすることがあります。学校自体、中心市街から離れたところに建っていることが多いので、いつも学校最寄りのバス停については念入りな下調べをすることになるのです。
子どもたちと話す際、わりとよく出る質問に《どうしたら、身体の不自由な人の気持ちになって考えることができますか?》というのがあります。これはなかなか単純にして質の高い問いかけではないでしょうか。 はっきり言ってしまうなら、脳性マヒの身体で産まれた私には、障害の無い人の気持ちは判りません。それでも、普通校に通っていた経験、大勢の支援者の人たちと会話してきた経験から、『ああ、障害の無い人はこんな風に考えるのだな』と推察しながら受け応えしているわけです。
いえ、障害の有無に関わらず、他人の考えを推し量ろうとする場合、全ての場面で相手の気持ちを想像し、察する力が重要になってきます。
こどもさんの質問に応える場合は、もう少し柔らかく、《目が見える。耳が聞こえる。手足が動く。字が読める。計算ができる。明るく楽しく笑える。何かが『できる』というときには、必ずそれが『うまくできない』と言う人が世界のどこかに必ずいるんだということを想像してみてください。
息を吸ったり吐いたり心臓を動かすことも、自力では難しい人もいます。今まで普通に出来ていたことが、だんだん出来なくなったり、突然出来なくなったりもします》という表現で、多様性について説明します。
さらに、《お家に戻ったらほんの少しで良いので、目や耳を塞いでみたり、なるべく床から立ち上がらないようにして動いてみてください。なんにも出来ないと諦めて落ち込むのではなく、どうしたら安全に動けるか。どうしたら楽しく過ごせるか。ゲームのつもりでやってみてください。たくさん考えれば考えるほど、不自由な人の気持ちに近くなると思います》と提案します。
最期に必ず《しんどくなったら必ずやめること。危ないこともあるし、疲れることもあるから、短い時間にしておいてください。特に目隠しを使う場合には、自分一人ではなく誰かに見てもらいながら動くこと。1日10分。これを一週間続けると、いろいろ気が付くことがあるかもしれません》と付け加えます。こちらが言葉で説明するより、体験してもらった方がより楽しいかなと思うからです。
中には『僕は絶対障害者にはなりたくないです』という感想をくれる子もいますが、出した結論が多少こちらの思惑と違っても、それはその子の感受性であり否定はしません。常と異なる体験をしてもらうことが大切かな。と思っています。
以上。
八障連通信292号PDF版はこちら
ここからは、八障連通信292号の本文です。
例会報告
9月18日の例会では、前半は第三者評価を行っている、「にほんの福祉ネット」の三谷氏から、事業所の特徴と、最近の第三者評価の傾向などを説明して頂きました。後半は10月16日(木)に行われる、「障害者福祉課長との懇談会」でのテーマについて、話し合いました。
例会の参加団体のなかには、すでに第三者評価を受けた事業所と、これから受ける事業所からの参加者が、それぞれ半数ずつ、いらっしゃった事で、第三者評価に対してのイメージや捉え方について、多くの意見や感想が飛び交い、貴重な意見交換の場となりました。(次ページに当日報告された「第三者評価」のレジメを掲載したのでご参照ください) 10月16日の「福祉課長との懇談会」では、取り上げるテーマとして、①重度の人たちの通所先が経営困難に陥っている現状や、会員団体の共通課題として、家賃補助(日中活動系施設等運営安定化補助金・日中活動系サービス推進事業補助金)の現状維持について、②計画相談事業が推進されていない現状と課題、③障害者雇用枠の市職員採用試験において、点字での試験が受けられない事への問いかけ、④中核都市になるに至って、差別禁止条例などの位置づけについての行政側の見解、の4点を決めました。最後に、11月8日に行う、知的事業所向けの学習会「日中支援から生活支援へ」での、当日の進め方や役割分担について話し合いました。また、11月20日の市議との懇談会でのテーマについては、福祉課長との懇談会の様子から、全体で共有できるテーマを見つけていく方向性とし、次回の臨時運営委員会議で決める事としました。<文責/川出>
事務局通信
今年度も早くも半期を過ぎ、下半期に入りました。去る8月にお送りした通信290号に年会費の請求と振込用紙を同封しました。会計担当者からの報告では、既に半数以上の会員が納入済みとのことでした。ご協力ありがとうございました。また、未納の会員には引き続き早めの納入をお願い致します。ご存知のように八障連は補助・助成金はどこからも受けて無く、ほぼ会員からの会費のみを頼りに運営されております。改めて、ご理解とご協力をお願い致します。尚、振り込まれる際に法人名または個人名のみの明記での納入がたまにあります。個人賛助会員または事業所を持たない団体を除いて、特に複数の事業所で登録している法人については、会計・事務局で判断に迷うケー
スもありますので、法人名・事業所名併記での納入をお願い致します。<文責/夛田>
10月・11月の予定
第3回 八王子差別禁止条例イベント「みんなでつくろう!やさしさあふれるわが街を」
10月11日(土)13時30分~16時 クリエイト5階
障害者福祉課長との懇談会10月16日(木)18時~20時 市役所(後に23日に変更しました)
八障連臨時運営委員会 10月30日(木) 18時~20時 クリエイト
6法人共催 講演会 「障害のある人もない人もみんないきいき暮らせるまちづくり」
11月1日(土)14時~16時 東浅川保健福祉センター
八障連主催 知的事業所向け企画
11月8日(土)13時~16時クリエイト
市議会議員との懇談会
11月20日(土)18時~20時クリエイト
例会企画報告
9月18日の例会企画として、「福祉サービス第三者評価」を実施している評価機関・株式会社にほんの福祉ネットの三谷さんより、「第三者評価」を活用するためのお話を伺いました。当日提出されたレジメ(の概要)を掲載しますのでご一読頂き、各々の評価に基づいて活用して頂ければ幸いです。(なお掲載にあたり、編集上の理由で一部レジメ内容を変更していますのでご了承ください)
第三者評価を前向き・未来志向の視点で活用していただくために
株式会社にほんの福祉ネット
私どもは、施設運営・現場での支援・経営支援・研修・評価などの経験を有するメンバーを核として、平成19年度より福祉サービス第三者評価を実施しております。評価の実施に際しては、事業所の「ありたい姿」の実現に向けた取り組みの実現に向けた支えとなるべく、運営や現場、評価などの経験を背景に、訪問調査における聞き取り、対話を大切にしております。
また、利用者本位の支援に向けた取り組みの見直し・改善、いずれにいたしましても、前向きな取り組みのためには「やる気」や「活力」が根底で必要となるため、埋もれている「強み」を表に出すことや、職員の「報われた」という思いに資すること、それらを可能な限り成果物に反映させることに努めております。
1)概要
第三者評価とは、よりよい事業所にしていくために、事業所と評価機関が協同して点検を行い、改めて現状を認識し組織の活性化につなげつつ、課題の設定や課題解決のためのプロセスの明確化を図る一連の作業を言います。都の評価制度に則りつつ、①評価事業における当社の方針に基づき、②都内での活動実績、および③評価者の専門性を生かしつつ、事業をめぐる動向を踏まえて事業所の自主性を後押しする評価を実施します。
ア)評価事業における方針
①報われる評価による活力の促進
強み・埋もれた力の明確化、「認められる」「報われる」仕掛けなどにより、今後の取り組みのため
の活力につなげます。
<評価項目に基づく評価者との対話は、事業所(職員)の特徴を顕在化・意識下させ、強
みや課題の発見・再認識につながりえます。 >
②改善点・課題点=理念・目標と現状との差=今後取り組んでいくこと
事業所理念、事業所の考える「ありたい姿」をもとに、今後取り組んでいくべき事柄など、将来に
対する視界の明確化をお手伝いいたします。
イ) 略
ウ) 評価者の専門性の還元
現場での支援や運営、高齢・障害の各分野におけるケアマネジメント、地域交流、都内のみなら
ず全国各地における研修など、評価者各自が磨いてきた専門性を、「調査」という名のコミュニケ
ーションを通して、事業所に還元します。 (詳細はhttp://www.nihon-fukushi.net/参照)
2)使用調査票に見る当社方針の実践 - 「前向き・未来志向の評価」「事業所の自主性を後押し
する評価」
ア) 職員アンケート、自由記述における前向きな声、建設的な声、参画意識などを引き出す工夫
当社版
貴事業所の特によいと思う点 あなたの働く事業所の良い点(組織・事業所・専門機関・働く場所として)
貴事業所の特に改善したいと思う点 組織として今後取り組んでいきたいこと、今後力を入れていきたい取組み
特色
貴事業所の特によいと思う点 専門職集団、公的制度に基づく施設、地域における福祉の専門機関、職場環境など、多様な面から見た組織の状態を把握する
貴事業所の特に改善したいと思う点 「〇〇が出来ていない」で終わるのではなく、「だからどうしていきたいか」という回答を引き出す
イ)「利用者調査」「家族アンケート」:自由意見における前向きな声、建設的な提案などを引き出す工夫
当社版
日頃お感じになっている当事業所に対するご意見・ご要望など、ご自由にお書きください。
当事業所を利用することで助かっていること、「良かった」と思えた場面などがあればお聞かせください。
今後も当事業所を利用するにあたり、「こうしてほしい」「こうであってほしい」といった期待があればお聞かせください。
特色
日頃お感じになっている当事業所に対するご意見・ご要望など、ご自由にお書きください。
まずは認める
そのうえで前向きな提案を引き出す
《以下略》
連載コラム 『日々のなかから、、』 <できる・できない> Vol.31 事務局長 杉浦 貢
小中学校の二学期が始まってしばらく経ちますが、そろそろ私にとっては、一年で一番忙しい時期に差しかかります。それというのも、10~11月は、学校訪問が集中する時期だからです。学校を訪れる際に最大の難関になるのが、移動です。京王、西東京といった路線バスを使用する頻度が一番高いのですが、最近はほぼ全ての車体がスロープバスになっているので、昔のようにバス停で待っていても車いすを無視して通り過ぎる、居なかったことにされるなど、乗車拒否されることも無くなりました。
では何が難関かといえば、バス停の方に少々問題があることが多いのです。バス停の場所が、住宅街の狭い歩道の上にあったり、歩道そのものの舗装が均一でなかったりで、スロープが充分に延ばせなかったり、スロープ板がデコボコしたりすることがあります。学校自体、中心市街から離れたところに建っていることが多いので、いつも学校最寄りのバス停については念入りな下調べをすることになるのです。
子どもたちと話す際、わりとよく出る質問に《どうしたら、身体の不自由な人の気持ちになって考えることができますか?》というのがあります。これはなかなか単純にして質の高い問いかけではないでしょうか。 はっきり言ってしまうなら、脳性マヒの身体で産まれた私には、障害の無い人の気持ちは判りません。それでも、普通校に通っていた経験、大勢の支援者の人たちと会話してきた経験から、『ああ、障害の無い人はこんな風に考えるのだな』と推察しながら受け応えしているわけです。
いえ、障害の有無に関わらず、他人の考えを推し量ろうとする場合、全ての場面で相手の気持ちを想像し、察する力が重要になってきます。
こどもさんの質問に応える場合は、もう少し柔らかく、《目が見える。耳が聞こえる。手足が動く。字が読める。計算ができる。明るく楽しく笑える。何かが『できる』というときには、必ずそれが『うまくできない』と言う人が世界のどこかに必ずいるんだということを想像してみてください。
息を吸ったり吐いたり心臓を動かすことも、自力では難しい人もいます。今まで普通に出来ていたことが、だんだん出来なくなったり、突然出来なくなったりもします》という表現で、多様性について説明します。
さらに、《お家に戻ったらほんの少しで良いので、目や耳を塞いでみたり、なるべく床から立ち上がらないようにして動いてみてください。なんにも出来ないと諦めて落ち込むのではなく、どうしたら安全に動けるか。どうしたら楽しく過ごせるか。ゲームのつもりでやってみてください。たくさん考えれば考えるほど、不自由な人の気持ちに近くなると思います》と提案します。
最期に必ず《しんどくなったら必ずやめること。危ないこともあるし、疲れることもあるから、短い時間にしておいてください。特に目隠しを使う場合には、自分一人ではなく誰かに見てもらいながら動くこと。1日10分。これを一週間続けると、いろいろ気が付くことがあるかもしれません》と付け加えます。こちらが言葉で説明するより、体験してもらった方がより楽しいかなと思うからです。
中には『僕は絶対障害者にはなりたくないです』という感想をくれる子もいますが、出した結論が多少こちらの思惑と違っても、それはその子の感受性であり否定はしません。常と異なる体験をしてもらうことが大切かな。と思っています。
以上。