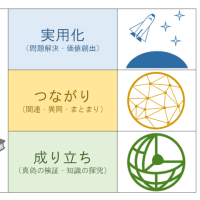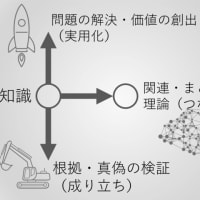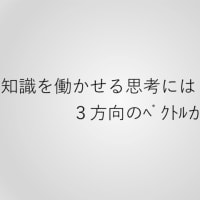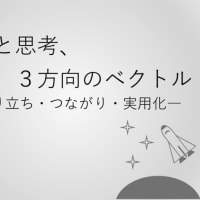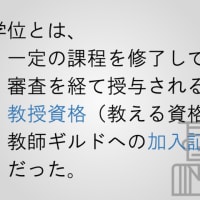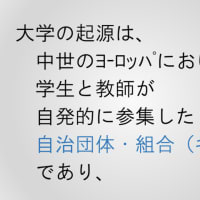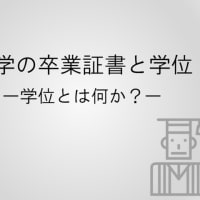『障害の理解』(九州保健福祉大学通信教育部 2013年テキスト科目)
1.障害の基礎的理解
障害の医学モデルと社会モデルを対比させて、国際障害分類(ICIDH)から国際生活機能分類(ICF)への考え方の変化を理解する。ICIDHでは、病気・変調→機能障害(インペアメント)→能力障害(ディスアビリティ)→社会的不利(ハンディキャップ)という図式に示されるように、病気・変調による心身の機能障害が障害を生み出す根底にあると考えていた。このような考え方は基底還元論と呼ばれ、病気の原因を特定しようとする障害の医学モデルであるといえる。それに対して障害の社会モデルとは、社会の偏見や障壁(バリア)によって障害が作られていると考え、社会の意識や政策を問題にする。これらの障害の医学モデルと社会モデルを統合しているのがICFである。
ICFの特徴は、1)環境因子(促進因子・阻害因子)を取り入れたこと、2)障害(マイナス)の面に注目する病理欠陥アプローチではなく、障害を受けていない生活機能(プラスの面)にも注目すること、3)障害の表記について、活動制限や参加制約などのように中立的な表現を使用したことが挙げられる。ICIDHと同様に、ICFでも障害を身体レベル、個人レベル、及び社会レベルの3つのレベルに分けている。ICFの障害の3つのレベルは、相対的独立性と相互依存性という2つの性質を有している。すなわち、心身機能・構造に機能障害があっても、福祉用具(環境の促進因子)の利用によって活動制限・参加制約が生じないこともあれば(相対的独立性)、逆に活動・参加が減少することによって心身機能・構造に機能障害が生じることもある(相互依存性)。
ICFの視点では、長期間の臥床や安静によって関節拘縮や筋力低下などが生じる廃用症候群は、活動・参加が低下することにより生じる状態として理解される。ICFは障害についての考え方を示すものであるが、実際に障害者とは誰のことであるのかということは、障害者基本法と各種の実体法(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、及び精神保健福祉法)、及び障害者自立支援法により定義される。身体障害、精神障害および知的障害に関する法律や施策は、それぞれ歴史的経緯が異なっている。障害者福祉の思想・理念、障害者福祉政策、及び国際的な動向については、それらを相互に関連させて理解する。
人権思想とは、人は生まれながらにして人としての権利を有しているという考え方である。こうした人権は、国家が存在する以前の状態(自然状態)から有しているという意味で自然権と呼ばれる。それに対して、国家が個人の人権や生存権を保障する役割を果たすという考え方が社会権である。障害者の人権について、ノーマライゼーションとは、障害者をノーマルに近づけるのではなく、障害者がノーマルな生活を送ることができるようにするという考え方である。障害のマイナスの面に注目することが病理欠陥アプローチであり、それに対して障害者の持っている強みに注目することがストレングス視点である。障害者の自立について、自立生活運動の考え方とは、日常生活動作の自立や経済的自立のことではなく、人格的な自立のことであり、選択と自己決定を行うことにより生活の主体となることである。障害者の自己決定について、エンパワメントとは専門家主導の援助や病理欠陥アプローチではなく、パワレスな状態にある障害者の自己決定や問題解決力を高める援助のことである。リハビリテーションにおいて、障害によって低下した心身の機能を訓練により回復させることを治療的・代償的アプローチと呼ぶ。それに対して、リハビリテーションの人間的復権とは、障害によって失われた人間らしく生きる権利(生きがい、役割、尊厳など)を回復させることである。
2.障害の理解
(1)身体障害
身体の部位及び機能について系統的に理解する。1)感覚機能(視覚、聴覚・平衡機能)、2)音声・言語機能、咀嚼・嚥下機能、3)運動機能(骨格、筋、関節、脊髄、脳)、4)肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、及び5)内 部機能(心機能、呼吸機能、腎機能、膀胱直腸障害、小腸機能、ヒト免疫機能、肝機能)。聴覚機能と音声・言語機能の関係について、言葉を話すときは自分の
声を自分の耳でも聞いているため、聴覚障害があると構音や音声言語にも障害が生じる。言語機能には受容(理解)と表出のプロセスがあり、さらにスピーチ (話し言葉)とランゲージ(言語体系)の側面がある。言語の働きとしては1)言葉で会話やコミュニケーションをする(外言)、2)言葉で声かけや注意をして(外言)、行動をコントロールする(内言)、3)言 葉を使って思考する(内言)がある。このように、言語機能とは社会的能力であり、知的能力でもあるといえる。また、発声・発語機能、呼吸機能、及び咀嚼・
嚥下機能は、一部で同じ身体器官を共用しているため、誤嚥(食道→気管)が生じることや、これらの機能に同時に障害が現れることもある(球麻痺)。
感覚機能と運動機能の関係について、物理的刺激→感覚受容器→電気信号→求心性末梢神経系→中枢神経系→遠心性末梢神経系→電気信号→運動効果器→物理的
運動という一連の流れの中に位置づけられる。運動機能には中枢性と末梢性、運動実行と運動調節、随意運動と不随意運動の側面があり、運動の麻痺や失調を理 解する視点となる。脊髄損傷では損傷部位以下の運動・感覚障害、膀胱直腸障害が生じる。そのため、損傷部位が頭部に近いほど障害レベルが高くなり、高位頸
髄損傷では呼吸障害が加わる。運動障害を肢体不自由の用語からみると、上肢(操作)、下肢(移動)、および体幹(姿勢保持)のそれぞれの機能に注目する。 労作性とは、安静時に対して運動時に障害が現れることである。バイタルサインとは、生命に直結する指標であり、心拍数、血圧、呼吸、体温(身体機能)、お
よび意識レベル(精神機能)である。
(2)精神障害
精神障害の専門用語には、精神病理学(精神症候学)、精神分析学、および神経心理学の領域に独自の用語法が存在しているので、それらの相違を意識しながら理解する。精神障害には、1)現実検討力の低下、2)主体感の低下、3)意欲の低下・亢進、4)社会性の低下、5)衝動抑制の低下などの側面が挙げられる。症状性精神障害とは、身体疾患や治療薬など何らかの外因によって精神症状が引き起こされ、可逆的である。それに対して、器質性精神障害とは脳そのものの変性により生じるものであり、不可逆的である。
人格という用語には、1)性格(パーソナリティ)、2)自我意識(エゴ)、3)社 会道徳や人間性などの品性(モラル)という意味でつかわれる。人格(性格)とは、社会経験により獲得された行動や思考の傾向の個人差のことであり、それに
対して生得的な個人差は気質と呼ばれる。人格障害とは、社会不適応となる行動や思考の傾向が長期間にわたり変化することなく続いていることである。自我意 識とは、見当識やアイデンティティなど、自己についての内省的意識が統合され、主体感を伴う状態である。感覚と知覚の違いについて、感覚とは物理的刺激が
末梢受容器を通じて電気信号として神経系を伝わることであり、知覚とはその刺激を脳で受け取り意味づけることである。物理的刺激が存在せず知覚が生じてい ることが幻覚(幻聴など)である。思考とは知的能力の1つであるが、精神障害の思考障害という場合は、現実検討力が低下した状態(妄想)や論理性やまとまりのない状態(支離滅裂、観念奔逸)、主体感が低下した状態(思考途絶、作為思考)をさす。
情動・感情・意欲・気分・情緒について、実際には互換的に使用されることも多いが、1)情動とは快・不快に基づき、接近・回避行動や闘争・逃走反応を生じさせる原初的反応であり、易怒性、情動失禁などのように使用される、2)感情とは、情動が社会的に分化したもので、好悪を中心とした評価反応であり、感情鈍麻(感情表出が乏しい)、感情平板化(感情表出の幅が狭い)、多幸感などのように使用される、3)意欲とは生理的欲求(睡眠・食事など)や動機づけ(目標に向けた行動を始発し、維持する働き)であり、精神運動性とは動作の表出量やテンポについて使用される、4)気分障害とは躁状態や鬱状態について使用される、5)情緒とは、ストレスや葛藤、家庭環境など心因性という意味で使用される。また、行動障害とは、社会的に不適切な行動や自傷行動、他害行動について使用される。
(3)知的障害
知能としては、知覚、動作・操作、記憶、言語、学習、概念形成、計算、推論などの認知機能が含まれる。これらの認知機能については、WIAS-Ⅲ知能検査などの検査項目を手掛かりにすると具体的に理解しやすい。WAIS-Ⅲ知能検査で測定される認知機能については、認知心理学の考え方に沿って理解していく。認知心理学とは行動心理学を基礎としている。行動心理学では、人間の心理について主観的な内省報告を排して、客観的に観察可能な行動だけを分析対象としており、
刺激(S)→反応(R)
が分析の単位となる。認知心理学では、この刺激(S)→反応(R)の間について、以下のように情報処理の流れを想定し、知能に含まれる認知機能はこの情報処理の流れの中に位置づけられる。
刺激(S)→ 感覚(物理刺激の電気信号が神経系を 伝わること)→知覚(刺激を受け取り意味づける こと)→記憶(外界の刺激を内的イメージとして 一時
的に保持する、さらに長期的に保存し、想 起・検索する)→理解や思考(判断・概念形成・ 計算・推論など)、および意思決定→反応(R)
知能の分類としては、言語性(言語を使用して測定される能力)と動作性(図形や具体物の操作により測定される能力)や、結晶性(獲得された知識・技能)と流動性(新奇の課題・場面における問題解決)という分け方がある。また、知能の指標として、WAIS-Ⅲで算出される群指数(言語理解、知覚統合、作動記憶、処理速度)とは、WAIS-Ⅲの検査課題を因子分析(統計的手法)によって、4つのグループにまとめたものである。知的障害の判定の基準として利用される知能指数(IQ:Intelligence Quotient)について、IQには比IQと偏差IQの2つがある。元来、IQのQ(Quotient)は比率や商(割り算の答)という意味であり、児童を対象としたビネー式知能検査では、IQとは精神年齢÷生活年齢×100として算出する(比IQ)。比IQでは生活年齢に比して精神発達(知的発達)が遅れているかを判断する。一方、偏差IQについて、ウェクスラー式(WAIS-Ⅲ・WISC-Ⅳ)などの知能検査では、同一年齢集団内での相対順位、すなわち偏差値(平均100、標準偏差(SD)15)としてIQを算出する(偏差IQ)。偏差IQでは正規分布の中での相対順位により知的障害を判断する。偏差IQに基づくと、平均100から2SDを引いたIQ70が知的障害の判定基準となる。同様に、IQ55(-3SD)やIQ40(-4SD)、IQ25(-5SD)は理論的な基準であるといえる。それに対して、知的障害の経験な基準として、大島の分類ではIQ70、50、35、20を基準とする。これらの2つの基準の数値を組み合わせると、IQ70~IQ55-50~IQ40-35~IQ25-20~という4つの区分が作られ、それぞれの区分に知的障害の軽度から最重度までが分類される。また、IQ80~70は境界線知能の基準とされる。ただし、WAIS-Ⅲなどの知能検査は、実際の人間関係の中での社会適応能力については、十分に測定していないことは留意すべき点である。その点について、知的障害の定義においても、知的機能および社会適応機能の双方に制約があるものとされている。
(4)発達障害
発達障害とは、発達期の発達過程において心身の機能を獲得することの障害であり、従来の(広義の)発達障害として、知的障害や脳性麻痺が含まれることもある。それに対して、近年に発達障害といわれるものは、学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、および自閉症を指す。これらの発達障害は、全般的な知的能力に遅れはないものの、中枢神経系の機能不全により、発達の過程において特定の認知機能を習得することに障害(学習能力障害)がある。その特定の認知機能として、1)学習障害については読み・書き・計算・推論など、2)注意欠陥/多動性障害については反応抑制や心的努力など、3)自 閉症については共同注視(ジョイント・アテンション)やゲシュタルト知覚(情報の断片やパーツを意味ある全体像としてまとめて理解すること)、感情理解、
想像力などが挙げられる。こうした習得障害によって、苦手な能力の個人内差が極端になり、認知の凹凸といわれる発達障害の認知特性が作られる。こうした認 知特性について、苦手な能力を得意な能力で補うことや、周囲の理解や配慮によって適応することが困難になった場合に、医療機関を訪れて発達障害の診断を受
けることになる。また、苦手な能力を得意な能力で補う適応努力やソーシャルスキルの弱さ、周囲の誤解によって持続的なストレスが生じたために、発達障害そ のものの障害の他に、2次的症状や自尊感情の低下も生じうる。成人期の発達障害では、このような2次的症状に対するケアも併せて求められる。
学習障害の学習(ラーニング)とは、経験による行動変容や知識・技能の習得という意味の心理学用語であり、学業成績(アチーブメント)という意味ではないが、実際には学業成績が言及されることが多い。自閉症のうち、知的障害を伴うものが4分の3であり、4分 の1が知的障害を伴わないもの(高機能自閉症)、さらに言語発達に遅れがないものである(アスペルガー症候群)。自閉症では知的障害を伴うケースが多いと
いえるが、しかし自閉症の特性(社会性)と知的障害は異なる次元である。知的障害と対比させると、高機能自閉症やアスペルガー症候群とは、知的能力に制約 がないが、社会適応能力に制約があるといえる。狭義には、自閉症とは3つ組と呼ばれる特性のすべて を満たすものである。その基準のすべてを満たしていなくても自閉症の特性が認められる場合は自閉症傾向と呼ばれ、自閉症のスペクトラム(連続体)の1つと
して捉えられる。典型的な自閉症児は生後1年で気づかれるが、自閉症傾向で知的障害を伴わないケースでは成人期に初めて診断を受ける場合もある。また児童 期に注意欠陥/多動性障害と診断されて、小学校高学年以降に自閉症に診断変更されるケースもみられる。注意欠陥/多動性障害には3つのサブタイプがあるが、不注意および多動性―衝動性の両者を示す混合型が多い。不注意優勢型は、緩慢な認知テンポが特徴であり、混合型とは異なるものであるとされる。混合型でも小学校高学年になると多動性が落ち着いてくるが、不注意は成人期に至っても持続する。
発達障害の運動面の障害として、特に学習障害やアスペルガー症候群で、タイミングやバランスなどの協調運動、微細運動の困難(不器用)がみられることが指
摘される。発達障害の診断とはそれぞれ異なる分類であるが、実際には診断が併存していることが多く、併存例では注意機能や行動抑制機能について臨床像が類 似しているため、鑑別診断が課題となっている。
(5)高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳外傷や脳血管障害など脳の器質的な損傷により、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会行動障害が生じたものである。交通事故によ
る脳外傷や脳卒中による脳血管障害など脳が損傷を受けたとき、身体の麻痺や筋骨格系の損傷を伴わない、もしくはそれらの運動障害が一定の回復をした場合、 あるいは顕著な失語症を伴わない場合に、このような認知障害は見過ごされることが多かった。高次脳機能障害とは、日常生活動作(ADL)の点では、基本的ADLは自立しているが、手段的ADLが 障害を受けている状態といえる。びまん性軸索損傷とは、頭部に直接外力が加わった損傷ではなく、頭部の回転角加速度運動により生じた衝撃(モーメント)に
よって、広い範囲の軸索(神経線維)や血管に断裂(剪断損傷)が生じることであり、交通事故の外傷で問題となる。このような頭部の回転角加速度による衝撃 の影響として、軽度のものは脳震盪であるが、重度になると脳幹症状が現れる。
遂行機能(エグゼクティブ・ファンクション)とは、心理学では実行 機能といわれ、即時的な反応を抑え、計画的、目標志向的で秩序ある柔軟な行動を支える制御機能のことである。遂行機能(実行機能)としては、プランニング
や自己モニタリング、行動や思考の切り替え、行動抑制などが挙げられる。社会行動障害とは、脱抑制による感情的な易刺激性や衝動性など対人関係における問題をさす。
認知障害という用語は高次脳機能障害について使用されることが多く、認知症(高齢者)や認知特性(発達障害)とは異なる。認知症も脳 器質の障害(病変)であるが、器質の病変が進行性であることと、記憶障害や見当識障害が特徴的である。それに対して高次脳機能障害とは、脳器質の損傷が進
行性ではないもの、として一応対比させることができる。認知症も高次脳機能障害も、一旦獲得された認知機能が失われることである。それに対して、発達障害 とは、発達期に認知機能を獲得することの障害(習得障害・学習能力障害)である。発達障害の認知特性とは、このような習得障害により、認知機能の個人内差
が極端になること(認知の凹凸)である。また、知的障害(精神遅滞)は、認知機能の獲得の全般的な遅れとして特徴づけられる。これらの認知障害や認知症、 認知特性という用語に対して、認知機能という用語はどの障害についても広く使用されている。高次脳機能障害(認知障害)、認知症、および発達障害(認知特
性)については、それらの認知機能の相違を意識して理解する。
3.自立支援のための連携と協働
ICFでは障害について身体レベル、個人レベル、及び社会レベルの3つ のレベルに分かれているように、障害には異なる側面が存在する。そのため障害者の介護や自立支援では、それぞれの側面に対して保健医療や社会福祉の領域の
複数の専門職種や機関が関与する。さらにそれらの側面は相互に影響しているため、障害の異なる側面を総合的に理解すると同時に、専門職種や機関の間の連携 や協働が求められる。また、ICFでは障害を個人と環境の相互作用として捉え、環境の促進因子と阻害因子によって障害の状態が変化すると考えるように、生活環境や地域社会との繋がりも重要になる。障害者の生活ニーズに社会資源を結びつける援助がケアマネジメントである。
障害の心理という場合、第2章で学習したように行動・認知・感情・意欲・人格といった客観的な側面の他に、当事者の体験としての障害といった主観的な側面も存在している。この主観的側
面としては、障害に対する心理的な適応や、生活目標、生きがいなどが含まれる。障害者の生活ニーズとは、障害の客観的な側面と主観的側面を併せたものとな り、それらはQOL(生活の質・人生の質)を構成している。また障害者本人だけでなく、家族などの身近な人にとっての障害という側面も存在しており、障害者の家族への支援も併せて求められる。リハビリテーションの治療的・代償的な機能回復訓練の対象とされる日常生活動作(ADL)について、生活圏の拡がりに応じて、基本的ADL(BADL)と手段的ADL(IADL)に分けられる。BADLとは、身辺の身体介助に関する食事や排泄、入浴、更衣などである。それに対してIADLとは、調理、洗濯、電話、買い物、交通機関の利用、金銭管理などである。これらのADLが自立していることは、1人暮らしをするための1つの目安とされ、ADLは生活自立や社会参加の基盤の1つ といえる。このようなリハビリテーションの治療的・代償的なアプローチに対して、リハビリテーションの全人間的復権の視点では、単に心身の機能を回復させ
るだけでなく、むしろ障害によって失われている人間らしい生活(生きがい、役割、尊厳など)を回復させることが目標とされる。例えば、上肢麻痺がある場 合、治療的・代償的アプローチで独力での更衣というADLの自立が目標とすると、更衣に時間を要して外出する機会が減ることになる。それに対して、全人間的復権の視点でICFの活動と参加の向上を目標とした場合、更衣の介助を受けることにより、ADLが自立していなくても、更衣を短時間で済ませることができるため、外出する機会(活動と参加)が増えると考えることができる。障害者の介護や自立支援において、自立とはADLの自立や経済的自立というよりも、人格的に自立していることであり、選択と自己決定を行うことによって生活の主体となり、バリアフリーや機会均等によって社会に参加することである。
最新の画像[もっと見る]