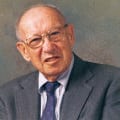今日のマコなり社長のインサイドストーリーズから
・疑問を持たなければ本を読むこと自体が目的化してしまい、なぜ本を読むのかを説明できないまま、手段だけをオススメする人になってしまう。それは、分かりやすい老害である。
【読書の本質的な4つの価値】
1.分からないことを知る価値
・分からないことを分かりやすく学ぶという点において、AIは無敵であるが、本は分からないことを生んでくれる側面もある。
・「具体的なイメージがつくように理解したい」と思っているときは、AIが圧勝する。一方で、本は書き手が読み手に対して分からないと思うことを作り出し、それを自己解決していく。問題を自分で作って自分で消していくような構造になっている。
・顕在化した「分からない」に対してAIは圧倒的だが、そもそも本は分からないことを生んでいることも忘れてはいけない。
2.感情が動く体験を得る価値
・感情が動くときは、ギャップがあるときであり、それを言い換えると、予定調和を崩すということである。
・自分にピタッとハマるような本を見つけることができたときの感情体験を、AIで代替することはまだ難しい。
3.具体と抽象のトレーニングの価値
・本に書いてあることをどのように自分の現実に落とし込むかを頭の中で想像すること。
・AIが出したアウトプットに対して、人間が評価をして責任を取る必要がある。その評価をするためには人間自身も抽象的なものから具体的な案を考えたり、具体的な事象から抽象的な法則を考えたりしなければならない。
★自分が具体と抽象を行き来するトレーニングをしていなければ、AIに正しく動いてもらうことができない。
・具体と抽象を行き来するトレーニングの良い機会として、読書がある。一定の文字量があり、読み進める中で少し手を止めて余白の中で考えてみることが大事である。この余白こそが読書の価値である。
★自分の頭で考えてみるという経験があればあるほど、AIをうまく使えることは間違いない。
★読書は自分の具体と抽象の行き来を強くしてくれる。
4.偶然の出会いの価値
・偶然の出会いを意図的に作ると、それは偶然ではなくなってしまう。
・AIを使っていると顕在化したものに答えてもらうという感じになってしまう。
・読書の4つの価値を最大化するためのアクションプランは、効率的に本を読もうとし過ぎないことである。
・仕事においては、利益を上げるためにやっているので「より効率的に」「生産的に」と考えるのは正しい。ただ、自分の教養を深めたり能力を高めたりするという意味では、逆算的に考え過ぎるとなにも学べなくなってしまう。
・読書の4つの価値を得るためには、寄り道が必要である。無駄な寄り道なしに効率は得られない。これはすごく矛盾している。「うわ、この本は微妙だった」と思う体験なしに、読書の価値は得られない。
・一定の無駄と失敗があるからこそ、ものすごく感動する本に出会えたり新しいやりたいことが見つかったりして、本の価値が最大化する。
・読書習慣を問題解決の手段に置き換えようとすると、まさに無駄を削り過ぎて非効率になっていく。要約だけを読んで本を読んだ気になるのは違う。
・本を読む前に、どのような価値を得たいのかを見定めると良い。
・やや抽象度の高いアドバイスやメッセージが出てきたら、自分の現実にどのように落とし込めるかを考えることが大事である。本で学んだことを人に説明するのも良いトレーニングである。
・偶然の出会いを受け入れるために、いつもだったら読まないような本も迷わず買ってみる。
・人生に変化を起こしていくためには、感情が動く体験を得たり自分の思考力を鍛えたり、考え過ぎずに偶然の出会いを受け入れたりすることも必要である。
・聞きたいことが決まっているのであれば、AIは素晴らしい道具なのでガンガン活用しよう。ただあまりにも効率に傾き過ぎると、どんどん非効率になっていくことを忘れないようにしよう。