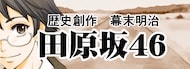あなたがもし、
「才能というのは神のようなものが授けてくれるものであるが
それを受け止める人はイタコだか神子のような存在。
だからそれによってもたらされたものは
皆が共有してよいはずだ」
と、考えるなら
これはとても日本的。
二次創作はこれがベースかも…。
あなたがもし、
「才能というのは自分の中にあって、天啓で目覚めるものである。
それに目覚める者は選ばれた存在。
だからその者が何かを作る行為は
小さな創造主と同じ」
と考えるならこれは
西洋的、ルネサンス的。
この考えはアートに通じる。
才能についての考え方は
この2つがあるのですが
ルーツも構造も考えずにすぐ混同するのは危険が伴いがちです。
私がデビューした雑誌は
みのり書房の月刊アウト別冊でしたので
二次創作を描いているというだけで
カミソリ入りの手紙をもらいました。
今時はすっかり認可されたようで
あの時に受けた攻撃は何だったのかと思ってしまいます。
私は自分の選んだ方法が正しかったのか
二次創作を正当な創作活動だと認めてもらうにはどうしたらいいのか
必死に探したのですが
結局は「ジャンル確立までの時間と認知度」に託すしかなかったかもしれない。
もともと著作権の考え方は
ルネサンス的なものだと思います。
そこにあって大事なのは「誰の作品か」という「主体」です。
最初に権利というのがなぜ主張されなければならないのかに
「作者はあくまでも人間である」というのがある世界だと思います。
一人の天才を「神」と崇めるにしても
神を越えるような傲慢は最大級の罪ですので。
ところが、キリスト教の無い日本の文化では
いともカンタンに本歌取りをし
琳派のようにリスペクトからのアレンジを行う。
西洋だと、ラファエル前派のようなものにしても、わざわざ一度反逆の意識を持っていたりするので
最初からキリスト教的な考え方をインストールされているかいないか
これは大きいです。
もっとも、ニーチェ以降を生きてる今の西洋人全てが二次創作アンチなわけがないですが
それでも「誰が描いているか」への意識や、その作品意図についての意識は
若干、日本より高くなると思います。
二次創作に著作権はあるべきだと
主張するのは簡単かもしれませんが
オリジナルを太陽
二次創作を月とした場合
太陽なら言うかもしれません。
「月は何を育てるのか」
無意味、無意識、ナンセンスであるカルチャーの素晴らしさを
相手の土俵でどう伝えられるのか。
「私たちは何をしているのか」
は説明できると思います。
問題は「それがどう有益であるか」
を
さして切望しない人に説明できるのか。
「これは創作された既存の世界観を共有して、その世界に生きる自分の言葉です」
というのがどこまで通用するか。
少なくとも「現実逃避」自体を否定された場合は難しいですよ。
まあ一番やりやすそうなのは
(あっちの土俵で話すとして)
「二次創作は作品解釈と批評の、最も創造的な一形式である」
これではどうかと思います。