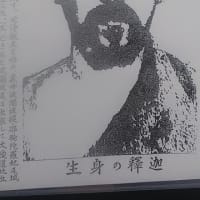ブッダの、
「真理のことば (ダンマパタ) 感興のことば (ウダーナヴァルガ) 」より。
原始仏典のうち、ブッダの教えを集めたもの。
無作為に選んで書き記します。 最終回です。今回の「ことば」も、当時の出家弟子向けに説かれたものを選出しています。われわれ一般人には難しい「ことば」です。
「生存に対する妄執を断ち切り、実体についての固執を断ち切った修行僧にとっては、生れをくり返す輪廻が滅びている。今や迷いの生存を繰り返すことはない」
「戒めを保っているいる人は修行僧であり、空を体現している人は瞑想者であり、専念している人はヨーガ行者であり、ときほごされて「やすらぎ」に帰しているところには安楽がある」
「裸の行も、髷 (まげ) に結うのも、身が泥にまみれるのも、断食も、露地に臥すのも、塵や泥を身に塗るのも、蹲 (うずくま) って動かないのも、 疑いを離れていない人を浄めることはできない」
※ 下線部 当時、仏教僧以外の行者たちが行っていた苦行のことと思います。
「身は飾っていたとしても、徳を行じ、耐え忍び、身をととのえて、慎み深く、行いが清らかで、生けとし生けるものに対して暴力を用いない人こそ、〈バラモン〉とも、〈道の人〉とも、また〈托鉢遍歴僧〉とも言うべきである」
「或る修行者・バラモンたちは、迷いの生存のうちに執著していて、煩悩の汚れを滅ぼすに至らないうちに、途中で没落してしまう」
「或る修行者・バラモンたちは、迷いの生存のうちに執著していて、互いに異論をいだいて論争する。これらの人々は愚者であり、一方だけしか見ていないからである」
※ 下線部、ここで言うバラモンとは、「道の人としてのバラモンではなく、カーストとしてのバラモン」のことと思われる。
「愚か者よ、螺髪 (らほつ) を結んで何になるのだ。かもしかの皮をまとって何になるのだ。汝は内に密林 (=汚れ) をいだいて、外側だけを飾っている」
「螺髪を結っているからバラモンなのではない。氏姓によってバラモンなのではない。生まれによってバラモンなのではない、と伝えられている。真実と理法とを守る人は、清らかである。彼こそ (真の) バラモンなのである」
※ 螺髪とは、わかりやすくいえば、大仏さまや如来像の、パンチパーマみたいな髪型・・・です。当時のバラモン階級の人たちは、螺髪を結っていたのでしょうか。
「人は水によって清らかになるのではない。人々はここで大いに沐浴している。真実と理法とを守る人は、清らかである。彼こそ (真の) バラモンなのである」
※ 今でもインドでは、ヒンドゥー教徒がガンジス川で沐浴しています。罪が浄化されると言うわけですが、ブッダは、「沐浴しても罪は消えない」と喝破されています。
実際、コロナ下の中、ガンジス川でものすごい数のヒンドゥー教徒たちが沐浴して・・・インドでコロナの感染爆発が起きました。
また、昔、真言行者と修験者が滝行や川で行をしているのに立ち会ったことがあります。定期的にやっていたそうですが・・・いい人たちではありますが・・・す凡夫でしたよ。
「もしもバラモンが自分のつとめに関して彼岸に達した (=完全になった) 時には、真理を観ずる彼にとって、一切の縁は消滅するであろう」
「もしもバラモンが自分のつとめに関して彼岸に達した (=完全になった) 時には、真理を観ずる彼にとって、一切の煩悩の汚れは消滅するであろう」
「もしもバラモンが自分のつとめに関して彼岸に達した (=完全になった) 時には、真理を観ずる彼にとって、彼の束縛の絆は全て消滅するであろう」
「もしもバラモンが自分のつとめに関して彼岸に達した (=完全になった) 時には、真理を観ずる彼にとって、彼は生まれと老いと死とを超えるであろう」
「太陽は昼に輝き、月は夜に照し、武士は鎧を着て輝き、バラモンは瞑想に専念して輝く。しかしブッダは常に威力をもて昼夜に輝く」
以上、「真理のことば (ダンマパタ) 感興のことば (ウダーナヴァルガ) 」の紹介終わります。
全体的に、ブッダ自ら語られたことばに加え、後々のお弟子さんの語られたことばが集積されたお経のような気がします。
これ以降は、「サンユッタ・ニカーヤ ブッダ 神々との対話 悪魔との対話」を紹介します。
・・・帰宅時、カーポートに車を入れた瞬間、かわいらしい「カゲロウさん」が飛んできて窓につきました。なにカゲロウかは判りませんが、白いカゲロウさんです。

・・・・・