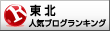毎年恒例、王祇祭を3週間後に控え、当屋へ準備にやってきました
今年の下座は、大杉川原村の清和治四郎さん
わたしも若勢頭の一人ということで、本格準備のため朝から参加しました。
本日の作業は、
当屋行事で使う各種道具を借りに座の宝蔵へ
そして、不浄払いを行ったあと
当屋各所に注連縄を張るといった作業になります

こちらは煎じ場になります。
王祇祭で振舞われる豆腐をここで焼きます。
今年は12表(30Kgで)、例年より1俵多いそうです。
3日間かけて次々に焼いていくんですよ。
このために別名豆腐祭りとも。。

こちらが囲炉裏になります。土の持ってあるところに串挿しされた豆腐をさして焼きます。
このままでは、串が汚れますので豆腐を作ったときにでたおからを土手として盛って水をかけながら焼き上げるんです。

注連縄をかけ始めてから短いということが発覚し、急遽足す作業をしております
若い世代には無理な作業になります。
伝えるためには、だれか覚えないといけないということはみんなわかっているんですが、
この祭りのときにしか使わない、しない作業になりますので
覚えてもすぐにわすれてしまいます。
意外にも、こういう技術って貴重なものなんだと毎年思っています。

最後に入り口に張りこれにて無事に御神体を迎えることができます。

いよいよ不浄払いです。
祭りにかかわる人間、また、使う道具や着物の不浄を払い
祭りの成功と無事に開催できることを祈願します。
今年はうちの長男が、大地踏という大役をうけておりますので、
演ずるときに着る着物も一緒に払っていただきました。

現在の床の間はこんな感じになっております
ここが春日神社ということになっています。
見えませんが、
大きく春日神社と書いてあります

こちらは祭りで使う花になります
非常に縁起がいいものです
各家庭に配られるほか、
注連縄と交換でもらうことができます

最後は当然この状況
けっしてすごいご馳走が振舞われるわけではありません
漬物、ご飯、味噌汁といった昔ながら物になります
欠かせないのは1番と呼ばれるお酒
ちゃんと燗主というものが朝から常駐していて
1日中お酒は振舞われております。
しかも樽に入って出てきますので
非常に香りよくて
おいしいんですよ。
いよいよ2月1日に向けてスタートしました。