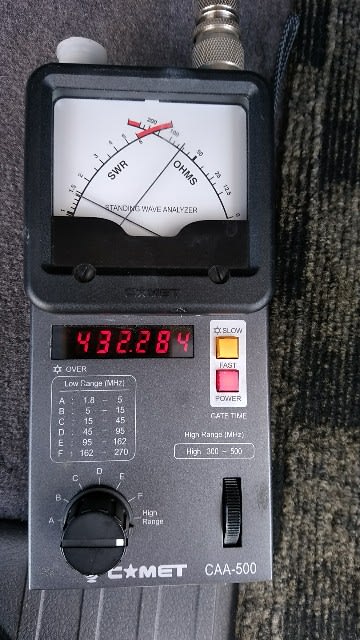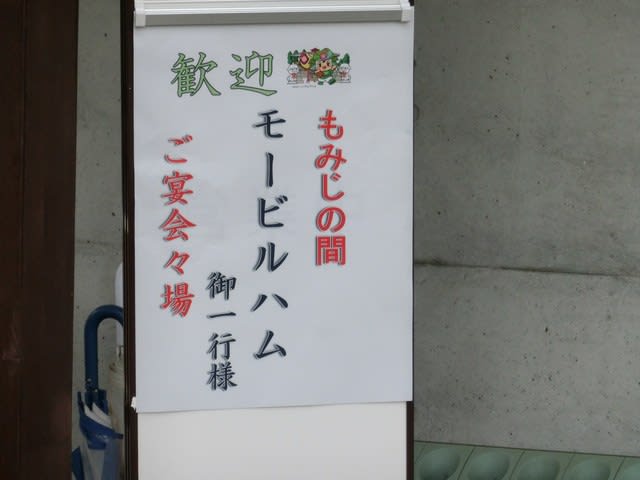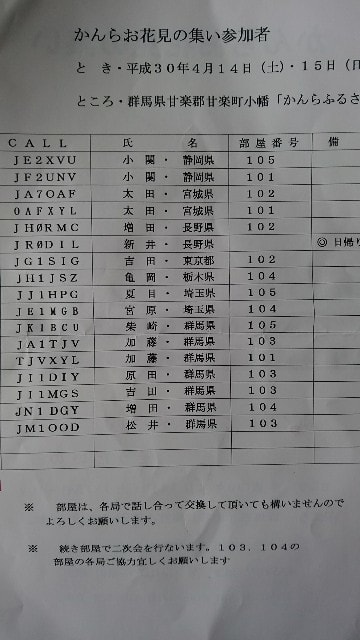今日は、息子を職場の近くまで送って行ったついでに、市内の鼻高町方面に寄り道をしてきました。
鼻高町は高崎市内にある町ですが直ぐ隣は安中市になります。
向こうに見える山は、任侠博徒の国定忠治や文学の流派の「白樺派」の発祥地、冬のオリンピックで初の銀メダルを日本にもたらした猪谷千春がスキーの練習に明け暮れた事で有名な『赤城山』です。

ここは、『鼻高展望花の丘』。
地域の人達が丹精込めて綺麗な花を育てています。
近くの鼻高小学校の児童も、授業の一環としてこの花の丘の手入れを手伝います。


花の丘からは、榛名富士を抱える榛名富士を含めた外輪山(榛名山)も綺麗に見えています。
榛名山は、赤城山、妙義山の2つの山と合わせて、上毛三山の1つに数えられています。
右端の山は水澤山。この水澤山の中腹には、水澤観音堂が鎮座し、山門界隈には、日本三大うどんの一角を担う、『水沢うどん』の店が建ち並んでいます。
また、この山の裏側には、伊香保温泉があり、木暮旅館や福一旅館、千明旅館等々、平家の落人が拓いた温泉旅館が軒を連ねています。
伊香保温泉は、北辰一刀流の開祖、千葉周作と縁があります。
千葉周作が若かりし頃に、江戸で馬庭念流(現:群馬県高崎市吉井町)の使い手と戦い敗れてしまったために、再度、馬庭念流に挑戦するために、上州(群馬県)に出向き、馬庭念流の使い手と試合を行い、ことごとくその使い手を打ち破ってしまったのだそうです。
破れた馬庭念流の使い手は、千葉周作に惚れ込み、馬庭念流の使い手やその多くの門弟達は、北辰一刀流に帰依してしまったのだそうです。
その記念として、北辰一刀流に帰依した門弟達が、武道額を伊香保神社に掲げようとして、馬庭念流一門の逆鱗に触れ、一発触発の事態になってしまい、大きな戦いの場になるところでしたが、馬庭念流の使い手だった木暮武太夫(木暮旅館館主)らと千葉周作との話し合いによって、事無きを得たという有名な場所が、この伊香保温泉なのです。
伊香保神社下の片隅に、それを語る石碑がひっそりと昔を偲んでいますが、この話は、今は殆ど知られてはいません。
ちなみに、千葉周作が初めて開いた北辰一刀流の道場は、高崎市冷水町(旧群馬町冷水(ひやみず))の佐鳥家の馬庭念流の道場を変えてつくられました。
『北辰一刀流』の“北辰”とは、北斗七星から名付けられました。また、“一刀”とは、千葉周作が最初に剣術を習った流派が一刀流だったので、北斗七星と一刀流を合わせて『北辰一刀流』と言う名前にしたのです。
北辰一刀流は、多くの門弟を輩出し、明治維新に貢献した坂本龍馬も名だたる門弟の一人でした。
高崎市国府町に妙見様・・正しくは『北斗妙見菩薩』という、今は無人の寺院があるのですが、この寺院が、まさに北斗七星を奉っている寺院なのです。千葉周作の守り本尊が、代々この北斗妙見菩薩だったのですが、上州金古宿国府村(現:群馬県高崎市)の佐鳥家に道場を作ったおりに、近くに自分の家の守り本尊がこの地にある事を知った千葉周作は、たいそう喜んだと、伝えられています。なお、この『北斗妙見菩薩』は、全国3カ所ある内の1つです。
また、大正ロマンを代表する竹下夢二の恋人も伊香保温泉の有名な旅館の娘でした。
第二十代総理大臣の高橋是清の娘も、ここ伊香保温泉の旅館に嫁いでいます。
まだまだ、語りたい実話があるのですが、長い話になるので、割愛します。


この丘は、地域の宝としてみんなが参加して年間を通して綺麗に管理されているのです。
鼻高の丘から見える景色を見ていると、心地好い春の風が頬を撫でながら通り過ぎて行きます。

遠くに見える浅間山の雪は、かなり溶けていますね。

浅間山から左に目を向けると、荒船山がよく見えます。
荒船山は、数年前にクレヨンしんちゃんの作家が訪れて、そこで帰らぬ人になってしまった山でもあります。

カメラのズームを引いた荒船山方面の写真です。
左に荒船山、右に妙義山
妙義山と言うのは、白雲山、金洞山、金鶏山、相馬岳、御岳、丁須の頭、谷急山などを合わせた総称で、表妙義と裏妙義に分かれています。
左から船が右の荒波(妙義山)に向かって進んでいるように見えるところから、荒船山という名前がつけられたようです。
まあ、諸説ありますが。
鼻高花の丘の直ぐ近くには、ダルマで有名な、『少林山』があります。

この少林山ですが、ご免なさい。正式名を忘れてしまいました。
ネットで調べれば出てきますが、今は、ちょっと面倒。
この寺は、黄檗宗派の寺院で、普段はとても静かなお寺ですが、正月などは、他県からも参拝客が押し寄せて、かなりの人混みになります。


鼻高町は高崎市内にある町ですが直ぐ隣は安中市になります。
向こうに見える山は、任侠博徒の国定忠治や文学の流派の「白樺派」の発祥地、冬のオリンピックで初の銀メダルを日本にもたらした猪谷千春がスキーの練習に明け暮れた事で有名な『赤城山』です。

ここは、『鼻高展望花の丘』。
地域の人達が丹精込めて綺麗な花を育てています。
近くの鼻高小学校の児童も、授業の一環としてこの花の丘の手入れを手伝います。


花の丘からは、榛名富士を抱える榛名富士を含めた外輪山(榛名山)も綺麗に見えています。
榛名山は、赤城山、妙義山の2つの山と合わせて、上毛三山の1つに数えられています。
右端の山は水澤山。この水澤山の中腹には、水澤観音堂が鎮座し、山門界隈には、日本三大うどんの一角を担う、『水沢うどん』の店が建ち並んでいます。
また、この山の裏側には、伊香保温泉があり、木暮旅館や福一旅館、千明旅館等々、平家の落人が拓いた温泉旅館が軒を連ねています。
伊香保温泉は、北辰一刀流の開祖、千葉周作と縁があります。
千葉周作が若かりし頃に、江戸で馬庭念流(現:群馬県高崎市吉井町)の使い手と戦い敗れてしまったために、再度、馬庭念流に挑戦するために、上州(群馬県)に出向き、馬庭念流の使い手と試合を行い、ことごとくその使い手を打ち破ってしまったのだそうです。
破れた馬庭念流の使い手は、千葉周作に惚れ込み、馬庭念流の使い手やその多くの門弟達は、北辰一刀流に帰依してしまったのだそうです。
その記念として、北辰一刀流に帰依した門弟達が、武道額を伊香保神社に掲げようとして、馬庭念流一門の逆鱗に触れ、一発触発の事態になってしまい、大きな戦いの場になるところでしたが、馬庭念流の使い手だった木暮武太夫(木暮旅館館主)らと千葉周作との話し合いによって、事無きを得たという有名な場所が、この伊香保温泉なのです。
伊香保神社下の片隅に、それを語る石碑がひっそりと昔を偲んでいますが、この話は、今は殆ど知られてはいません。
ちなみに、千葉周作が初めて開いた北辰一刀流の道場は、高崎市冷水町(旧群馬町冷水(ひやみず))の佐鳥家の馬庭念流の道場を変えてつくられました。
『北辰一刀流』の“北辰”とは、北斗七星から名付けられました。また、“一刀”とは、千葉周作が最初に剣術を習った流派が一刀流だったので、北斗七星と一刀流を合わせて『北辰一刀流』と言う名前にしたのです。
北辰一刀流は、多くの門弟を輩出し、明治維新に貢献した坂本龍馬も名だたる門弟の一人でした。
高崎市国府町に妙見様・・正しくは『北斗妙見菩薩』という、今は無人の寺院があるのですが、この寺院が、まさに北斗七星を奉っている寺院なのです。千葉周作の守り本尊が、代々この北斗妙見菩薩だったのですが、上州金古宿国府村(現:群馬県高崎市)の佐鳥家に道場を作ったおりに、近くに自分の家の守り本尊がこの地にある事を知った千葉周作は、たいそう喜んだと、伝えられています。なお、この『北斗妙見菩薩』は、全国3カ所ある内の1つです。
また、大正ロマンを代表する竹下夢二の恋人も伊香保温泉の有名な旅館の娘でした。
第二十代総理大臣の高橋是清の娘も、ここ伊香保温泉の旅館に嫁いでいます。
まだまだ、語りたい実話があるのですが、長い話になるので、割愛します。


この丘は、地域の宝としてみんなが参加して年間を通して綺麗に管理されているのです。
鼻高の丘から見える景色を見ていると、心地好い春の風が頬を撫でながら通り過ぎて行きます。

遠くに見える浅間山の雪は、かなり溶けていますね。

浅間山から左に目を向けると、荒船山がよく見えます。
荒船山は、数年前にクレヨンしんちゃんの作家が訪れて、そこで帰らぬ人になってしまった山でもあります。

カメラのズームを引いた荒船山方面の写真です。
左に荒船山、右に妙義山
妙義山と言うのは、白雲山、金洞山、金鶏山、相馬岳、御岳、丁須の頭、谷急山などを合わせた総称で、表妙義と裏妙義に分かれています。
左から船が右の荒波(妙義山)に向かって進んでいるように見えるところから、荒船山という名前がつけられたようです。
まあ、諸説ありますが。
鼻高花の丘の直ぐ近くには、ダルマで有名な、『少林山』があります。

この少林山ですが、ご免なさい。正式名を忘れてしまいました。
ネットで調べれば出てきますが、今は、ちょっと面倒。
この寺は、黄檗宗派の寺院で、普段はとても静かなお寺ですが、正月などは、他県からも参拝客が押し寄せて、かなりの人混みになります。