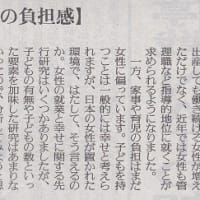カレーが大好きなので,本書のタイトルに惹かれて読んでみました。
日本で食べるカレーと本場のカレーでは違いがあることはわかるが,カレーそのものを否定した書き方には違和感がありました。
インドではもともと野菜や肉を炒めた料理があって,それを「kari」「karil」と言ったそうです。
当然煮込んでスパイスを入れる料理もあるのだからそれがカレーでいいだろうと思うのだけど,なぜそれを否定するのかわかりませんでした。
イギリスがインドを植民地化していた時にそれを進化させて現在のカレーが出来上がったのだからもともとカレーのルールはインドにあったということになるでしょう。
たくさんのスパイスを混ぜてカレー粉を作ったのがイギリス。
それだけのことです。
それが本書を読んでわかったことであり,屁理屈ばかりが並んでいるように思えました。
否定した後にすぐ肯定する文章が出てくるのは著者の表現力に問題があるのかもしれません。
ただし,インド,パキスタン,中国などの隣国との関係を記載したところは面白かったと思います。
ブックカバーには本書の概要が以下のように記載されています。
カレーを「スパイスを用いた煮込み料理」と定義すれば、そこには数え切れないほどたくさんのインド料理が含まれる。日本でイメージされる「カレー」とはかけ離れたものも少なくないーー在インド日本大使館にも勤務した南アジア研究者がインド料理のステレオタイプを解き、その実像を描き出す。インド料理店の定番「バターチキン」の意外な発祥、独自進化したインド中華料理、北東部の納豆まで。人口世界一となった「第三の大国」のアイデンティティが、食を通じて見えてくる!