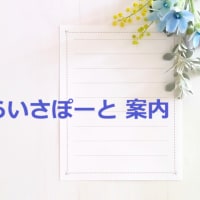『子どもが心配~人として大事な三つの力』養老孟司著PHP新書
この本は4人の識者と養老さんとの対談集となっているが、
脳研究で現代人の環境がどこまで人間の発達に影響を及ぼしているかといった、
一見難解そうであるが対談形式で大変面白く興味深く読める。
第3章「子どもの脳について分かったこと」で小泉英明氏は、
発達に応じて睡眠のリズムを乳幼児から正しく作っていくことが大切だが、
ASDの場合、日周リズム(朝に日が昇り明るくなり夕方に日は沈み夜は暗くなる)の習得が上手くいかないことがある、と述べている。

確かに赤ちゃんの時はあまり泣かずに手がかからなかったとか、
反対に急に夜中に火が付いたように泣きだすとか、
いつまでも寝ないで母親も子どもも疲れ果ててしまうとか、
日周リズムを通常の発達のように習得していくことが難しいのかもしれない。
しかしいつまでもその症状が続くのかというとそうでは無く、
通常の生活リズムの中で徐々に習得していけるものだと思っている。
その場合、その子どものASD特性によって通常の生活リズムを分かりやすく構造化する必要はある。
そんなに難しいことでは無い。基本は定時に起床、食事、日中活動、就寝で、その場面を分かりやすくしてあげればいい。
難しいのは不安定な子どもの状態に付き合う親の精神的体力が持つかどうか、だ。
頼れる親族が近くに居れば多少は気を休めることができる。
またレスパイトのために福祉サービスを利用することも可能だ。
しかし、基本的なリズムは家庭で過ごしながら身につけていくことになる。
そもそも愛着形成が難しい中で、
ぐずる子どもをなだめるのは誰か。
多動な子どもを迷子にならないよう見守るのは誰か。
こだわりに付き合うのは誰か。
兄弟関係で神経を使うのは誰か。
学校教育や行事に関しても、親の気の休めるところはなくクタクタになってしまうのである。
この時期、個人の時間を持つことが限られてくる。それもキツイ。
だがその時期が永遠に続くわけではない。
信頼できる支援者に話を聞いてもらい、親として今できることを無理をせず粛々と積み上げて行けば、
ゆっくりと、確実にその子らしい成長の姿を親に見せてくれるようになる。
てんかんなど他の疾病や障害を抱えている場合もあるので対処の仕方は様々だと思うが。
まわりと比べて何故自分だけがと悲しみや怒りが生じてくるのは仕方が無い。
そんなやるせないときもあって当然だがいつまでも負の思いを抱え込んでいていても、やはり仕方が無い。
思い悩むより体を動かすことだ。
そんな親の姿をまわりは見ている。子どもは一番よく見ていると思う。