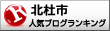土偶から見て草創期早期は具象的表現

前期に入ると土偶は、得体の知れないものになり、抽象的な何か見えないものを造形したように見える

縄文時代草創期から前期初めまでは、生業開発の時期で、道具開発が主となり
同様に土器の模様は、それを表現するために造形表現していたのだろう
撚糸文、羽状縄文土器までは具体的なものを模様で表現していたものと思う

太陽暦開発などは表現しようが無く、象徴的な数字を波状突起口縁の土器で表現していた

図はお借りしました
引用ーーーーーーーーーーーーーー
■7.「縄文」土器の「縄」と「しめ縄」の意味するところ
そもそも「縄文」土器の縄模様も、縄文人の死生観を明かしています。この縄模様が一万年ほどにもわたって、土器に付けられ続けたからには、よほど確たる理由があるに違いありません。
縄文土器には、よく蛇がそれとわかるデザインで登場します。蛇は冬眠をします。冬の間に冬眠し、春になると目覚める。それはあたかも死から蘇ったように縄文人たちは捉えたことでしょう。そこから蛇は「再生」のシンボルと捉えられました。
その蛇が交合する様は、まさに神社のしめ縄のように二匹が絡み合います。いえ、逆にしめ縄は蛇の交合を象徴していると考えられています。その交合の様を縄で模倣し、その縄を土器の表面に押しつけて「縄文」をつけたのです。
土器は煮炊きによって食べ物の種類を大きく広げ、気化熱で内部の温度を下げることで食べ物の保存を可能にしました。人々のいのちを支える有り難い道具でした。その土器に「縄文」をつけることで、中にいれる食物に「再生」の力を伝え、それを食べることによって「再生」の力を我が身に取り込む。
それは家族の健康長寿と子孫の繁栄を願う、という祈りだったのではないでしょうか。現代の我々が神社で神に祈るのは、無病息災、安産、七五三での子供の元気な成長、というような事でしょう。しめ縄のもとで、そのような祈りをする我々の心は、1万年も縄文土器を作り続けてきた縄文人の心に、思いのほか近いのではないでしょうか。
円環的死生観、精霊信仰、そして神社での祈り。我々日本人の「三つ子の魂」は、縄文時代に形成されたのです。
(文責 伊勢雅臣)