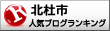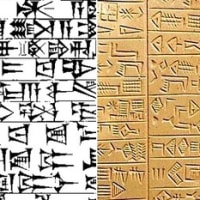大阪や奈良盆地地域での古墳の中軸方位はバラバラ
大きく見て、佐紀古墳群のみ南北方位で後円部を北に向けている。
畿内の古墳の方位

図に示す古墳の方位は注目されていないようで、余り正確ではないようです、以下同様です。
どうやら古墳時代末まで古墳の中軸方位が一つに統一されることはなかったようだ
それは中央集権政権により統制することがなかったのか、あるいは統制する力を持った集権政権はなかったということか。

地方に於いても古墳の方位はその地域に応じて例えば富士山の噴火の影響が強い埼玉地域ではその方向を向くような状況のようだ。
しかし古墳時代末期の河内大塚古墳は前方部を北に向け、聖方位なのだろうか 北から20度西へ傾いているように見える。

見瀬丸山古墳も同じである様だ。今城塚古墳も同様。ここに来て大古墳は南北方位となりしかも前方部を北方に向けることになった。
訂正します。 今城塚古墳はその後の調査で立春方位のようです。

古墳の方位はあまり正確ではありません。
また墳丘にも特徴があり、剣菱形というのが確認されているのは、
畿内の今城塚古墳
河内大塚山古墳、
見瀬丸山古墳
鳥屋見三才(鳥屋ミサンザイ)古墳と、
東国の武蔵の埼玉古墳群の瓦塚古墳、
下野の塚山古墳(宇都宮市南部)
くらいであって、極めて数が少なくなっていたという。
その築造時期は五世紀後葉から六世紀前半頃にかけてとみられる時期になるようだ。
これらは北方に前方部を向けていることからは、佐紀古墳群とも異なり、それまでの古墳築造とは異なる指向が入って来ているようだ。
これ以後の大王墓については、今城塚古墳と同じ剣菱形前方後円墳であり、
古市古墳群の西方の高鷲の地に営まれた河内大塚古墳(大阪府豊中市、三三〇メートル)や、
奈良盆地南部の身狭の地に営まれた見瀬丸山古墳(五条野丸山古墳)(奈良県橿原市、三一〇メートル)などがあげられるとも云われている。
これら二つの古墳は、その始祖である今城塚古墳の近くに営まれることもなく、また旧来の有力な古墳のなかに含まれるわけでもない。その巨大さにより、大王権力が従来にまして隔絶したことが理解できるが、その地域的・氏族的基盤を離れていることが注目されるという。

この段階に来て初めて大王墳は、連合政権としてのヤマト政権の盟主の地位を示すものから、諸豪族から完全に超越した権威として確立したものに変質したものと理解され、またそれは単なる同盟の盟主として従来のようにその構成員が交替しうる性格のものでなくなっていることを示すもので、その権力を支える勢力の動向とも関連して、転々と陵墓は移動するようになったようだという。
ここで縄文時代以来の、太陽暦を作るための立春観測は、纏向遺跡廃止以後には廃止され、冬至と夏至が重視されることになり、太陰太陽暦のようなものへと変わったのだと思う。
超大型古墳が作られ、鉄器時代に入ると共に権力集中が起きて権力による暦の支配が始まったことになったのだろうか。
こうしたことから見て
弥生から古墳時代の半ばまでは東西方位を向いていた縄文時代以来の太陽祭祀は排除され、古墳時代の最後にチャイナや騎馬民族の南北方位重視に変わったように思う。
図はお借りしました