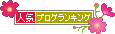神や仏の存在を感じるような不思議な経験は未だかってないのだが、金縛りは2度ほどある。又、オレンジ色に空を染める秋の夕陽を見た時など、ふとした出来事に自然の摂理と人間の宿命を感じることがある。そんな時畏敬をもって私は「天」という言葉を憶うのだ。
「天の声」とは何か。
私は、人が自我に目覚めるように、自分自身の存在そのものについてある種の覚醒をした時に脳裏に浮かんでくる言葉が天の声ではないのかと考えているのである。天は優しく思いやり深く、時として厳しく冷酷で、人生において幾度となく我々に警告を発するものだ。それを傲慢不遜に無視し続ければ、いつの日か報いを受けるのである。聞き入れがたき声もあろう、それゆえに天の声を聴くことは辛いことかもしれぬが、受け入れ得られれば反面救いの言葉でもあるのだ。
又、天佑、天罰という言葉を考える時、特別な才能を与えられることは天の特別な恵みであり、才能を与えられた人間が、その才能を生かす努力をすれば佑けがあり、せねば罰がある。才能を与えられていない人間には罰も佑けもない。天佑とか天罰とかは天恵を授かったものがそれに如何に処したかによって下るものなのだと考えるのである。
そう考える時、人間の不遜と傲慢を思う。天の何処かから、人間に「お前は万物の霊長である」とのご託宣でもあったのか、人間が自分でそう言っているにすぎぬではないか、自画自賛の我田引水ではないか。敬虔な気持ちで畏れる心はあるのか。
人間以外の動物は原始的本能が満たされれば休むのである。已めるのである。自然の摂理に従うのである。人間のみである、貪り尽くしても已めないのは。イナゴは大量発生し食べ尽くして自らは滅びる。人間はこの地球を食べ尽くしても、まで已めないだろう、より以上の便利さや快楽を追求する欲望を満たすために。欲望を満たすための知性なのだ。
人間は、その欲望を満たさんとするその知性故に滅びるのではないか。人間ほど自然の摂理に逆らい、万物の霊長などと驕り高ぶり、この地球に害しているものはないのではないか。私は個々の人間のことを言っているのではない、人間総体としての人類のことを言っているのだ。
人類が滅びてこそ神が存在することになるのではないか、と思うことがある

出来上がっているこの世の仕組みを変えたり、止めたりすることは簡単ではない。否、尋常でなく困難である。
出来上がっている仕組みのその中で、人は複雑に利害を絡めて生きているからだ。省庁の天下りや社会保険庁の不正などは無くなるはずがないのだ。正義漢ぶった非難中傷をそれが大衆の嫉妬だと彼らは知っているし、我々も気付いている。
役人になりたければなればいいのである。なれもしなかった者がなれたら自分もするであろうことを、なれずに出来ないばかりに嫉妬しているのである。そんな正義感など甘い汁でも少し吸わせればなし崩しに消えてゆくのである。人間の本性を考えてみるがいい。自らの心の深奥を見つめてみるがいい。
人間社会の仕組みは利権を生み出し、その利益の配分に人は与るのである。そして利権を得たものが利益を配分することによって受益者の支持を得のさばってゆくのだ。それは階層的になるのである。そして指弾されることがあっても恐怖が無ければ人はのらりくらりと何とでも言い逃れをしようとするものだ。そして出来てしまうのだ。
故に、時として必然の如くテロが起きるのである。暴力による世直しが起こるのである。それによって作り上げられる次の体制もまた、続けば同じく澱む。同じことが繰り返されるのである。高々100年続いていることを永遠に続くと考える方が可笑しい。
人の世は、同じ体制が100年も続けば流れと同じくその血は澱むのである。澱んだ血は肉を切って外へ出すのである。仕組みを壊すことは何であれ一種の革命である。作り上げた時の労力の度合いと壊す時の悲惨は比例する。それは命の量即ち血の量なのだ。
革命は絶対的に血を欲する。そして革命の質は流した血の量に比例するのだ。それは善悪理非で論ずるものではないのである。

パグ犬きなこの写真日記














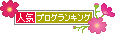
 は昨日、朝シャンプーをして、ペットの撮影会がショッピングモール「エミフル」であったので、散歩がてら行ってきました。2番目だったそうです。歩いて結構距離が有るので、ハァ~ハァ~言っている変な顔のまま撮られたそうです。さて、どんな顔に映っているやら、次回の無料雑誌Collarが少し楽しみです。
は昨日、朝シャンプーをして、ペットの撮影会がショッピングモール「エミフル」であったので、散歩がてら行ってきました。2番目だったそうです。歩いて結構距離が有るので、ハァ~ハァ~言っている変な顔のまま撮られたそうです。さて、どんな顔に映っているやら、次回の無料雑誌Collarが少し楽しみです。