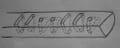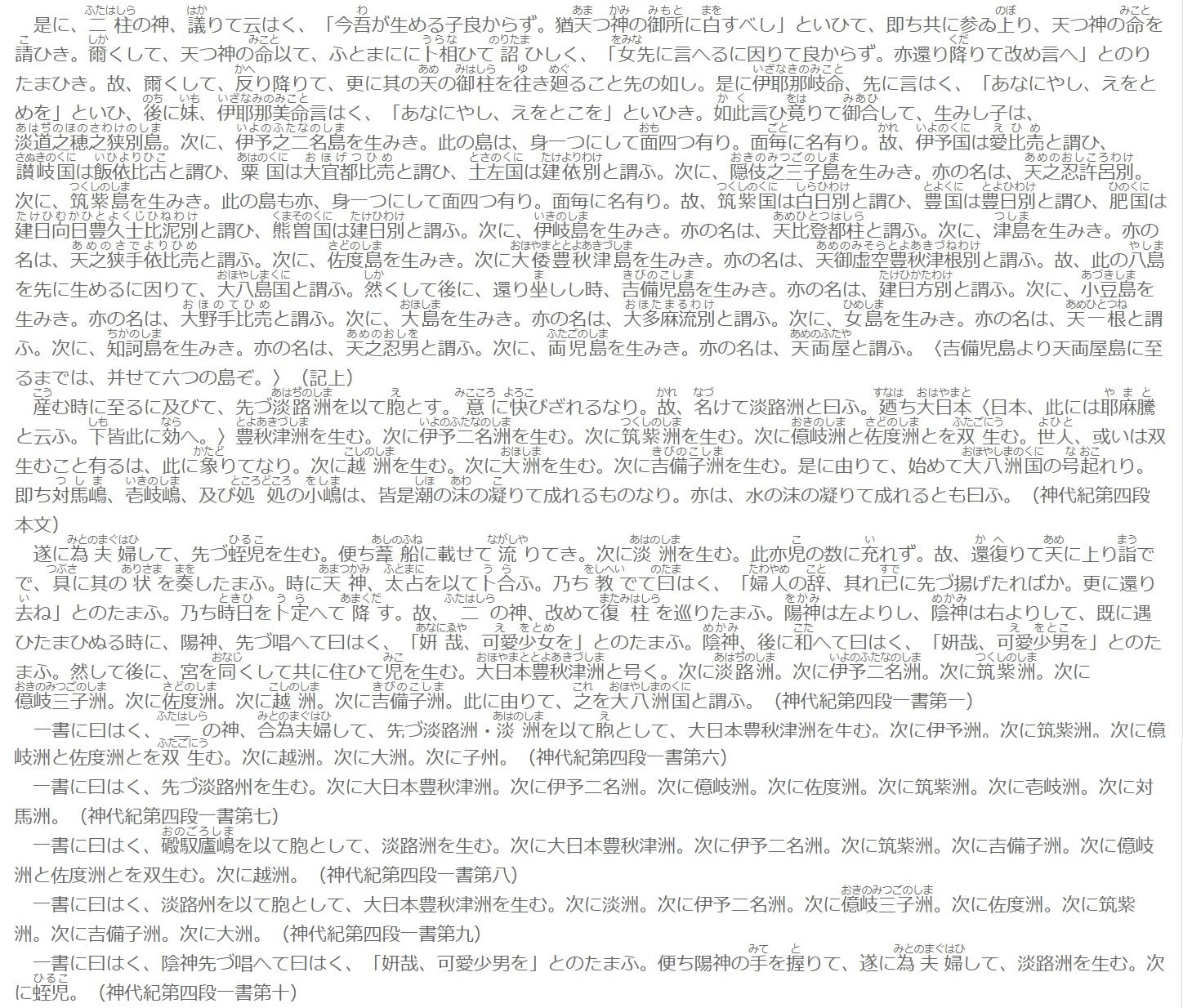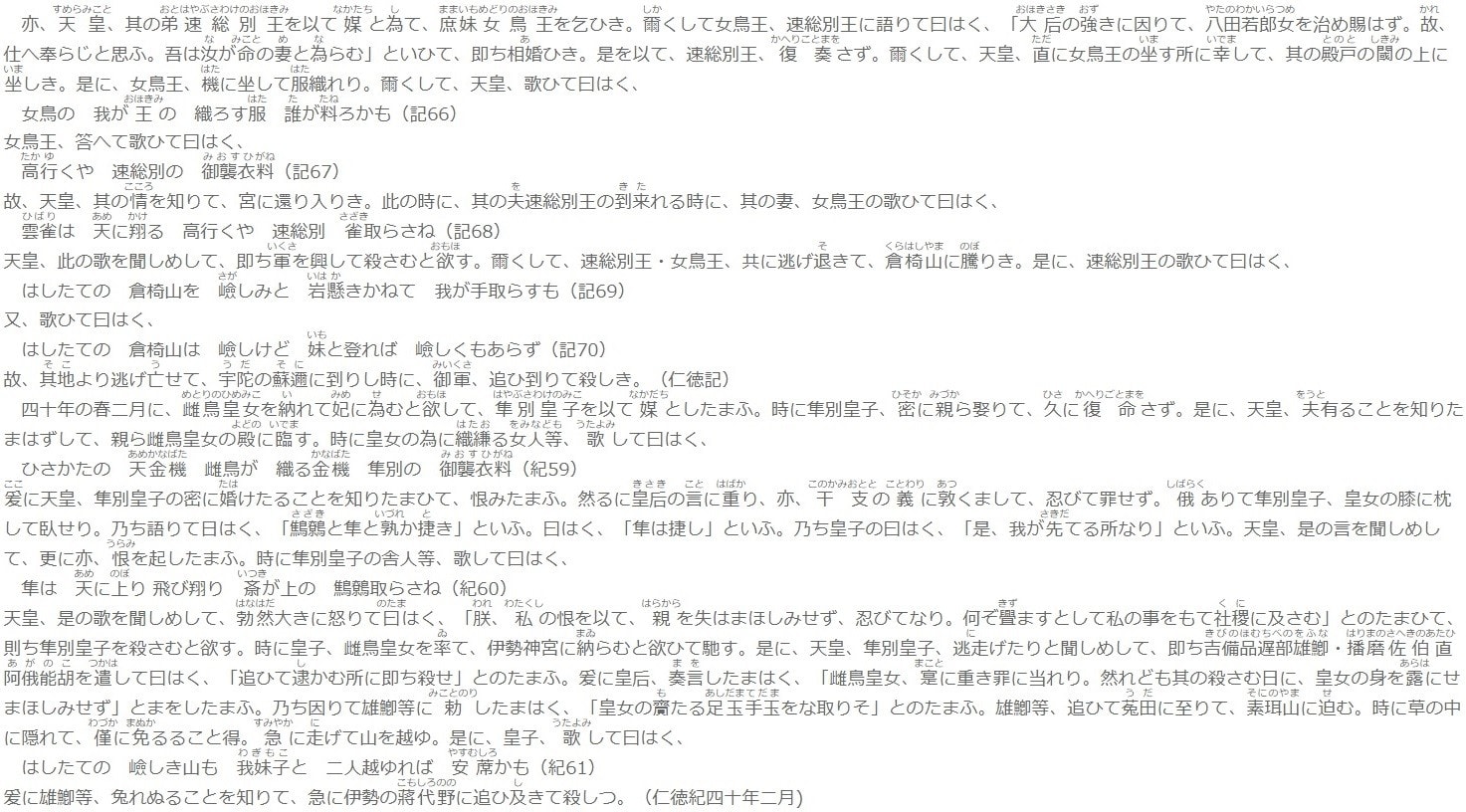万葉集で、慣用的に「恋ひつつあらずは」という言い回しが使われている。
上代におけるズハの用法は、文法学的にとても難しいものと思われている。「ンヨリハ」説(本居宣長)、「ズシテハ」説(橋本進吉)以降もさまざまに解釈されてきている。同じズハの形であるのに巧妙に訳し分けることが行われている
(注1)。以下の用例では現状の解釈を示すために多田一臣氏の訳を引く(傍点筆者)。
かくばかり 恋ひつつあらずは
高山の
磐根し巻きて 死なましものを(万86)
こんなにばかり恋い焦がれ
てはいずに、いっそ高い山の岩を枕に死んでしまいたいものを。
立ちしなふ 君が姿を 忘れずは 世の限りにや 恋ひ渡りなむ(万4441)
しなやかに立つあなたの姿を忘れ
ずに、生きている限り恋い続けることだろうか。
三諸の 神の帯ばせる
泊瀬川 水脈し絶えずは
吾忘れめや(万1770)
みもろの神が帯にしておられる泊瀬川、その流れが絶え
ないかぎりは、私はあなたをどうして忘れることがあろう。
夕々に
吾が立ち待つに けだしくも 君来まさずは 苦しかるべし(万2929)
夕べごとに私は立って待っているのに、もしも万一あなたがおいでに
ならないとすると、つらいことに違いない。
筆者はズハという結びつきによって構文が成されたものであるとは認めない。すなわち、ズハという言葉を連語として有意であるとは考えない。仮定や比較を表すとは見なさないのである。考えないのだから、ズハの前項が未実現か既実現かを考慮して仮定の用法を分類して事態の先後関係を順行、逆行と仕分ける
(注2)には及ばないと考える。実例に沿って議論を進めてみよう。
ズハのある文には、「まし」を伴うことが多い。
かくばかり 恋ひつつあらずは 高山の
磐根し巻きて 死なましものを〔如此許戀乍不有者高山之磐根四巻手死奈麻死物乎〕(万86)
「まし」は反実仮想を表す。現実の事態に反した状況を想定し、もしそうなら、これこれの事態が起こったであろうのに、と想像する気持ちを表す。「ものを」は「もの」と「を」が複合した間投助詞で、順接にも逆接にも使う。「まし」で現実に反することを仮想しておき、「ものを」で逆説的に現実に帰る機能を果たしている。
「まし」の使い方としては、「ませば……まし」、「ましかば……まし」が基本形であり、前件が省略されることがある。省略されていても意味が通じるからである。
万86番歌の例で省略を補ってみれば、次のような構文になるであろう。
「かくばかり恋ひつつあらず」ハ「(死なませば)高山の磐根し巻きて死なまし」モノヲ
ハの前は、これほどに恋しつつあることがない、の意である。
ハの後は、もし仮に死ぬとするなら高山の磐根を巻いて死にたい、のだけれどなあ、の意である。
この両者が、助詞ハによって結ばれており、文章全体の骨格を決めている。
これほどに恋しつつあることがないのは、もし仮に死ぬとするなら高山の磐根を巻いて死にたい、のだけれどなあ、という回りくどい言い方をしている。
これを例えば、こんなに恋しているくらいなら高山の磐根を巻いて死んだ方がましだ
(注3)、の意に解するのは誤りである。第一に、当時は人生を肯定的に捉える傾向があり、「恋ひつつあり」が辛い状態にあるとは考えにくい。第二に、助動詞「まし」の語義を、「益し」の意と捉えることは間違いである。第三に、「高山の磐根し巻きて」の修辞的意味を封殺したら、何のために歌を考えひねり作っているのかわからないことになる。
どうして「高山の磐根し巻きて」という表現が生まれているのか。
それはこれが恋の歌だからである。恋をして男女は同じ枕を巻いて寝る。「巻く」は「
娶く」と同根の語で、妻として抱く意を包含する。すなわち、この歌では、共寝すること、恋をすることに対して否定的な言動は一切見られていない。前半で恋を否定しておいて、そんなことはとてもじゃないが嫌な話で、当然ながら死ぬのは同等に嫌なこと、つまりは、仮に死ぬとするなら彼女を娶かないで、共寝の枕を巻かないで、高山の岩盤なんかを巻いて首吊りするほどに嫌なことだよなあ、と言っている。
本当に言いたいことは、それとは真逆のことである。このように恋し続けていって、首吊り自殺なんかしないで枕を共にしながら生きていければいいよなあ、ということである。首にロープを巻くのではなく彼女を娶いて生きていければいいよなあ、このように恋を続けて、という意である。
「恋ひつつ」とは、恋して恋して、の意である。「つつ」という言い方の「つつ」は、二つながらにあることを示している。「恋ひつつ」とは、恋して恋して、の意である。ハの後でも「巻く」ことが二つながらにあることを示唆している。首にロープを巻くのか、腕を巻くのかである。「ハ」は前と後とをつなぐ助詞である。前と後とがつながるものであることを支持する要素として、両者が絡みんでいることの明示となっている。言葉に忠実な表現が行われている。
かくばかり 恋ひつつあらずは 朝に
日に 妹が踏むらむ
地にあらましを〔如是許戀乍不有者朝尓日尓妹之将履地尓有申尾〕(万2693)
「かくばかり恋ひつつあらず」ハ「(地にあらませば)朝に日に妹が踏むらむ地にあらまし」ヲ
このように恋をしつづけないということは、どういうことかというと、もし仮に私が地面になるのであれば、朝に昼に彼女が足蹴に踏みつける地面でありたいというとんでもない倒錯になるよなあ、の意である。
当たり前のことであるが、人間が地面になることはない。反実仮想である。仮に地面になるとして、最悪のなり方は朝や昼に足蹴にされる地面になることである。これは恋の歌である。恋の時間で大切なのは夜である。夜に足蹴にされることは、M的な性癖を持っていたらひょっとすると許されたり喜ばれたりするかもしれない。ところが、朝や昼に踏みつけられる地面になるとはそういうことではなく、ただ路盤になるということである。冗談じゃないのだが、それが恋を続けないということだと言っている。つまりは、これまでどおり恋を続けていきたいと高らかに歌っている。「つつ」の二つ性が指しているのは、「朝に」と「日に」でもあり、「朝に日に」と「夜に」を暗示したものでもあり、あるいは「踏む」足が右足、左足であるからでもある。
吾妹子に 恋ひつつあらずは
秋萩の 咲きて散りぬる 花にあらましを〔吾妹兒尓戀乍不有者秋芽之咲而散去流花尓有猿尾〕(万120)
「吾妹子に恋ひつつあらず」ハ「(花にあらませば)秋萩の咲きて散りぬる花にあらまし」ヲ
彼女に対して恋しつづけないということは、どういうことかというと、もし仮に自分が花であるとしたら、秋のハギが咲いて、散ってしまった、その花であったらよいのになあ、というのと同じことだ、と言っている。
散ってしまった花は見る影もないものである。どうしてよりによって「秋萩」を採用しているのか。それは、アキハギだからである。アキハギ(キは甲類、ギは乙類)とは、ハ(葉)とキ(木、キは乙類)(ハギで濁音化)がアキ(飽、キは甲類)てしまった様子を示しているように聞こえる。つまり、あの小さな花弁は、ハ(葉)ギ(木)に飽きられて捨てられた残骸なのである。花のなかでも恋を表す点では最低、最悪の花、それが「秋萩の咲きて散りぬる花」である。そんな最低、最悪の花になりたいわけはなく(反実仮想)、彼女に恋しつづけると宣言している。

アキハギ
この歌で「つつ」の二つ性が後半部で指しているのは、「咲きて」と「散りぬる」でもあり、「は(葉)」と「ぎ(木)」でもあり、「はぎ(萩)」=「は(葉)」+「ぎ(木)」と「花」とでもある。こういう言葉遊びの才覚を隠しながら、否定と否定とを両立させる高等テクニックの表現を展開している。
後れ
居て 恋ひつつあらずは
紀伊の国の
妹背の山に あらましものを〔後居而戀乍不有者木國乃妹背乃山尓有益物乎〕(万544)
「後れ居て恋ひつつあらず」ハ「(山にあらませば)紀伊の国の妹背の山にあらまし」モノヲ
置いてけぼりを食わされて後に残り恋しつづけないということは、もし私が山であったとしたら、紀伊の国のイモセの山、それはイモ(妹)とセ(背)とが吉野川を挟んであって一つにはなれない山であるが、そうだといいのになあというのと同じことだ、と言っている。山は動かないから合体することはない。間に川が流れているから大地震があっても一つにはならないだろう。そうだといいなあというのは、取り残されて相手のことを忘れて恋しなくなるというほどのことである。
これは恋の歌である。今言ったようなことは、とてもじゃないが容認することはできない。言いたいことはその真逆で、旅に行くなら一緒に出掛けて恋をしつづけて、恋が爆発して一つの山になることがあるのを望んでいる。
「つつ」という言い方の二つながら性は、ハの後でも、山が二つながらになっている。「妹」の山と「背」の山である。
外に
居て 恋ひつつあらずは 君が
家の 池に住むといふ 鴨にあらましを〔外居而戀乍不有者君之家乃池尓住云鴨二有益雄〕(万726)
「外に居て恋ひつつあらず」ハ「(鴨にあらせば)君が家の池に住むといふ鴨にあらまし」ヲ
離れていてあなたのことを恋しつづけないということは、もし仮に人間である私が鴨であるとしたら、あなたの家の池に住んでいるという鴨でありたいというのと同じことだなあ、と言っている。庭の池に鴨をペットとして飼っていたことがなかったとは断言できないが、アヒルやガチョウではないから、怪我でもしたのか飛び立てなくなった鴨が、渡りの季節を過ぎてもいつづけているということであろう。当然、一羽でいる。そんな取り残されて動けない鴨になりたいわけではない。つまりは、遠距離になったからといっても恋しつづけたいのである。
「つつ」という言い方で表す二つ性は、後半部で「池(ケは乙類)」と「
行け(ケは乙類)」
(注4)とに示されている。「行け(ケは乙類)」は「行く」の已然形で、すでに行ってしまったこと、渡り鳥の群れが渡ってしまっていることを指している。だから「に住むといふ」などと変にもったいぶった言い方をしているのである。そして、「住む」ところは「家」のはずだから、「家」と「池」とが二つながら存在していることにも対応していると言える。
後れ
居て 恋ひつつあらずは
田子の浦の 海人にあらましを
玉藻刈る刈る〔後居而戀乍不有者田籠之浦乃海部有申尾珠藻苅々〕(万3205)
「後れ居て恋ひつつあらず」ハ「(海人にあらませば)田子の浦の玉藻刈る刈る海人にあらまし」ヲ
置いてけぼりを食わされて行ってしまったあなたのことを恋しつづけないということは、もし仮に私が海人であるとしたら、田子の浦で玉藻を刈って刈ってをくり返す海人でありたいというのと同じことだなあ、と言っている。あなたと一緒に連れ立って出掛けたいのであって、田子の浦で玉藻刈りに専念しなければならない海人にはなりたくなどないのである。
最後のとってつけたような「珠藻刈る刈る」は、前半にある「つつ」と対応させるために「刈る」と「刈る」を示すためにつけられていると思われ、際立たせるための倒置表現となっている。田子の浦の海人が玉藻を刈っては刈ってをくり返すという地口はわかりやすいものである。そこがタゴ(原文に「田籠」)だから、タコ(蛸)のようにたくさん手(足?)を持っていて、藻刈鎌を同時に複数使うことができるからである。この玉藻についてはよく知られた歌がある。
麻続王の伊勢国の
伊良虞の島に流さえし時に、人の、
哀傷しびて作る歌
打つ
麻を 麻続王 海人なれや 伊良虞の島の
玉藻刈りをす(万23)
麻続王、これを聞きて
感傷しびて和ふる歌
うつせみの 命を惜しみ 波に濡れ 伊良虞の島の 玉藻刈りをす(万24)
右は日本紀を
案ふるに曰はく、「天皇四年乙亥の夏四月戊戌の朔乙卯に、三位麻続王、罪有りて因幡に流し、一子は伊豆の島に流し、一子は血鹿の島に流す」といふなり。是に伊勢国伊良虞の島に
配すと云ふは、
若疑し後の人の歌の
辞に縁りて誤り記せるか。
この歌では、天皇の被る天子だけに許された冠、玉藻を、我が子の遊びのためにちょっと拝借したため天武天皇の逆鱗に触れ、流罪になったことについて歌にしている
(注5)。すなわち、玉藻を借ることを海藻である玉藻を刈ることに準えて歌っている。その歌の意を加味すれば、後に残されて恋をしつづけないということは、もし海人となるとしたら、もちろん海人になるなどということはないが、好ましからざる海人になって蛸のように手がたくさんあって玉藻をどんどん借りてしまい流罪の憂き目に遭うのが必定な田子の浦の海人になりたいというのと同じぐらい駄目なことであると言っているとわかる。言いたいことはその真逆で、私のことを置いていかないで恋しつづけさせてくれて、仮に海人となるにしてもほとんど玉藻をカル(借・刈)ことのない海人、魚や貝を獲るのが専門の海人になることが望ましいですよねえ、と言っている。
よく知られた麻続王の玉藻の歌を踏まえているとすれば、その左注に見えるように、天皇の玉藻を拝借したがために連座させられることを示唆していることになる。私のことを放って遠くに行くと、私は玉藻を借りる海人になって、あなたも連座させられて罪になりますよ、と恋の脅迫を仕掛けているのである。
かくばかり 恋ひつつあらずは
石木にも ならましものを 物思はずして〔如是許戀乍不有者石木二毛成益物乎物不思四手〕(万722)
「かくばかり恋ひつつあらず」ハ「物思はずして(石木にもならせば)石木にもならまし」モノヲ
これほどに恋しつつあることがないのは、もし仮に私がもの思いをしないで岩石や樹木になるのだったら、岩石や樹木になるであろうことよ、という意である。当然、人間らしい感情を持たない木石ではないのだから、このように恋し続けているのである。
「つつ」という言い方で表す二つ性は、後半部では「石」と「木」に反映されている。
表面上はこのように解されるが、これまでの例と比べると、修辞として物足りない感がぬぐえない。もう少し突っ込んだもの言いをしているのではないか。
初句で「かくばかり」と言っている。それがどれほどのものなのか、歌の内部には説明されていないように見える。しかし、それでは何を言っているのかわからない歌ということになる。
なぜ「
石木(キは乙類)」と言っているのか。これは同音の「
岩城(キは乙類)」のことなのではないか。岩城とは、岩で造られた墓の石室のことである。死者を埋葬する空間として確保されている。古墳の横穴式石室では、追葬されることがあらかじめ準備されていた。すなわち、寿陵のように死んだ後のことまで考えられている
(注6)。念の入った準備である。物思いにふけることなく、行く末のことに悩み煩うことも一切ない。老い先の心配はいらないよ、死んだ後までも、というきつい冗談を言っている。木石が「物思はず」であるばかりか、死んだら入るべき「岩城」がすでに決まっているというのは「物思はず」にいられることである。これほどまで恋しつつあることがないのは、他人のものになることはなくて必ず自分のものになるからあれこれ気にかけることがないお墓を持っているように、何かと思案することがないのと同じことだ、ということである。「つつ」は後半部で、「石木」と「岩城」の二つに表れている。本心は、恋の煩いに遭いながらこんなにも恋し続けるのが良いことで、寿陵をこしらえて死んだ後の安心感を得ようとするなんて棺桶に片足を入れた人の考えること、ご免だね、そんな全然楽しくないことは、と言っている。
家にして 恋ひつつあらずは
汝が
佩ける
大刀になりても
斎ひてしかも〔伊閇尓之弖古非都々安良受波奈我波氣流多知尓奈里弖母伊波非弖之加母〕(万4347)
「家にして恋ひつつあらず」ハ「汝が佩ける大刀になりても斎ひてしか」モ
「てしか」は、テは完了の助動詞ツの連用形、シカは回想の助動詞キの已然形である。もう済んだ話で不可能だが、もしそれが可能なら~したいものだ、という意味である。これは、反実仮想の一様式といってよいだろう。「ませば……まし」と似た表現である。
「斎ふ」という言葉は、将来の吉事、幸福、安全が得られるように、善い行いを重ね、悪い行いを慎しむことが原義である。吉言を述べ、まじないをすることも広くイハフと言っている。ここでは、安全が護られることを期待するために、守り刀になろうものをという呪言的な意味合いを含めて言っている
(注7)。
家にあって恋しく思い、また恋しく思うをくり返すことがないというのはどういうことかというと、実際にはできっこしないことであるのだが、お前(自分の子)が腰に着けている大刀に私がなってでも安全が護られるようにしたいものよ、というのと同じことでもある、の意味である。「つつ」の表す二つ性は、「
大刀」は諸刃の剣で、どちら側にも刃があることを表している。そしてまた、守り刀となって安全を護るという言い方に、親が子を護るという意味と、防人が国を護るという二つの意味を兼ねるからである。
つまり、お前が腰につける大刀になってでも護ることができるようにというほどに、善い行いをし、悪い行いを慎んで家にずっといて、お前のことを恋しく思い続けているよ、と言っている。家にい続けていれば、インターネットにつながってもいないのだから、悪いことをしようにもできないのである。初句の「家にして」の意味はここにおいてのみ明らかとなる
(注8)。
吾妹子に 恋ひつつあらずは
苅薦の 思ひ乱れて 死ぬべきものを〔吾妹子尓戀乍不有者苅薦之思乱而可死鬼乎〕(万2765)
「吾妹子に恋ひつつあらず」ハ「苅薦の思ひ乱れて死ぬべき」モノヲ
この歌は、下を「まし」で承けていない。上に多く見た例に寄せれば、次のようになるだろう。
吾妹子に 恋ひつつあらずは 苅薦の 思ひ乱れて 死なましものを(万2765改)
「吾妹子に恋ひつつあらず」ハ「(死なませば)苅薦の思ひ乱れて死なまし」モノヲ
彼女に対して恋しつづけないということは、どういうことかというと、もし仮に死ぬのだったら、(苅薦の)思いが乱れて死んでしまいたい、というのと同じことだなあ、ということである。万2765番歌はその同類表現で縮約されたものと考えられよう。
彼女に対して恋しつづけないということは、どういうことかというと、もし仮に死ぬのだったら、(苅薦の)思いが乱れて死んでしまうべきなのだ、というのと同じことだなあ、ということである。死に方として、同じ死ぬにしても、思いが乱れて死んでしまうのではなくて、一途に思い続けて死んでしまうことのほうが、彼女に恋する身として誠実というものである。それなのに、ノイローゼを患って自死を選ぶ場合、思いが乱れて死ぬという言い方をする。そういう言い方をする以上、そんな死に方は死に方としてふさわしくないのである。だから、思いが乱れて死ぬようなことなく、一途に彼女のことを恋いつづけている、というのが本音であり、歌の本意である。
この歌における「つつ」の二つ性はどこにあるのだろうか。枕詞「
苅薦の(刈薦の)」は、薦筵に編んだものの長さを部屋の大きさに合わせるために端を刈ることをしたら、せっかくの綴じ目がなくなるから緯糸にも経糸にもしている
菰が区別なくバラバラになることを指して作られた言葉ではないかと考えられる
(注9)。「つつ」の二つ性は、経糸と緯糸の二つがあるところを指しているということだろう。
「恋ひつつあらずは」が倒置されている例も多い。
白波の
来寄する島の
荒磯にも あらましものを 恋ひつつあらずは〔白浪之来縁嶋乃荒礒尓毛有申物尾戀乍不有者〕(万2733)
「恋ひつつあらず」ハ「(あらませば)白波の来寄する島の荒磯にもあらまし」モノヲ
恋いつつあることがないというのは、どういうことかというと、もし仮にあるとしたら、白波が来て寄せる島にある荒磯でもありたいものだなあ、ということに相当する、と言っている。激しい波がしきりに打ち寄せる荒磯などにはなりたくはない。アップアップしたくはないからである。ずっと息継ぎのことしか考えていなければならないなんて、それは泳いでいるのではなく溺れているのである。金がなくて賃労働を得ようと翻弄されるだけ、あるいは、権力闘争に明け暮れて落ちつく暇もないといった状況に陥り、浮いた話の一つもない人生などまっぴらご免である。荒れた海のなかで露頭を顕わにしている岩などになるのではなく、恋をしつづけたい、というのが本心である。
波が「白波」と呼べるほどのものである限り、何度も何度も来ては寄せ、来ては寄せをくり返すものである。「つつ」の二つ性はそこに表れている。「
荒磯」に「
有り」、「
荒磯」に「
有らまし」といった韻も関係するかもしれない。
秋萩の
上に置きたる 白露の
消かも死なまし 恋ひつつあらずは〔秋芽子之上尓置有白露乃消可毛思奈萬思戀管不有者/秋芽子之上尓置有白露之消鴨死猿戀乍不有者〕(万1608・2254)
「恋ひつつあらず」ハ「(死なませば)秋萩の上に置きたる白露の消かも死なまし」
恋いつつあることがないというのは、どういうことかというと、もし仮に死ぬとして、秋のハギの上に置いた白い露が消えるように死んでしまいたい、というのと同じことである、と言っている。
ハギの花は露が置いたように点々と咲くものであり、露があったことは紛れていてわからないまま消えていくことになる。シラツユであり、露知らずの意を含んでいる
(注10)。すなわち、この歌は、恋しつづけないということは、アキハギの上に置いた白露が、存在すらおよそ意に介されないままに消えてなくなるように、無碍なことに死んでしまいたいというのと同じことに当たると言っている。これは恋の歌である。恋する相手から、いるかいないか気に留められないのではかなわない。たとえ嫌われようとも、それは異性として認められているということで、まだ救いがあるというものである。そして、これからも恋しつづけていたいと歌い、できることなら相手に振り向いてもらいたいと願っている。奥ゆかしく、情熱的な歌である。
この歌での「つつ」の二つ性は、後半部では、白露が置くのは霧の「
気(ケは乙類)」によるが、それが「
消(ケは乙類)」となることを言っている。
秋の穂を しのに押し
靡べ 置く露の
消かも死なまし 恋ひつつあらずは〔秋穂乎之努尓押靡置露消鴨死益戀乍不有者〕(万2256)
「恋ひつつあらず」ハ「(死なませば)秋の穂をしのに押し靡べ置く露の消かも死なまし」
恋いつつあることがないというのは、どういうことかというと、もし仮に死ぬとして、秋の穂がしっとりと濡れておし靡かせるほどに露がかかっている、その置いている露が消えるように死んでしまいたい、というのと同じことである、と言っている。
実際の思いはその真逆である。死んでしまいたくなどなくて、それも最悪の死に方、絶対に簡単には消えないはずの大量の露が忽然と消えるような死に方はしたくない。秋の穂をぐっしょり濡らし、秋の穂を押し靡かせ垂れさせている露は、そう簡単には消えるはずもなくて長くありつづける、そのように恋いつづけたいと告白している。もしも露が簡単に消えるとなると、押し靡かせて頭を垂れている稲穂も元通りになり、稔っているはずが稲粒は空っぽだったということになり、凶作であるほどに不吉である。
「つつ」の二つ性は、上の万1608・2254番歌にあるのと同じく、「
気(ケは乙類)」と「
消(ケは乙類)」によるものと思われる。また、「しのに押し靡べ」にもあるのだろう。シノという音(言葉)は、「篠」字で常用される小さな竹、つまり、ササ(笹)のことをいう。「篠は小竹なり。此には
斯奴と云ふ。」(神代紀第八段一書第一)、「小竹を訓みて
佐佐と云ふ。」(記上)とある。サとサの二つ性を隠していることになる。言語遊戯の歌である。
秋萩の 枝もとををに 置く露の
消かも死なまし 恋ひつつあらずは〔秋芽子之枝毛十尾尓置霧之消毳死猿戀乍不有者〕(万2258)
「恋ひつつあらず」ハ「(死なませば)秋萩の枝もとををに置く露の消かも死なまし」
「置く露の 消かも死なまし」の三例目である。
恋いつつあることがないというのは、どういうことかというと、もし仮に死ぬとして、秋萩の枝もたわむほどに置いている露が忽然と消えてなくなるように死んでしまいたい、というのと同じことである、と言っている。
実際の思いはその真逆である。死んでしまいたくなどなくて、それも最悪の死に方、秋萩の枝がたわむぐらいまでついている大量の露が消えてなくなるような死に方はしたくない。秋萩の枝をぐっしょり濡らしている露は、容易に消えるはずもなく長くありつづける、そのように恋いつづけたいと告白している。露が簡単に消えるとなると、枝のたわみは大したことはなくて元どおりになるということである。それは本当のところ秋萩と呼ぶことはできないのかもしれない。枝が十分にたわむほどになると、萩の枝は充実したことの証となる。そんな萩の枝は、刈り取って簾に編まれた。これは恋の歌である。
御簾を作って部屋に掛け、中を隠して情事に至る。だが、萩の枝が充実していないと簾は完成しない。二人の関係がそこまで進んでいないということや、まだ若くて未熟だから不適当であるということを意味する。
「つつ」の二つ性は、同様に「
気(ケは乙類)」と「
消(ケは乙類)」によるものと思われる。また、「とををに」という言葉にもあるのだろう。トヲヲはタワワの母音交替形であるが、トヲトヲを約したものと受けとれるから、トヲとトヲの二つ性を含んでいる。
「恋ひつつあらずは」を助動詞「む」ばかりで承ける例もある。
後れ居て 恋ひつつあらずは 追ひ
及かむ 道の
隈廻に
標結へ吾が背〔遺居而戀管不有者追及武道之阿廻尓標結吾勢〕(万115)
「後れ居て恋ひつつあらず」ハ「道の隈廻に標結へ吾が背、追ひ及か」ム
置いてけぼりを食わされて行ってしまったあなたのことを恋しつづけないということはどういうことかというと、道の曲がり角には目印をつけていってください、追いかけていって追いついてしまうつもりですよということです、と言っている。本心は真逆で、置いてけぼりを食わされてもここでずっとあなたに恋しつづける。道の曲がり角ごとに目印をつけて目立つようなことはしないでほしい、追いかけていって追いつこうとしたくならないように、と言っている。
題詞に「勅
二穂積皇子
一遣
二近江志賀山寺
一時、但馬皇女御作歌一首」とある。歌の作者は但馬皇女で、相手は穂積皇子である。但馬皇女は高市皇子の宮に在って人妻なのである
(注11)。恋しつづけないということは、後先考えずに行動するのと同じことなのだ、と言っていて、この歌で伝えたいのは、置いてけぼりを食わされても一人恋しつづけているのが好ましく、人目に立つような下手な行動は互いに慎もうということである。
このような場合でも、ハの上にある「つつ」の二つ性は後に反映されている。「道の隈廻」はくねくね曲がる道の曲がりごとにということであり、左カーブ、右カーブが交互に現れるし、「追ひ及かむ」というのも「追ふ」ことが「及く」、つまり、「追ひ追ひ」することを指している。
剣大刀 諸刃の
上に 行き触れて 死にかも死なむ 恋ひつつあらずは〔剱刀諸刃之於荷去觸而所𭣰鴨将死戀管不有者〕(万2636)
「恋ひつつあらず」ハ「剣大刀諸刃の上に行き触れて死にかも死な」ム
恋いつづけていないとは、どういうことかというと、(剣大刀)諸刃の上を行くように触れて、いずれにせよ死んでしまうように死んでしまいたい、というのと同じことだ、と言っている。これは恋の歌である。本心では、死んでしまいたいのではなく、恋しつづけたいのである。「剣大刀諸刃の上に行き触れて」という比喩は、情勢がどちらに転んでも死罪になるような緊張状態を言っている。うまく立ち回ることで生き続けてきたのであるが、それがバレてどのみち死ななければならなくなっている状況に陥ってしまった。やはり忠誠を誓うなら一人の主君に仕えるのでなければならず、二君に仕えようとしたことが誤りであった。恋も同じで、一人の人を恋しつづけるのでなくてはうまくいかない。今、自分は、あなたのことしか考えていないのであって、これからもあなたのことしか考えないで恋しつづけたい、と言っている。
ハの前の「つつ」の二つ性は、ハの後のどちら側にも刃がある諸刃のさまと、「死にかも死ぬ」という言い方に表れている。助詞のハとハ(刃)とを絡めあげて使っているようである。
住吉の
津守網引の
浮子の
緒の 浮かれか
行かむ 恋ひつつあらずは〔住吉乃津守網引之浮笶緒乃得干蚊将去戀管不有者〕(万2646)
「恋ひつつあらず」ハ「住吉の津守網引の浮子の緒の浮かれか行か」ム
恋いつづけていないとは、どういうことかというと、住吉の津守が網を引くときの浮子がついているロープのように浮かんで行ってしまいたい、ということと同じことだ、と言っている。
「住吉の津守」は港の安全管理に当たる人で、船の出入りを円滑にする仕事をしている。網が設置されていたら船の行く手を阻み、接岸する邪魔になる。だから本来すべきことではないが、内職として「網引」をしているように描かれている。船が見えたらロープは切って流れるままにしていたという設定なのであろう。これは恋の歌である。相手に訴えたいことは正反対で、恋いつづけて、放たれたロープについた浮子がプカプカ浮かぶようなことにならず、あなたのもとに引き寄せられたいと言っている。
ハの前の「つつ」の二つ性は、ハの後の「浮子」に表れている。網にはいくつもの「浮子」が付けられていた。「浮子」と「浮かれ」という言葉の表出にも表れている。
いつまでに
生かむ命そ おほかたは 恋ひつつあらずは 死なむまされり〔何時左右二将生命曽凡者戀乍不有者死上有〕(万2913)
この歌は訓みが確定していない。結句の原文「死上有」はシヌルマサレリ(元暦校本など)、シヌゾマサレル(荷田春満・萬葉集童蒙抄)、シナムマサレリ(鹿持雅澄・萬葉集古義)、シナマシモノヲなどと訓まれている
(注12)。
字面だけからわかることとして、恋しつづけないでいるということは、死ぬこと以上のことである、の意であろうと推測される。シヌルウヘニアリ、シヌルウヘナリと訓むことはできるが、ウヘを比較の上位を表す語として使う例は上代に見られない。そこで、上等の意からマサルという語を当てようとされてきた。「上」字はアガルとも訓み、「神あがり〔神上〕」(万167)の例に従えば、カムアガリアリのように死ぬことと関連させて訓むことも可能ではある。ただし、貴人について使う言葉であり、三句目にある「凡者」と釣り合わない。その「凡者」は不注意なことに、オホカタハ、オホヨソハ、オホロカニなどと訓まれている。万2532番歌に「凡者」をオホナラバと訓む例があるから従えばよいのだが、歌意を曲解した先入観からここには当たらないと却下されている
(注13)。
上の句で命が限られていることが詠まれている。限られた命をどのように使うかは、時のイデオロギーやプロパガンダに左右されることはあっても、基本的にはその人その人の判断で決められることである。人生を神仏に捧げるというのではない人であるなら、という意味で使っている。通り一遍、いい加減、平凡のことをいうオホ(凡)の意をそのまま表している。神に仕えるために斎宮へ行くような特別な場合を除き、ふつうの人、凡人であるならば、恋をしつづけないということは、死んでしまう以上につまらないことである、と読みとれる
(注14)。五句目の「死上有」は、斎宮忌詞を用いた言い回しではないか。「死を
奈保留と
称ふ。」(倭姫命世記)、「死を
奈保留と云ふ。」(延喜式・斎宮寮式)と見える。
いつまでに
生かむ命そ おほならば 恋ひつつあらずは
直ることあり(万2913)
「いつまでに生かむ命そおほならば恋ひつつあらず」ハ「直ること」アリ
いつまで生きられる命かわからない、命を神に捧げたわけではないごくふつうの人であるなら、恋をしつづけないということは、どういうことかというと、忌詞で死んでしまうことを表すナホル、というのと同じことである。ふつうの意味のナホル(直・治)は、険悪、異常な状態からもとの平静、平常な状態にもどることである。天気、機嫌、病気、拘禁状態などから回復することをいう。そのままの意味で解すれば、恋煩いをせずにいるということは、平静であるということである。それはそのとおりなのであるが、それははたして人の人生というに値することなのであろうか、というのが歌の作者、抒情というものを少なからず良いものと思っている人にとっての感慨である。神と結婚してしまう斎宮様じゃないのだから、恋に狂うことなく生き続けるなんてもったいないよ、と言いたいのである。そこで、忌詞を使って歌にし、その点を強調するために「死上」という義訓書きにしている。シヌの上等表現がナホルである
(注15)。
そして、「つつ」の二つ性は、この「直る」という言葉の二重性、heal と die に表れている。
以上、万葉集の「恋ひつつあらずは」の用例を見てきた
(注16)。すべての例で確認されたように、「ズハ」という連語を考えて無用な混乱に陥る必要はなく、係助詞の「ハ」が前と後とを等価であると示すことで理解されるものであった。PハQとあれば、P=Q(P≒Q)のことと考えればよいのである。「ハ」は前後を機械的に結合するのが役割である。前件に「……アラズ」と否定形が置かれているのは、そこで条件節になる(P→Qなどで示される)のではなく、否定している事柄ないし否定したい事柄どうしを結合させて、実際にはその真逆のことを主張しようとしている。「ハ」を現代語に訳すとき、ンヨリハやズシテハ、デナクテ、セズニ、ナイデなどではなく、Pナンテ(マルデ)Qダ、に近いものがあるだろう。「クリープを入れないコーヒーは、日焼けした写真プリントのようだ。」といった言い方が例となる
(注17)。この例は商業広告である。クリープを入れないことを広告主は推奨するのではなくて入れてくれることを求めていて、写真プリントも日焼けして色がわからなくなるようでは困るから耐久性のある顔料が望まれるのである。
否定的な言辞どうしを「ハ」で結ぶ言い方によって、その表現とは真逆のことを言い表そうとする手法は、上代人にとってさほど難しいものではなかったと思われる。昨今、皮肉が通じなくなったと言われることが多い。皮肉を言っていることを理解しあえるリテラシーが失われた、ないしは、共有されなくなったからであると説かれている。その場合、まったく同じ言い方で褒めているのか貶しているのか状況から読み取らなくてはならない。広義の反語についても同様なことと言われている。ところが、上代では、同じ言い方ではなく、已然形+「ヤ」が反語を表すように、はっきりした文型をもって反語表現が行われている。否定的な言辞どうしを「ハ」で連接させるのも、一つの文型として確立しているものだから、疑問の余地は生じない。
短詩文形式の歌が隆盛を誇っていたのが上代の文体の特徴的なところである。短い言葉だけで言いたいことを全部言うにはどうしたらよいかということを一生懸命に考え、端的な表現が指向されていたと言えるだろう。反語表現を現代語に訳す際、~であろうか、いやいや~であろうことはない、などと二重に訳している。つまりは言葉が二倍に膨らんでいる。三十一文字(音)のうちに短縮化したいのだから、半分で済む言い方は重宝されることになる。否定的な言辞動詞を「ハ」で結ぶ言い方も、~でないのは、~というのと同じことだ、つまりは、~であって、~にならないようにしたいものだ、と、否定を裏返して訳して結果的に四倍に膨らんでいる。四倍の量のことを一気に言えるのだから、この言い方は修辞的表現として当時の言葉の使い手たちにたしなまれたのである。なぜそれほど短く言おうとする圧力がかかっていたのか。それは、文字を持たなかったからであろう。記憶にとどめられるように短くしていきたかった。その傾向の最たる言葉は枕詞である。意味が多層に重なり合って訳そうにも訳せない代物と化している。なぜ枕詞というものが生まれたのか。すでに述べたことと同じであろう。
(注)
(注1)浜田1986.は、「恋ひつつあらずは」は、「恐らく話者の意識の中に「こんなにいつまでも徒に恋しく思っていたく
ない」という気持がある為に、それが打消の「ず」となって、現るべからざる「かくばかり恋ひつつ
あらば」という条件句の中に現れる結果となったものではないかと思う。」(243頁)とする。
(注2)小柳2004.ほか参照。個別具体的に用例を検証し、可能的未実現、既実現、不可能的未実現、可能的仮定条件句、不可能的仮定条件句、などと分類している。一つの言葉、「ズハ」にまとめられるはずはなかろうことを無理にまとめようとしている。解釈は袋小路に入っており、不毛な議論が絶えない。
本稿では「恋ひつつあらずは」の例をとりあげている。これまでの「ズハ」の分類では既定の事態を受けるものの一方に偏っている。もう一方の未定の事態を受けるものとする分類の例を二、三採りあげ、検証しておく。
立ちしなふ 君が姿を 忘れずは 世の限りにや 恋ひ渡りなむ〔多知之奈布伎美我須我多乎和須礼受波与能可藝里尓夜故非和多里奈無〕(万4441)
「立ちしなふ君が姿を忘れず」ハ「世の限りにや恋ひ渡りな」ム
しなやかに立つあなたの姿を忘れないということは、どういうことかというと、生きている限りであろうか、いやいやそうではなく死んだ先できっと恋い続けるであろう、ということである。あなたの雄姿を忘れないというのは、向こうの世界でも恋い続けていることだ、と言っている。この場合、空想を空想が「ハ」で承けているとすれば、空想だとわかっているからわざわざすべてを反転させて解さずとも済むとも考えられる。しかし、それでは何を訴えるために歌っているのかわからないことになる。多田氏による現状の解釈、「しなやかに立つあなたの姿を忘れずに、生きている限り恋い続けることだろうか。」という訳では、この歌がモノローグとなってしまう。声に出して歌を歌うとは、相手に直接、あるいは、間接的に
伝としてであれ、まずは何かを相手に訴えるために発していると考えるべきである。
この歌は恋の歌である。言いたいことは、現実的に、生きている今、しなやかに立つあなたの姿を目にしたい、この世の限りとして燃える恋がしたいということである。あの世で恋をしているなんて、今恋をしていないの裏返しである。そんなことはまっぴらである。本心は真逆で、このまま放って置かれたらあなたの素敵なお姿を忘れるでしょう、あたり前の話ですがあの世で恋しても仕方がないでしょう、今、私のことを気にかけてくださいね、と言っている。
吾が袖は
手本通りて 濡れぬとも
恋忘れ貝 取らずは
行かじ〔和我袖波多毛登等保里弖奴礼奴等母故非和須礼我比等良受波由可自〕(万3711)
「吾が袖は手本通りて濡れぬとも恋忘れ貝取らず」ハ「行か」ジ
この歌は遣新羅使歌群中の歌である。対馬まで来たところで詠んだ歌である。私の袖は袂からどんどん濡れてしまっていても恋忘れ貝と呼ばれる貝を取ることはない、とはどういうことかというと、ここからどこかへ行くつもりはないということである、と言っている。袖が濡れたのは自分の涙によってである。恋をしているのに現状では職務がら郷里に帰ることなどかなわない。すでに袖は濡れているのだから、水の中の恋忘れ貝を手に取るとしても大して変わりはないが、そうはしない。それはここを去って行くつもりはないということだ、と言っている。逆に言うと、恋忘れ貝を取ってはじめて新羅へ行くことができるようになる、というのである。それは、あなたへの恋心を忘れてしまわない限り、異国へ行くなんてできることではない、ということであり、当たり前の話だがお上の命令で新羅へ遣わされていて、仕事なのだから行かないわけにはいかないのであるが、後ろ髪を引かれる思いとして唯一あるのはあなたへの恋心なのだ、と言っている。
この解釈は、竜頭蛇尾の文型によく適合している。五句目の途中までを「行かじ」だけで承けている。「行く」は新羅へ行くことである。何かかんかいろいろ条件をクリアしてようやく行くことができるというのが頭でっかちの文にしている。むろん、宮仕えの身で行かないという選択肢はない。なのにそのことを天秤にかけ、恋心が激しくてどうにもならないと大げさに訴えている。誇張表現のために「恋忘れ貝」という言葉を用いている。
現状の解釈(多田氏)では、「私の袖が袖口あたりからすっかり濡れ通ってしまおうとも、恋を忘れさせるという貝を拾わずには帰るまい。」とあり、望郷の念、故郷にいる妻への情を振り払おうとする思いを歌っていることとしている。しかし、この解釈では単なるモノローグとなっており、しかも「行く」を新羅へ向かうことではなく妻のもとへ帰ることと捉えている。そもそも恋を忘れさせる貝を拾って恋人のところへ帰るというのでは理屈が通らない。
吾妹子が
屋戸の橘 いと近く 植ゑてし
故に 成らずは
止まじ〔吾妹兒之屋前之橘甚近殖而師故二不成者不止〕(万411)
現状の解釈(多田氏)では、「あなたの家の庭の橘を私の家のすぐ近くに植えたのだから、実らせずにはおかないつもりだ。」とする。実が成るのと恋愛が成就するのとを掛けて歌われている。それはそのとおりであろうが、「いと近く」がどこに近いのかが問題とされている。通説では自分の家の近くのこととされている。
「吾妹子が屋戸の橘いと近く植ゑてし故に成らず」ハ「止ま」ジ
あなたの家の庭の橘をすぐ近くにごく最近植えたせいで実が成らないとは、終わりにならないということと同じである、と言っている。「近し」という形容詞は、場所だけでなく時間についてもいう。つまり、ここでは、とても最近、植えたということも含み示している。
橘の実のことは、「ときじくのかくの
木実」(垂仁記)、「
非時香菓」(垂仁紀九十年二月)とも呼ばれている。タヂマモリが
常世国から将来したとされている。「時じく」は時間に関係なく、の意で、いつでも香りが豊かであることを表している。橘の実が成るということを恋愛成就と掛けているのだから、時間とは無関係の実が成るのなら永久に変わらない愛を手に入れることができたということになる。だが、つい最近植えたということは、時間とは関係がないとはまだまだ言えそうにない。実が成らないうちは、育成の作業は終りにならない。反対に、実が成ったら終わるというのは、実が成ったらそれは「非時香菓」だから、時間とは関係がないレベルに超越できたことを意味する。つまり、永久不変の愛を手に入れることができたことになる。目下のところ、その愛を育み中ということになろう。彼女の家の橘を場所的にも時間的にも「いと近く」植えた。「橘」を移植したとは彼女が自分の側に、ごく最近やってきたということで、相手に惚れ抜いて一緒になった新婚さんの歌である。「止む」とは、動きが自然におさまること、物事が途中で行われなくなること、事が決着することである。夫婦として落ち着きを見せるまでしばらくかかりそうだと客観的に自分を見ている。よって、「殖而師故二」は「植ゑてし
故に」ではなく、「植ゑてし
故に」と訓むのが正しい。この歌は、「大伴坂上郎女の橘の歌一首」(万410)に「和ふる歌」である。大伴坂上郎女が、娘のことを心配する歌を詠み、その歌に「和」している。若い娘は客観視できているから、この歌のやりとりをもって「止む」、つまり、母親の心配について決着がついている。
くり返しになるが、この場合、「ズハ」をもって「可能的未実現」を示すと考えるのは誤りである。「橘」が「非時香菓」であることを伝える歌とならず、時間軸を超える関係性を視野に入れていることを汲み取ることができなくなる。
(注3)高山の磐根を巻いて死ぬならば、これほどに恋い続けてあることはない、という因果関係に捉えることはできない。高山の磐根を巻いて死ぬなどと大仰なことをしなくても、感染症に罹ったり、栄養失調がもとで死んだり、足を踏み外して溜池に落ちて溺死することは日常的なことであった。死因とは関係なく、死んでしまえば恋い続けることも、息をし続けることも、毎朝納豆を食べ続けることもできない。「恋ひつつあり」を拒むために山の巌で首つり自殺するという歌をノイローゼの歌と解するのは誤解である。つないでいるのはハであって、バではない。
(注4)イク(行、往)はユク(行、往)に比べて新しく、俗な形かと思われており、万葉集歌では字余りの句に現れている。この駄洒落もかなり俗な部類のものである。
(注5)拙稿「玉藻の歌について―万23・24番歌―」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/a1e703d9391bbd05309a1dd9a00a945eなど参照。
(注6)薄葬化し、火葬されるようになっていた時、どのような寿陵が営まれていたのか詳細は不明である。
(注7)「
大刀」は「断つ」から派生した語と考えられ、守り刀となる短いもの、ただしカタナとはないから短刀ではなく短剣のことであろう。
(注8)家に放火するといったことは悪い行いだが、そうなると「家にして」でなくなるから除外される。
(注9)拙稿「枕詞「刈薦(かりこも)の」について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/b311622d92d50aed57fa9e715fc0ba89参照。コモが敷物とされるだけでなく、コモヅノとなって食用や真菰墨の採集にも用いられていることから、その二つの様態を表して「つつ」に対応しているとも考えられる。
(注10)上代に副詞のツユの確例は見られない。
(注11)万114番歌の題詞には、「但馬皇女在
二高市皇子宮
一時、思
二穂積皇子
一御作歌一首」、万116番歌の題詞には、「但馬皇女在
二高市皇子宮
一時竊接
二穂積皇子
一事既形而御作歌一首」とある。不倫関係にある女性が邸宅を抜け出して思い人のところへ追いかけて行くほど大胆なことをしたら、ちょっとたいへんなことになるだろう。
(注12)「ズハ」という語について本居宣長や橋本進吉に議論されて以来、先入観があるからこれらの訓み方が定着している。ラ変動詞のマサレリ(優・勝)は集中ではほかに、「益有」(万492・1206)、「益流」(万3016)、「麻佐礼留」(万803)、「益」(万3083)という用字が行われている。マサル(優・勝・増・益)でも、訓字を用いた場合には「益」「増」字が使われている。「上有」そのままで義訓されている例はない。
(注13)澤瀉1963.71頁。吉井2021.225頁。
(注14)推古紀三十二年四月条では、仏道に励む僧尼のことを「
道人」、一般人を「
俗人」と対置している。
(注15)ナホルという忌詞が上代に使われたとする確例はないものの、斎宮忌詞以外の忌詞は、例えば、「
失火」(天智紀六年三月)などとある。
三句目の「凡者」はオホナラバと訓むのが一番しっくりくる。平凡な人であるならば、の意として解することができるのだから、この訓み方は説得力を持つものと考える。
「……こと有り」という形は、「……」について別に説明することを予感させる言い方である。
古の人、云へること有り。「
娜毗騰耶皤麼珥。(汝人や母似?)」。
此の古語未だ詳らかならず。(雄略紀元年三月)
「云へること」が「有」るとまず呈示しておき、その「云へること」とは何か、次に述べている。万2913番歌の筆者の新訓と対照させると、「恋ひつつあらずは、直ること有り。」というのは、もともとは倒置形であってもおかしくなかったことを感じさせてくれる。助詞「ハ」の力量である。忌詞の「直る」を言って落ちとしているから歌のような語順になっている。「直る」に当たるところが落ちでも何でもなければ、倒置して「恋つつあらずは」を文末に持ってきていたであろう。倒置形になっていないという点から考えても、「死上」は「直る(こと)」と訓むのが正解に近いと理解できる。
(注16)「恋ひつつあらずは」から少し形の崩れた類例がある。
長き夜を 君に恋ひつつ
生けらずは 咲きて散りにし 花にあらましを〔長夜乎於君戀乍不生者開而落西花有益乎〕(万2282)
「長き夜を君に恋ひつつ生けらず」ハ「(花にあらませば)咲きて散りにし花にあらまし」ヲ
長い夜を君に恋いつづけて生きているのではないということは、どういうことかというと、もし花であるなら、もちろんそんなことはないのだが、仮にそうであったら、咲いて散ってしまって見る影もない花でありたいなあという、まことにみじめなことであるよ。
つまり、秋の夜長にあなたのことを恋いつづけて、もし花であるなら、すでに咲いて散ってしまった花などではなくて、盛んに咲いている花であるように、あなたの注目を浴びていたいことよ。
現状の解釈を多田氏に見れば、「この秋の長い夜を、あなたに恋い続けて生きているよりは、いっそ咲いて散ってしまった花であったらよかったものを。」となっている。恋心に悩み疲れるというのはわからなくはないが、だからといってそれで自暴自棄に陥っていると悪態をつかれたら、聞く相手は嫌になる。
後れ居て 長恋ひせずは
御園生の 梅の花にも ならましものを〔於久礼為天那我古飛世殊波弥曽能不乃于梅能波奈尓忘奈良麻之母能乎〕(万864)
「後れ居て長恋ひせず」ハ「(梅の花にならませば)御園生の梅の花にもならまし」モノヲ
置いてけぼりを食わされて宴に参加できずに、長く慕いつづけることがなく無関心になるのは、どういうことかというと、もし仮に自分が梅の花になるのであれば、もちろんそんなことはないし望んでもいないけれど、よりによって御屋敷の庭の梅の花になりたいものだなあ、というのと同じことである。
この歌は、令和の出典とされた大伴旅人の「梅花歌三十二首〈并序〉」に奉和した歌である。作者の吉田宜はその宴席に参加できなかった。後日旅人から宴のことについて手紙が来て、それにこたえる歌として作っている。その宴席で梅の花の散るのを雪の
零ることになぞらえて歌に作りなさいとお題が示されていた。それが「序」である。謎掛けを仕掛けた歌会であった
(補注1)。
実際にどうかは別問題として、そういう想定のもとであれば、宴から日を経て吉田宜が作歌している今、大伴旅人邸の梅花は散ってしまって見る影もないことであろう。風流ぶって楽しむことなどできない。旅人邸の「
御園生の梅の花」は梅の花として最悪の花である。そんなみじめな梅の花にはなりたくないのである。今、野山でちょぼちょぼ咲いている梅の花になるほうがまだ救われている。
万862番歌は、大伴旅人の「梅花歌」の歌会を見事に承けた歌として機能している。本心は、宴に参加したかったのに参加できずに残念でした。季節をわきまえずに散ってしまうお庭の梅の花になどならないで、咲いているのを愛でられて楽しめるものになりたいです、と言っている。花が咲いていれば人目に付く。そのことは、出席できずにお目にかかることがなかったことへの詫びにもなっている。
なお、現状の解釈では、「後に残されていて、いつまでも恋い慕っていないで、いっそ御庭の梅の花にもなりたいものを。」と捉えられている。題詞に「奉
二-和諸人梅花
一歌一首」とある。諸人が梅の花をモチーフにして歌った歌に対して、宴会が終わってから唱和している。リモート参加ではないから、今から大伴旅人の庭の梅の花になっても仕方あるまい。
相見ずは 恋ひざらましを
妹を見て もとなかくのみ 恋ひばいかにせむ〔不相見者不戀有益乎妹乎見而本名如此耳戀者奈何将為〕(万586)
「相見ず」ハ「(恋ひざらませば)恋ひざらまし」ヲ、「妹を見てもとなかくのみ恋ひばいかにせむ」
お逢いしないということは、どういうことかというと、もし仮に私が恋をしないというのであれば、あなたに対して恋をしないであろう、というのと同じことである。あなたを見てわけもなく起こる恋心をどうしたらよいのだろうか。
この歌は二句切れである。逢わないなどということは、ちょっと考えられないことで、もし私が仮に恋をしない人種に属しているとしたら、よりによって最悪なことにあなたに対して恋をしないというのと同じことである、と言っている。本心は真逆であり、私は恋をする人種であり、その相手はまぎれもなくあなたである。なにしろあなたに逢っている。ああ、あなたを見ると自動的に湧きおこる恋心をどう扱ったらよいのだろう。どうかよろしくお願いします、という意味である。
「ズハ」を連語とする説に依拠すれば、もし~ないなら、~なかったら、の仮定条件ということになり、一句目で仮定していたのをさらに五句目で再び仮定するのはおかしいことになるとして、「恋ふるはいかにせむ」
(補注2)と訓むと解されることがある。「ズハ」は連語ではなく、P≒Qという命題を提示し、句切れの後の三句目以降は、その命題下における具体的な状況への対処法について追及することで相手に訴えかけようとするものである。
なかなかに 君に恋ひずは
比良の浦の 海人にあらましを 玉藻刈りつつ〔中々二君二不戀者枚浦乃白水郎有申尾玉藻苅管〕(万2743)
「なかなかに君に恋ひず」ハ「(海人にあらませば)玉藻刈りつつ(ある)比良の浦の海人にあらまし」ヲ
中途半端にもあなたに恋しないとは、どういうことかというと、もし仮に私が海人であるのなら、よりによって比良の浦の海人でありたがるのと同じことであり、そうなるといつまでも玉藻を刈りつづけることに陥るものだ、と言っている。「ハ」の上に「なかなか」とあり、下に「つつ」とある。「恋ひつつあらずは」の例に見られたように呼応関係にあると考えられる。海人のなかで特定の地名を有する海人について言及している。ヒラの浦は琵琶湖に面したところとされているが、この歌で取りあげているのはその音の妙である。ヒラというのだから、ひらひらしていて原文に「枚」と書かれている形状について示している。ひらひらしているものはおおよそ平板なもので、形式的に表と裏があるかのように扱っているが、本質的には区別がなく、見えている面をオモ(テ)、見えていない面をウラと便宜的に呼んでいるにすぎない。となると、ヒラノウラというところは、裏を確かめようとひっくり返しても、またその反対面が気になってまた裏を確かめようとひっくり返す、の堂々巡りになる場所であることを示している。そんなことに明け暮れていたら、恋をすることなく人生は終わってしまう。
なぜそう言えるかといえば、ウラ(裏)という言葉は、裏、内側、中、心、思い、の意を範疇としているからである。中にあるであろう心を知ろうにも薄っぺらくて知ることができない。「ハ」の上には「なかなかに」とあり、ウラの意に注目させる仕掛けとなっている。常套表現に「うらも無く」と使われている。
うらも無く 我が行く道に 青柳の 張りて立てれば 物
思ひ
出つも(万3443)
何心なく歩いて行くと、の意である。ヒラノウラというところは、心に何も物を思わなくなるところ、つまり、恋とは無縁のところの謂いなのである。
海人の性質に堂々巡りをするところがあるのは、オホサザキノミコト(大雀命、大鷦鷯尊、仁徳天皇)とウヂノワキイラツコ(宇遅能和紀郎子、菟道稚郎子)とが互いに位を譲り合っていた時、その間を
大贄(苞苴)となる魚を奉るために持ってまわって腐らせて哭いたとする話が載っている(応神記、仁徳前紀)。それは、海人は魚や貝を獲るばかりではなく、藻を刈り採ることもあった点と関連する。モという言葉(音)は、助詞のモ、並列を表し、あれもこれもの意を表すことと対照される。助詞のモと名詞のモ(藻)との間に語根的、語源的なつながりがあるとは知られないが、同じ音、同じ言葉として使われていたら、同じ意味合いでその言葉を使ってみたい、聞く人の心に訴えるところがあるに違いない、と思う人があっても不思議ではない。
万2743番歌では、中途半端にではなくあなたに恋をすると宣言していて、藻を刈り続けることに一生を捧げて恋もせず、何が楽しかったのかと言われるような失策人生など歩みたくない、大好きなんだ、あなたのことが、と言っている。
現状の解釈では、「なまなかにあなたに恋したりせずに、いっそ比良の浦の海人ででもあったらよいものを。玉藻を刈りながら。」としている。海人は常民とは異なる存在で、卑賤視された、あるいは、落魄のイメージが強いなどという。根拠の不明な見解であり、三句目以降の語句を選択した必然性もないことになる。
なかなかに 君に恋ひずは
留牛馬の浦の 海人にあらましを 玉藻刈る刈る〔中々尓君尓不戀波留牛馬浦之海部尓有益男珠藻苅々〕(万2743或本)
「なかなかに君に恋ひず」ハ「(海人にあらませば)玉藻刈る刈る留牛馬の浦の海人にあらまし」ヲ
同じように、「ハ」の上の「なかなか」と下の「刈る刈る」は呼応関係にある。
この歌ではナハが持ち出されている。縄は綯うことでできあがる。藁縄であれば藁と藁とを縒り合わせて二本の藁が一本の縄と成っている。右縒りであれ左縒りであれ、目をつけた個所のウラ(裏)は何かと探るには、ひっくり返してためつすがめつ見てみたり、時によっては少しほどいてみることもあるかもしれないが、ほどいたらもはや縄ではないからわからなかったということになる。「うらも無く」「玉藻刈る刈る」人生を送ったりはしない。あなたのことで頭がいっぱいだ、と言っている。
(注17)往年のCMの例は、「クリープを入れないコーヒーなんて、ピンボケの写真のようだ。」といった譬えを使っていたと記憶する。ここでは日焼けの写真プリントに改編した。写真プリントがコーヒー色に焼けることを含ませたかったからである。「ハ」の前と後とが絡んでいなければ歌のレトリックとしておもしろみがない。あるいはこうも言えるだろう。「ハ」の前と後とでかけ離れたことを言っていて、それをつなぐ助詞「ハ」に負荷がかかっている。どうして両者を「ハ」でつなぐことができるのかという疑問に対して、ほら、よく考えてごらん、前と後とで絡んでいるところがあるだろう、と証明してみせているのである。
(補注1)拙稿「令和の出典、万葉集巻五「梅花歌三十二首」の「序」について─「令」が「零」を含意することを中心に─」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/994f3bd968826c87cb3a8d8845581d17参照。王羲之の蘭亭の序を意識した催し物で、実際に梅の花を見て歌を作っているわけではないことは暦日からも窺える。
(補注2)中西1978.304頁。
(補注3)原文の「留牛馬」部分については異動がある。「留鳥浦之」をアミノウラノ、「留牛鳥浦之」をニホノウラノと訓む説もある。それらの訓みに有意性を見出せないので、通訓のナハに従った。
(引用・参考文献)
澤瀉1963. 澤瀉久隆『萬葉集注釈 巻第十二』中央公論社、昭和38年。
小柳2004. 小柳智一「「ずは」の語法─仮定条件句─」『萬葉』第189号、2004年7月。萬葉学会ホームページhttps://manyoug.jp/memoir/2004
多田2009.&2010. 多田一臣『万葉集全解1・2・3・4・5』筑摩書房、2009年、『同6・7』2010年。
中西1978. 中西進『万葉集 全訳注原文付(一)』講談社(講談社文庫)、1978年。
浜田1986. 浜田敦『国語史の諸問題』和泉書院、1986年。
吉井2021. 吉井健「副詞「おほかたは」について」『萬葉集研究 第四十集』塙書房、令和3年。
※「ズハ」については数多くの論文を参照したが、引用したものに限って記載した。
※2024年12月に一部訂正した。
 広重・東都名所 道潅山虫聞之図(国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1303513をトリミング)
広重・東都名所 道潅山虫聞之図(国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1303513をトリミング) 広重・東都名所 道潅山虫聞之図(国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1303513をトリミング)
広重・東都名所 道潅山虫聞之図(国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1303513をトリミング)