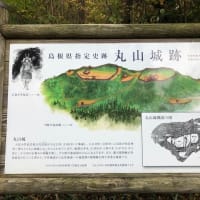63.戦国の石見(続き−2)
63.5.福屋隆兼の没落
63.5.1.福屋隆兼の逃亡

65.5.1.1.福屋隆兼の行動
川上松山城を落城させ、福屋隆任、神村長氏等の首級を得た毛利元就は、その福屋隆任の首級を父隆兼に送り、強い意志を見せつけた。
そして、翌日の永禄5年(1562年)2月7日には、福屋隆兼の本城乙明攻略に向かったのである。
先鋒は吉川元春で宍戸らの諸将を従え乙明城に向かって進んだ。
毛利元就は、小早川隆景とともに阿登ノ市(江津市跡市)に発向した。
福屋隆兼はこの急報に接し、一族老臣らと協議したが、士気すでに阻喪して防戦不可能な情勢であった。
そこで、福屋隆兼は、その夜ひそかに城を脱出して、浜田の細越山に遁れた。
しかし、吉川元春はすぐさま隆兼を追撃にむかった。
元春方の勢いに、福屋勢は抗うこともできず、その子彦太郎らと共に浜田から小舟に乗って出雲の尼子義久を頼って行った。
しかし尼子義久は毛利との和談に拘っており、隆兼らを庇護しようとしなかった。
仕方なく隆兼はさらに潜行して大和に逃げ、信貴山城(奈良県生駒郡)の松永弾正(久秀)を頼った。
ここに滞在した期間は明らかでない。
その後、隆兼は蜂須賀家政(蜂須賀正勝(小六)の子)に仕え、播磨の龍野から阿波の渭津城(徳島城)に移ったという。
陰徳太平記では、
坂本に境目論(所領の境界を巡る紛争)の出来けるに、駆け合わせ、比類なき働きをして討たれけるとぞ聞こえし。
とある。
この坂本は徳島県勝浦町の坂本であろう。
福屋隆兼の家族
福屋隆兼の室は吉川国経の娘である。
吉川国経には三男二女がおり、もう一人の娘は毛利元就の正室となり妙玖と称した。
隆兼の子に、彦太郎、次郎、宮丸がいた。
福屋彦太郎(嫡男)
嫡子彦太郎は隆兼と一緒に石見を逃れ、その後1580年初頭には、彦太郎は豊臣秀吉に仕え因幡と伯耆に居たという。
福屋次郎隆任(次男)
永禄5年(1562年)2月の川上松山城攻防戦で戦死した。
福屋宮丸(三男)
福屋隆兼は自分の息子・宮丸を幼少の時から井田兼之(福屋氏の末流)に仕える井出原官左衛門に預けた。
隆兼が逃亡すると福屋宮丸という名を捨てて井出原管助と名乗った。
その後の経緯は明らかでないが、宮丸の子孫は井出原という名をすて福屋に戻し、毛利家に仕えた。
宮丸から13代後の福屋半左衛門 (嘉永4年(1851年)2月15日没)の墓が山口県萩市に在る。
65.5.1.2.残された福屋の家人たち
一方福屋隆兼に見捨てられた者たちのことである。
福屋隆兼を追って浜田まで来た吉川元春勢は、福屋に一味した三子山城(城主:岡本兼祐)を攻めた。
この三子山城では、福屋の家人たちも立て籠もりで防戦していた。
しかし、岡本兼祐は、2月15日あっさりと降参した。
だが、三ッ子山城で戦っていた、福屋の家人家人福屋兵部大輔・千代延藤左衛門等はこのまま、犬死にするのは口惜し、せめて清らかに戦死すべしと、2月29日に麓の三宮神宮(浜田市黒川)に立て籠もり抵抗を始めた。
そこに、元就は使者を遣わしてこう伝えた。
隆兼既に逐電の上は家人等に於いて全く遺恨はない、残った者は一命を助け置き日頃の武勇諸芸堪能等に応じた所領を与える。
今詮無く戦死しても、何の為にもなりはしない。
早く降参せよと宥められると、流石に命が惜しいため、皆降参してしまう。

<石見国三宮神社>
毎週土曜日の夜は浜田の夜神楽週末公演の会場として使用されている。




毛利、福屋勢を殺害する
毛利の軍門に降った福屋勢は、安芸新庄へ連れていかれ、各所に分けて監禁され、その後悉く殺害された。
また、その他の残党は元春の部将森脇飛弾守らによって掃滅されることになった。
そのうち、大朝の養性寺に監禁されたが、神主内蔵允、稲光内蔵大夫たちのことを陰徳太平記で書き述べている。
大朝の養生寺に神主内蔵允、稲光内蔵大夫二人が人質として居たところ、吉川・熊谷の家人60余人が押し寄せた。
是を見て二人の家僕たちは一人も残らず逃げ去り、神主、稲光唯二人が取り残された。
此の二人の者共は究竟の弓の上手で其の業は神の如くであった。
神主は力量人に超えたりと雖も中(あ)たりの細かなること、稲光には懸絶せり。
稲光は、力彼に如かずと雖も、三四段が間にては、下げ針 (糸でつり下げた針,弓の的としてきわめて小さいもの)など十に九つは治定(安定)して射当てけり。
平日自賛しけるは目にさえ見ゆるものならば、蚊の睫毛、蟻の髭たりと雖も、矢はあらじなど荒言(無責任に大きなこと)を吐きけり。
弓を唐人の張るが如くに中にて張り、又は茶碗に水十分に入れ置き、其のはたに押し当てて張りけるに、其の水傾き溢るる事無きが如くに。
そのように弓上手の者であったので、さしもの新庄、三入の者共も迂闊に進めなかった。
二人の戦い振りを聞いた、元春は「殺すには勿体ない兵士である。命を助けて召し使う方が良い」と云った。
その旨を二人に伝えた。
最初は信用しなかったが、最後には騙され捕まってしまった。
神主、稲光以外の千代延藤左衛門、同藤三郎、井下弥五郎、原田三郎左衛門等、何れも比類なき働きして討たれた、とある。
そして、
そのほか所々にて討たれける者共、何れも手を盡くし働かぬはなかりけり。
総て頸数一千余級とぞ聞こえし
と、陰徳太平記は結んでいる。
63.5.2.陰徳太平記
第34巻 福屋隆兼没落之事
去る程に福屋少輔隆兼は一方の依頼とする、中ノ村の城は切り崩され、矢上の城は明け退いた。
今は家城阿登(あと:有福温泉町)の乙明(本明)の一城に成ってしまったので、如何にすべきかと案じ続けていた所に、吉川元春を先陣として、元就朝臣既に乙明けの郷に打ち入ったと知らされた。
隆兼は一族郎党を集め、元就既に当城へ発向と聞く、しからば引受一戦の中に家の存亡を試むべきや、又来鋭を避けて重ねて時節を待ち本懐をや達すべき、各所存の趣申すべし、と意見を乞うた。
敵は猛勢也、殊に元就朝臣の謀に絆され、重富を先きとして多くの一族郎党を誅せしかば、勢微に成って、中々一戦もすべき様なかりける間、誰駆合わせて合戦すべきと思う心もなく後ろ髪のみ引かれて、万座一同に唯一先ず当城を御開き有って重ねて尼子を頼み、御国入るべしと諌めけるによって、隆兼この儀に同じ、取るものも取りあえず、夜中に城を忍び出で浜田の湊、細越と云う山へ取り上がりけり。
元春続いて細越へ追いかけ給へば、隆兼ここも堪えず、小船に取り乗りて、嫡子彦太郎、その外侍五六人相具して、雲州へと志し、既に漕ぎ出さんとする折しも、徳田刑部少輔馳来たり。
斯く御座すべしと諫言申し、御勘気を蒙り候ひき、御許しを得んと候はば、御先途を見届け申すべきにて候とて、渚に跪き座りて居たりければ、隆兼涙をはらはらと流して、此の有り様に成りし事、汝が意見を用いざりし故慣れば、他人よりも恥ずかしきは、刑部が心中なり。
只今の忠志生々世々に忘れるべからずとて、軈て(やが)て手を取って舟に乗せ、雲州へこそ落ち行きけれ。
生々世々(「しょうじょうせぜ」は、生まれ変わり死に変わりを繰り返して限りなく多くの世を経ることを意味する仏教用語)
其後隆兼は出雲にも住居成り難くて、大和国へ上り、松永弾正小弼を頼み、志貴の城に在りけるとかや。
刑部も是れ迄付き添いたりけるが、隆兼流浪みなれば、世のたづき(生活の手段)など万事浅ましきありさま也けるを、刑部菜摘水汲み習は業に、身を窶れ心を老せしめ、忠勤を抽(ぬき)んでるが、坂本(徳島県勝浦町)に境目論(所領の境界を巡る紛争)の出来けるに、駆け合わせ、比類なき働きをして討たれけるとぞ聞こえし。
忠と云い、義と云い、是亦以て天下後世の人の臣となって二心を懐く者を愧づかしむべきに足れり。
第34巻 家人被誅殺付稲光神主因勇被助命事
福屋隆兼没落せしかば、家子郎党に同苗兵部少輔を先として、一千余人主の隆兼には棄てられつ、芸州へ降人に出づつべきには便りなし。
路上母を失へる子、中流に楫(かじ)を断えたる舟の寄る方なき身の行末如何にせんと、惘(あき)れていたりけるが、かくては各自所々にて、あえなく犬死にせん事の口惜しければ、いざや三の宮の神宮寺に取り籠もり、清浄に戦死すべしとて、我先にと立て籠もり、弓の弦食い湿し矢束ね、解いて寄せくる敵を待ち懸かりけりたり。
然る所に元就朝臣使者を遣わし、隆兼既に逐電の上は家人等に於いて全く遺恨無し。
一命を助け置き日頃の武勇諸芸堪能等を正し、勝劣高下に応じて所領宛行うべき。
今詮無く戦死して、誰か為にかせん。
早く降人に出べしと宥められしかば、流石命は惜しかりけり。
皆おめおめと冑を脱いで降参の名を下しける。
頓(やが)て新庄へ召し具せられ、宗徒の者共をば所々に分ち置いて誅せられけり。
その中に大朝の養生寺に神主内蔵允、稲光内蔵大夫二人、人質として居たりけるを、吉川並びに熊谷の家人六十余人押し寄せたり。
是を見て二人が家僕共一人も残らず逃げ去り、今は神主、稲光唯二人に成りにける。
此の二人の者共は究竟の弓の上手にて其神を得たり。
神主は力量人に超えたりと雖も中(あ)たりの細かなること、稲光には懸絶せり。
稲光は、力彼に如かずと雖も、三四段が間にては、下げ針(糸でつり下げた針,弓の的としてきわめて小さいもの)など十に九つは治定(安定)して射当てけり。
平日自賛しけるは目にさえ見ゆるものならば、蚊の睫毛、蟻の髭たりと雖も、矢はあらじなど荒言(無責任に大きなこと)を吐きけり。
弓を唐人の張るが如くに中にて張り、又は茶碗に水十分に入れ置き、其のはたに押し当てて張りけるに、其の水傾き溢るる事無きが如くに。
其の妙巧を得たる者也ければ、寄せ手数人射伏せける間、さしも新庄、三入の仕手共も、進みかねてぞ居たりける。
神主は簀子の竹など切り折ってからめかし、矢種盡きざるを敵に知らせ、戸口毎に鎗を物に結付け置いて、行廻るついでに、之を動かせば寺中に大勢籠もりたる様にぞ見えにける。
さて二人差し詰め、引き詰め敢々に射ける所に、熊谷が家人誰とは知らず一人、思い切って味方の中を進み出で、是程の敵を今迄討ち得ざる事、熊谷が手の者共の恥辱也。
いで吾切入撮(つま)み殺してんと言いて、塀を乗り越ゆる所を稲光雁股を以て、塀の棟木に額を射付けたりければ、此の者心は猛く勇めども、些かも動かず、頓てそこにて死にけり。
同じ手の者に、杉原太郎左衛門と云う大剛の者、具足の胴丸計り取って着、遅れ馳せに来たりけるが、神主稲光とても、紀昌(趙の邯鄲の弓の名人)養由(中国、春秋時代、楚の弓の名人)が後身にもあるべからず。
何ほどの事の有るべきぞとて、門よりつと走り入りけるを、稲光透垣(すいがき)の隙間より射たる矢、誤らず杉原が真中後ろへずんと射通したれば、矢場に伏して死にけり。
あまりに徒矢(むだ矢)なく射立て、猛威を振るいける間、此由を聞き給い、元春、可惜(あたら)兵也、殺さんこと、戦神のお咎めもあるべし、唯助けて召し使うべき也。
其由粟屋源蔵、森脇一郎右衛門言い聞かせ候へと宣ければ、両人馳せ向かいて此由述べたりけれども、二人の者中々謀られ申すましと曽て𣴎引(よういん)せず。
この頃西国一と称する大勇将下の人々かく漂零(落ちぶれること)の身と成りたる福屋が家人誰二人を多勢押し寄せて討つ事を得ず、謀り給う事は、日頃の武名の瑕瑾也。
唯一文字に切入給へ、矢種の有らん限りは、射盡くし、我等が弓勢の程をも見せ申し、又音に聞こえたる、吉川、熊谷衆の御腕の力、打ち物達者の程をも試み、冥土の思い出、閻魔の廰の娑婆物語にも仕るべきにて候ぞと罵りければ粟屋源蔵、侍の妄語することやあると、云い敢えず踊り入る所を、稲光引き設けたる矢なれば、ひゅうと放つ。互いに運や強かりけん,粟屋が股の間を後ろへ射通したり、粟屋頑なる者共の振舞哉。
一命を助けんと云うに、己が心の侫けたるままに疑いをなす事のはかなさよ。
八幡大菩薩も冥観あれ。お助けあるぞ。
我等を人質に執りて安堵の思いをなせんとて、刀脇差し抜き捨てて内へ入りたりければ、さては疑うべきにあらず。
二人の者共弓投棄て有り難しと悦びてい出ける間、元春の家人に召し置かれけり。
千代延藤左衛門、同藤三郎、井下弥五郎、原田三郎左衛門等、何れも比類なき働きして討たれにけり。
福屋兵部少輔は腹掻き切って伏しけるを、頸をば森脇一郎右衛門討ち手けるに、右京手早き男にて散々に切り結び、武永に数か所手を負はせける所を、山縣四郎右衛門はせ来たりて鎗にて突き伏せ、武永を助けてけり。
そのほか所々にて討たれける者共、何れも手を盡くし働かぬはなかりけり。
総て頸数一千余級とぞ聞こえし。
<続く>