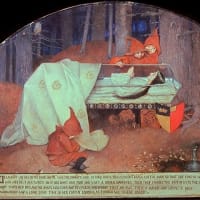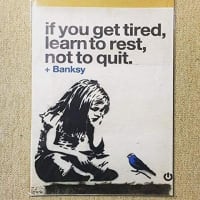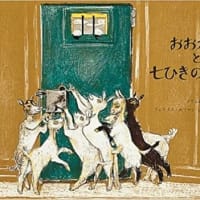『獣の奏者』の1・2巻を読み返しました。
『獣の奏者』の1・2巻を読み返しました。
この本は2006年に刊行されています。
3年ぶりに読み返して、思い出しました。
そうでした。
ラストに意義あり。
 上橋菜穂子さんは『獣の奏者』の「完結編」のあとがきで
上橋菜穂子さんは『獣の奏者』の「完結編」のあとがきで
「『獣の奏者』は、<闘蛇編><王獣編>で完結した物語りでした。<王獣編>のあとがきにも書いたように、あの物語は、獣(遠い他者)に向かって、ひたすら思いを伝えようとする人の姿を描いたもので、その結末としては、あれがすべてだと感じていたからです。その思いは、いまも変わっていません」と書いています。
でも、それはどうでしょう?
2巻の<王獣編>のラストは、「えっ、それでどうなったの? まさか、これでお終い?」と読者を戸惑わせるものでした。
たしかに、すごい盛り上がりで引き込まれ、感動するのです。ストーリーテラーとしての力量はすごい。
でも、感動したからって、その後の着地点が語られなかったら、あまりにも…。
物語作家としての役割が、果たされないままじゃないですか?
 時間というのは、過ぎ去っていきます。
時間というのは、過ぎ去っていきます。
わたしたちには常に「いま」というときしかなくて、「いま」はすぐに過去のなかにまぎれてしまう。
サーファーのように、「いま」という時間に乗っているしかないのが、生身のわたしたちです。
でも、物語は時間をすくい取れる。
時間を区切って定着させることができるんです。
作家は、すくいとった時間のなかで、物語を展開します。
作家が想像した物語が語られます。
そして、物語は、「~しましたとさ、チャンチャン」と落としどころがないと、おさまりません。
中途半端なままおしまいにするなら、それは物語として片手落ち。
なんのために、物語を始めたのかというと、終わらせるためです。
そして、その顛末を読者に語り聞かせるためです。
 作家だからといって、「自分の創った物語は自分のもの」と勘違いしてはいけないと、思います。
作家だからといって、「自分の創った物語は自分のもの」と勘違いしてはいけないと、思います。
読者がいなければ、物語は意味がない。
読者が読む、あるいは聴くことが、その受身の行為が、物語を成立させるのです。
読者に最後まで物語を伝える義務が、作家にはあると思います。
読者が納得しなければ、物語としては完結していないんです。
それを、「あわわ」というところで打ち切って、「あとは想像にまかせる」、というのは、きつい言い方をすると、思いあがりだと思います。
思い起こせば、村上春樹氏の『1Q84』も、あれで終わりだとしたらあんまりではないか、という幕切れでした。
だから、サラ☆は憤りすら感じました。
『獣の奏者』も同じ。
 続編が書かれて、ほんとによかったです。
続編が書かれて、ほんとによかったです。
でも、欲を言うなら、<王獣編>のラストに、
「そしてそのあと、王獣は○○に着地しました。それぞれの人はこんなふうになりました。(エリンは、りらんは、ダミアは、エセルは、イアルは???…)
それから盛大な結婚式が行われました。
人々は、とりあえず平和な日々を迎えましたとさ」
という物語の落としどころを付け足してほしいです。
ほんとに10ページでいいんですから。
そんなことをしたら、物語の余韻が損なわれるなんて、考えるとしたら、ううっ、上橋さん、勝手すぎます。
最近の「上橋菜穂子の世界」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ジブリノート(2)
- ハル文庫(100)
- 三津田さん(42)
- ロビンソン・クルーソー新聞(28)
- ミステリー(49)
- 物語の缶詰め(88)
- 鈴木ショウの物語眼鏡(21)
- 『赤毛のアン』のキーワードBOOK(10)
- 上橋菜穂子の世界(16)
- 森について(5)
- よかったら暇つぶしに(5)
- 星の王子さま&サン=テグジュペリ(8)
- 物語とは?──物語論(20)
- キャロル・オコンネル(8)
- MOSHIMO(5)
- 『秘密の花園』&バーネット(9)
- サラモード(189)
- メアリー・ポピンズの神話(12)
- ムーミン(8)
- クリスマス・ブック(13)
- 芝居は楽しい(27)
- 最近みた映画・ドラマ(27)
- 宝島(6)
- 猫の話(31)
- 赤毛のアンへの誘い(48)
- 年中行事 by井垣利英年中行事学(27)
- アーサー・ランサム(21)
- 小澤俊夫 昔話へのご招待(3)
- 若草物語☆オルコット(8)
バックナンバー
人気記事