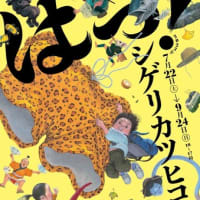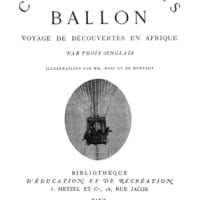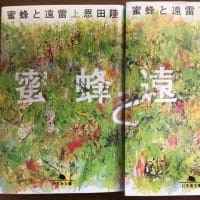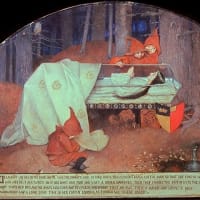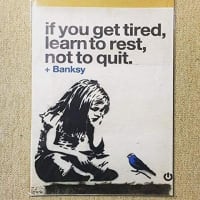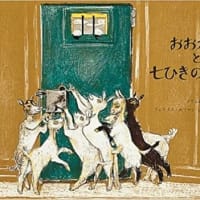少し古い話になるが、昨年末から今年の年頭にかけて、スウェーデンの作家、スティーグ・ラーソンの『ミレニアム』に没頭していた。3部作でそれぞれ分厚い上下巻なので、6冊を一気に読み通したことになる。
少し古い話になるが、昨年末から今年の年頭にかけて、スウェーデンの作家、スティーグ・ラーソンの『ミレニアム』に没頭していた。3部作でそれぞれ分厚い上下巻なので、6冊を一気に読み通したことになる。ちょうど入院中の父親の看護をしていたが、仕事が手を離れたこともあって、深く海の底に潜るように、本の中に潜っていた。
父が2月に亡くなった。
そんなことなど思いもよらず、読書の喜びに浸っていた。
少なくとも、この本を読んでいたときには、父は確かに生きていたわけで、忘れられない本になった。
 『ミレニアム』はいまさら言うまでもないが、読み応え十分のミステリだ。
『ミレニアム』はいまさら言うまでもないが、読み応え十分のミステリだ。とくに触れておきたいのは、第一部『ドラゴン・タトゥーの女』の書き出しの部分。
主人公のミカエル・ブルムクヴィストは、「名探偵カッレさん」とあだ名で呼びかけられる。
20年ほど前、駆け出しの新米ジャーナリストに過ぎなかったミカエルは、銀行強盗事件の解決に大きな役割を果して、花形記者の地位を手に入れた。
しかし、名声には代価が……。
「別のタブロイド紙が“名探偵カッレくん、ビーグルボーイズ事件を解決”という見出しを掲げたのだ。
年配の女性コラムニストの筆になるこの冷やかし半分の記事は、アストリッド・リンドグレーンの生み出した少年探偵を十ヵ所以上にわたって引きあいに出していた。
そのうえ、ミカエルが人差し指で何かを指差して口を開き、制服警官に何やら指示しているように見えるピンボケ写真まで載せてあった。
このとき彼は、便所ならあちらですよ、と言っていたのだが」(ハヤカワ文庫より)
ミカエルは、このあだ名が嫌で仕方がない。
大の大人でベテランジャーナリストが、子どもの本の主人公の名前でからかわれるのである。例えば、すぐれた論説を書いても、「へい、ドラえもん」と呼ばれるのと同じことかも。
 それはともかく、名探偵カッレくんは、後々名作になるに違いないミステリーの冒頭に、こういう形で登場する。
それはともかく、名探偵カッレくんは、後々名作になるに違いないミステリーの冒頭に、こういう形で登場する。このエピソードは、作品に特別な効果を与えていると思う。
リンドグレーンに親しんだことのある読者は、ホームタウンに帰ったような共感を覚えると思うのだ。
そして、子どもの頃に大好きだったカッレくんが登場するからには、この本は読むに価する本に違いないと、一応の好意的な受け入れ態勢を取る。
過去を共有する仲間として、読書に入るんじゃないだろうか。
つまり、何が言いたいかというと、子どもの本の力は大きいということである。
子ども時代の幸せな読書の記憶を呼び起こすことで、読者を味方につけることができる。仲間にすることができる、ということだ。
もちろん、作品が優れていなければ問題外なのだが、読者の子どもの本の記憶にインプットすることは、強力な小説作成術なのだと思う。
子どもの本は、「強力な磁石」なのだ。
 訳者のヘレンハルメ美穂さんはあとがきで、次のように述べている。
訳者のヘレンハルメ美穂さんはあとがきで、次のように述べている。「ミカエルとリスベットという人物が生まれるきっかけとなった要因がもう一つある。本書でも何度か言及されているスウェーデンの国民的児童文学作家、アストリッド・リンドグレーンの作品が、インスピレーションの源となっているという。リスベット・サランデルのモデルは、破天荒で行儀は最悪、されど力持ちで正義の味方、“長くつ下のピッピ”。現代社会に、大人になったピッピがいたとしたら、彼女はどんなふうに生きているだろう? どんなレッテルを貼られるだろう? そんな想像から、型破りな天才リサーチャーが生まれた。そして、そんなリスベットと補い合う、まったく正反対の人物として、優等生タイプで人好きのする“名探偵カッレくん”、ミカエル・ブルムクヴィストが配置された。」
 なるほど、なるほど、そういうことか。
なるほど、なるほど、そういうことか。興味はさらに強く刺激されるのだ。