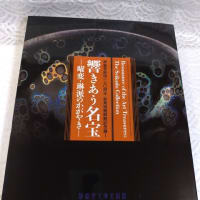【松平・徳川氏の歴史】
*清和源氏新田流とされる。三河国の有力
武士団。本貫地は上野国新田郡徳川郷と
いう。(旧地名:群馬県新田郡尾島町
世良田、新地名:群馬県太田市世良田町)
*三河国松平郷に起こり、15世紀初めに
岩津(岡崎から北北西に3km)に進出し、
西三河三分の一を所領として発展した。
室町幕府政所執事伊勢氏の被官として
の活動が見られる。応仁・文明の乱では
岡崎・安祥城などを入手した。このころ
岡崎・安祥・能見(のみ)・長沢・形原
(かたのはら)・竹谷・五井などの庶家
が成立している。岩津松平氏は永正三年
(1506)から同五年の今川氏との戦いで
滅亡し、安祥松平氏が惣領となる。以後
大給(おぎゅう)・滝脇・桜井・矢田・
福釜・青野・藤井・などの庶家を分出する。
*しかし、長親(家康五代の祖父)が嫡男
信忠より次子信定をとりたてたため、
家中は分裂した。信忠は清康に家督を譲り、
三木・浅井を分立させて隠居した。清康は
本拠を岡崎へ移し、三河の統一をめざした。
享禄四年(1531)より、清康は『世良田
(せらだ)』を称する。(世良田二郎三郎
清康・安祥四代岡崎殿)天文四年(1535)
の清康の死(森山崩れ)で、惣領職は一時
桜井家(信定)に渡った。広忠が岡崎に復帰
するも、織田氏の圧力により、松平一族は
分裂して衰退する。織田氏と抗争をする
今川氏が、一時期三河一国を領有し、松平
氏はこれに従った。桶狭間の戦いで今川義元
が戦死すると、松平氏は今川氏から独立し、
戦国大名として発展していき、豊臣大名と
なって五奉行に列し、ついには慶長八年
(1603)に家康が征夷大将軍に任ぜられ
江戸に幕府を開き、統一権力者となる。
この間に松平氏庶家は宗家の家臣化を遂げ、
江戸期には大名・旗本として、その多くが
存続した。
↓ランキングに参加中。クリック応援よろしくお願いします!

にほんブログ村
*清和源氏新田流とされる。三河国の有力
武士団。本貫地は上野国新田郡徳川郷と
いう。(旧地名:群馬県新田郡尾島町
世良田、新地名:群馬県太田市世良田町)
*三河国松平郷に起こり、15世紀初めに
岩津(岡崎から北北西に3km)に進出し、
西三河三分の一を所領として発展した。
室町幕府政所執事伊勢氏の被官として
の活動が見られる。応仁・文明の乱では
岡崎・安祥城などを入手した。このころ
岡崎・安祥・能見(のみ)・長沢・形原
(かたのはら)・竹谷・五井などの庶家
が成立している。岩津松平氏は永正三年
(1506)から同五年の今川氏との戦いで
滅亡し、安祥松平氏が惣領となる。以後
大給(おぎゅう)・滝脇・桜井・矢田・
福釜・青野・藤井・などの庶家を分出する。
*しかし、長親(家康五代の祖父)が嫡男
信忠より次子信定をとりたてたため、
家中は分裂した。信忠は清康に家督を譲り、
三木・浅井を分立させて隠居した。清康は
本拠を岡崎へ移し、三河の統一をめざした。
享禄四年(1531)より、清康は『世良田
(せらだ)』を称する。(世良田二郎三郎
清康・安祥四代岡崎殿)天文四年(1535)
の清康の死(森山崩れ)で、惣領職は一時
桜井家(信定)に渡った。広忠が岡崎に復帰
するも、織田氏の圧力により、松平一族は
分裂して衰退する。織田氏と抗争をする
今川氏が、一時期三河一国を領有し、松平
氏はこれに従った。桶狭間の戦いで今川義元
が戦死すると、松平氏は今川氏から独立し、
戦国大名として発展していき、豊臣大名と
なって五奉行に列し、ついには慶長八年
(1603)に家康が征夷大将軍に任ぜられ
江戸に幕府を開き、統一権力者となる。
この間に松平氏庶家は宗家の家臣化を遂げ、
江戸期には大名・旗本として、その多くが
存続した。
↓ランキングに参加中。クリック応援よろしくお願いします!
にほんブログ村