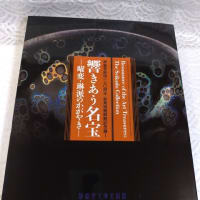【武田氏の歴史】
*新羅三郎義光の三男義清が、常陸国武田郡
を名字の地とした。義清の子清光は甲斐国
に配流され、子孫は同国に繁栄する。清光
の次男信義は「武田太郎」を称し、甲斐源氏
の惣領として治承・寿永の内乱期に活躍した。
*南北朝期になり、安芸守護の武田信武が
足利尊氏に属し、本国甲斐に入国して守護
となり、長男信成の系統が、以後同国守護
を相承する。次男氏信の系統が安芸分郡
守護職を務め、1440年一色氏討伐後若狭
守護にも補任される。両国守護職は惣領家
が保持しつづける。その後安芸の系統は
大内氏に滅ぼされ、若狭の系統は朝倉氏に
攻められ従った後、1573年信長の越前攻略
により滅亡する。
*甲斐の系統は1416年の上杉禅秀の乱以降
幕府と鎌倉幕府の対立の狭間におかれ、
家督は国外への流浪を余儀なくされたが、
1439年の永享の乱後幕府の支援によって
復活する。信昌の時、関東の内乱に影響
されて甲斐国内も内乱化し、守護代跡部氏
を滅ぼして統一的権力を確立する。ただし、
次いで嫡子信縄と対立し、今川氏・北条氏
らの介入をうけ、国内は大きく分裂した。
その後、信縄の子信虎が国内を統一し、
戦国大名化を遂げる。
*信虎は1519年古府中に躑躅ケ崎館を築造
し移り、領国支配の基礎とする。今川氏と
婚姻関係を結び北条氏と和を計って信州
進攻を開始するが、1541年嫡男晴信に
よって駿河へ追放される。
*晴信(信玄)は信州の諸豪族を討滅あるいは
追放し、大部分を計略。上杉謙信と信州・
北関東で戦うなどし、1554年には今川氏と
北条氏の婚姻関係を仲介し甲駿相三国同盟
(善徳寺の会盟)をむすび、領国経営と関東・
越後・越中の攻略を視野に入れる。ところが
1560年桶狭間の戦いで今川義元が没すると
徳川家康の策動もあり、嫡子義信を自害させた
ことにより三国同盟が破綻。家康と組んで
駿河進出をした後家康と戦い信長と対立する
など迷走を続け、三方が原の戦いの中、容体
が悪化し陣没する。
*子の勝頼は長篠の合戦で信長・家康連合軍に
敗れた後、甲斐国を全面制圧され自刃する。
※源氏の新羅三郎義光の流れをくむ名族
であり、安芸・若狭・甲斐をその手に
おさめていたのに、変化する周辺情勢に
手をこまねいている間に軍場の灰塵と
化す。“諸行無常”でございます。
↓ランキングに参加中。クリック応援よろしくお願いします!

にほんブログ村
*新羅三郎義光の三男義清が、常陸国武田郡
を名字の地とした。義清の子清光は甲斐国
に配流され、子孫は同国に繁栄する。清光
の次男信義は「武田太郎」を称し、甲斐源氏
の惣領として治承・寿永の内乱期に活躍した。
*南北朝期になり、安芸守護の武田信武が
足利尊氏に属し、本国甲斐に入国して守護
となり、長男信成の系統が、以後同国守護
を相承する。次男氏信の系統が安芸分郡
守護職を務め、1440年一色氏討伐後若狭
守護にも補任される。両国守護職は惣領家
が保持しつづける。その後安芸の系統は
大内氏に滅ぼされ、若狭の系統は朝倉氏に
攻められ従った後、1573年信長の越前攻略
により滅亡する。
*甲斐の系統は1416年の上杉禅秀の乱以降
幕府と鎌倉幕府の対立の狭間におかれ、
家督は国外への流浪を余儀なくされたが、
1439年の永享の乱後幕府の支援によって
復活する。信昌の時、関東の内乱に影響
されて甲斐国内も内乱化し、守護代跡部氏
を滅ぼして統一的権力を確立する。ただし、
次いで嫡子信縄と対立し、今川氏・北条氏
らの介入をうけ、国内は大きく分裂した。
その後、信縄の子信虎が国内を統一し、
戦国大名化を遂げる。
*信虎は1519年古府中に躑躅ケ崎館を築造
し移り、領国支配の基礎とする。今川氏と
婚姻関係を結び北条氏と和を計って信州
進攻を開始するが、1541年嫡男晴信に
よって駿河へ追放される。
*晴信(信玄)は信州の諸豪族を討滅あるいは
追放し、大部分を計略。上杉謙信と信州・
北関東で戦うなどし、1554年には今川氏と
北条氏の婚姻関係を仲介し甲駿相三国同盟
(善徳寺の会盟)をむすび、領国経営と関東・
越後・越中の攻略を視野に入れる。ところが
1560年桶狭間の戦いで今川義元が没すると
徳川家康の策動もあり、嫡子義信を自害させた
ことにより三国同盟が破綻。家康と組んで
駿河進出をした後家康と戦い信長と対立する
など迷走を続け、三方が原の戦いの中、容体
が悪化し陣没する。
*子の勝頼は長篠の合戦で信長・家康連合軍に
敗れた後、甲斐国を全面制圧され自刃する。
※源氏の新羅三郎義光の流れをくむ名族
であり、安芸・若狭・甲斐をその手に
おさめていたのに、変化する周辺情勢に
手をこまねいている間に軍場の灰塵と
化す。“諸行無常”でございます。
↓ランキングに参加中。クリック応援よろしくお願いします!
にほんブログ村