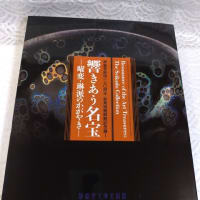【斯波氏の歴史】
*足利泰氏の長男家氏に始まる、足利一門中
の名族。鎌倉期には御家人として活動した。
斯波の家名は、所領の陸奥国斯波(紫波)に
由来する。
*高経は足利尊氏・義詮に仕え、康安の変後、
子息義将を幕府執事に登用するなどして幕政
を運営するも、貞治五年(1366)高経・義将
父子は失脚し、分国越前に没落した。
*翌六年(1367)の高経没後、すぐに義将は
幕府に復帰し、康暦の政変で細川頼之を排斥
すると、将軍義満・義持をたすけ、三度管領
になるなど幕府宿老として重きをなし、以後
細川・畠山両氏とともに、三管領の一家と
して幕政を左右した。
*義将の子義教(義重)は、従来の分国越前に
加え、尾張・遠江の守護を兼帯し、以後この
三国が世襲された。
*義教の孫義健の没後、一族の義敏と渋川義鏡
の子義廉とが家督を争い、応仁の乱の一因とも
なる。
*乱後、越前は朝倉氏、尾張は織田氏、遠江は
今川氏に奪われ没落し、戦国期の義銀まで
僅かに命脈を保った。その義銀も1560年5~6月
頃信長から国外に追放される。伊勢・河内を
流浪した後1600年に没したという。
※三管領に列した名族も最後は伊勢・河内を
流浪のうえ没するという・・“諸行無常”で
ございます。
↓ランキングに参加中。クリック応援よろしくお願いします!
 にほんブログ村
にほんブログ村
*足利泰氏の長男家氏に始まる、足利一門中
の名族。鎌倉期には御家人として活動した。
斯波の家名は、所領の陸奥国斯波(紫波)に
由来する。
*高経は足利尊氏・義詮に仕え、康安の変後、
子息義将を幕府執事に登用するなどして幕政
を運営するも、貞治五年(1366)高経・義将
父子は失脚し、分国越前に没落した。
*翌六年(1367)の高経没後、すぐに義将は
幕府に復帰し、康暦の政変で細川頼之を排斥
すると、将軍義満・義持をたすけ、三度管領
になるなど幕府宿老として重きをなし、以後
細川・畠山両氏とともに、三管領の一家と
して幕政を左右した。
*義将の子義教(義重)は、従来の分国越前に
加え、尾張・遠江の守護を兼帯し、以後この
三国が世襲された。
*義教の孫義健の没後、一族の義敏と渋川義鏡
の子義廉とが家督を争い、応仁の乱の一因とも
なる。
*乱後、越前は朝倉氏、尾張は織田氏、遠江は
今川氏に奪われ没落し、戦国期の義銀まで
僅かに命脈を保った。その義銀も1560年5~6月
頃信長から国外に追放される。伊勢・河内を
流浪した後1600年に没したという。
※三管領に列した名族も最後は伊勢・河内を
流浪のうえ没するという・・“諸行無常”で
ございます。
↓ランキングに参加中。クリック応援よろしくお願いします!