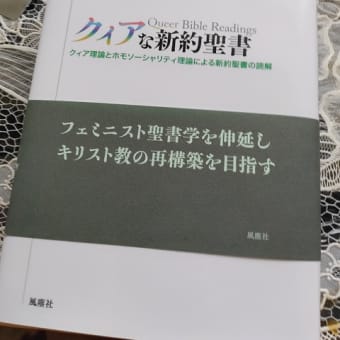MXテレビで11時から放映されていた『独孤皇后〜乱世に咲く花〜』が全50話最終回であった。このドラマの前の『如懿伝〜紫禁城に散る宿命の王妃〜』に引き続き中国ドラマを見ていた。自動録画の設定をしたままで、なんとなく見ただけである。
『如懿伝』については、このブログでも取り上げたことがある。参考まで。
「『如意伝』と『軽蔑』と僕」、というタイトルで記したものだ。
https://blog.goo.ne.jp/meix1012/e/45faa6e93a602d6b78cc0fd91a491a6f
で、今回は『如懿伝』ほどのドラマではないという感想であるが、ちょっと気付いたことがあるので、それについて書いてみよう。
人が亡くなるのだが、病死や衰弱死の場合、自分が亡くなる時期を正確に予見しているように描かれているのだ。人間は死ぬ時期を予見できる、そういうものだと僕たちは思っていたりはしない。
『独孤皇后』では、主人公の皇后が最期を迎える。心の病で衰弱するのだ。そして、自ら旅立つことを自覚し、思いを述べ、あたかも予測通りに亡くなってしまう。
フィリップ・アリエスの本を思い出していた。印象に残っているのが次のようなことだ。
近代以前の西欧世界の人間は、自分がいつ死ぬのかわかっていたという。そのため死期が近づくと、自分が死ぬための準備、家族にするべきことなどを伝えていたというのだ。これは逆説的に、近代になって自分がいつ死ぬのかがわからなくなったということになる。それは死にゆく存在としての人間であることを、当の本人が知っていたということであり、死を身近なものとしていたという感覚を持っていたことを意味する。
「14世紀から15世紀にかけての、富と栄光を渇望する世界の中で、幅をきかせ、強迫観念にまでなるのである。……中世末の人間は、…自分の無力さを、自分の肉体的破滅、自分の死と同一視したのである。自分が落伍者であると同時に死者であると見た。……当時、死はあまりにも親しみ深い、恐怖を与えぬものであった。それが人の感情をかき立てるようになったのは、死それ自体によるのではなく、死と失敗との接近によってである。」(フィリップ・アリエスに『死と歴史』みすず書房1983)
人間は元来「無力」を自覚し、死を受け入れていたのだが、近代になって「富と栄光」に自らを奪われて、その人間の本来性を喪失していく。「栄光」を科学や医療の発達とすれば、それらの発達が死を忘れさせてきたのである。確かに僕たちの生活からは、死の匂いがなくなっており、生の幸福感だけが社会にあるかのようだ。
歴史学者アリエスのこのような研究を中国ドラマから思い出すのだ。ドラマの中では、確かに中国皇帝の近辺の勢力争いで人が殺されたりする。その意味で人間が無残に扱われる。ところが同時に、そこに描かれる人物は死を身近にしながら生きてもいるのではないか、そんな気がしてくるのである。
最近がん闘病などで死を意識する機会があると思う。その時、死を受け入れる準備をするのではなく、生きる欲望だけが増加しているように感じるのは僕だけだろうか。特に医療が発達しているからでもあるだろう。そう考えると、医療の発達が人間が必ず死ぬという事実から遠ざけている、そんな矛盾した状況を生きるしかない、不可思議なことだと思うのは考えすぎだろうか。
死は「恐怖を与えない」、生きることが「強迫観念」、僕たちの常識を照らすと思う。