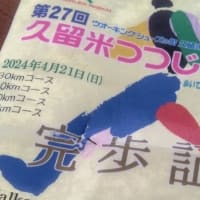昨日も、久留米まち旅博覧会である。
近代的なBS久留米工場でタイヤ製造工程を見学した翌日は、ここ田主丸大塚古墳公園にいる。
大した落差である。

案内を受け持つのは、久留米市埋蔵文化財センター職員である。
ここ大塚古墳公園には大小二つの古墳が保存されている。

大塚2号古墳。
「普段は入れないですが、今日は特別に中に案内します。」(埋蔵文化財保護課職員)
真っ暗な中、羨道から前室を通り、玄室に入る。
玄室は、10人は楽々入れる程で、案外と広い。

天井に被せられた巨大な石。
筑紫平野には八女、広川、朝倉、小郡、中でも高良山麓には無数と言っていい程の古墳群がある。
古墳時代、筑後地方は、日本第一等の都会であった事は間違いない。

こちらは大塚第一号古墳。
築年代は古墳時代後期6世紀後半らしい。
全国的に古墳が小型化する中、この一号墳は九州一の大きさであるという。
何故、この時代に大型の前方後円墳が作られたのか、大いに興味がそそられる。

円墳頂上部に登る。

大塚一号墳は、筑紫平野を見渡せる、耳納連山中腹の台地に造られている。
「この風景を、古代人も見ていたんですね。」(埋蔵文化財保護課職員)
かつては、この地域の豪農の別荘が、ここに建てられていたんだとか。
「なので、この頂上部は平に削られてしまいましたが、あと数メートルは高かった筈です。」
当時でも、ここが古代人の墓であるとは、この辺りの人間なら、認識していた筈である。
やい、豪農か何か知らないが、なんて事しやがる!

御覧の様に現在は、古墳公園として保存されている。
「ですので、保存に関しては、もう心配ありません。」

「因みに、一号墳の玄室内の調査はしておりません。」(埋蔵文化財保護課職員)
との事。
何でと問うと、
「盗掘の痕跡も無かったですし、石室内は1300年前のままだと思います。でも、調査するという事は、なんらかを壊す事になります。」
保存する事が、一番大事なのだと言う。
将来、玄室の門石を壊すことなく調査できる様な、小型のファイバースコープ等の技術の発展を待ちたい。
その前に、その予算が付くかどうかの問題もあるが。

平原古墳群に移動。
鷹取山登山の際に、毎回見てきた馴染みの古墳である。
「この公園から25分程、歩いて貰います。」(埋蔵文化財保護課職員)
通いなれた道だ。
とっとこ行こうぜ。

平原古墳公園は紅葉がいい具合である。

この平原古墳群では、70基以上の古墳が確認されている。
言わば古代の共同墓地なのだ。
「ただし、墓を作る事の出来るのは、ある程度の地位にあった家系に限りますけどね。」
この平原古墳群は大塚古墳より、若干年代が下り、7世紀のものらしい。

円墳の頭頂部が崩れ落ちている古墳を上から覗く。
へー、俺も中に入ろっと。

熱心に古墳の解説をする職員。

玄室から見上げた空。
この様な、スッポンポンの墳墓はいいが・・・

この様に、入口以外は閉塞された墳墓には、
「午前の部では、ゲジゲジや蝙蝠がいた古墳もありましたので、そのつもりで。」
「ひえ~~~!!」(女性軍)
「げげ、そりゃ楽しみ!!入ろう、入ろう。」(私)
墓穴に入らずんば、蝙蝠を得ずである。

期待虚しく、この後数基の古墳に入ったが、蝙蝠様にはご対面は叶わなかった。
ゲジゲジはいたけど。
ここ平原古墳群内でも、墳墓の大きさ、使われている石等に明確な差がある。
経済格差=身分格差が、こんな面でも如実に見て取れる。
「いやー、今日は良かったですねー。」
一番嬉々として喜んでいたのは、他ならぬ担当の文化財保護課職員である。
何回入っても、古墳は楽しいみたいだ。
やっぱ、好きこそ物の上手なれってのは本当だね。
よかったね。
好きな事で飯が食えて。
でも、お陰で貴重な経験が出来たよ。