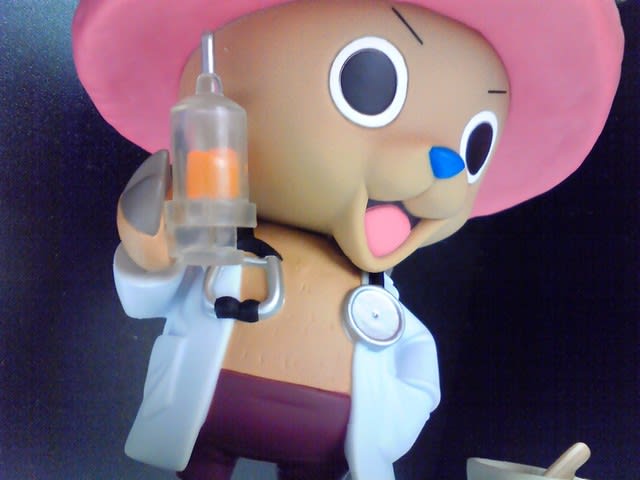
日本の(地方税も含めた)税収の総額は、四半世紀前の平成2年度からほぼ58兆円近辺で推移しておりほとんど変わっていません。一方歳出を見れば、社会保障を除く一般歳出は8000億円程度しか増えていない一方で、社会保障費は20兆円を超える大きな伸びを示しています。
さらに詳細を見ていくと、社会保障費の中でも、高齢化の影響を受け医療費の伸びが著しいことが判ります。
現在、概ね45兆円程度に膨らんでいる現在の国民医療費の内訳を見ると、医師や看護師などの人件費が20兆円、医薬品が10兆円、医療材料が3兆円、そしてその他施設整備費や光熱水費などで11兆円が費やされています。
一方、それに対する財源は、(大まかに言って)税金による負担が39%、保険料負担49%、患者の自己負担12%という構成で、9割近くが公的資金により賄われているという状況です。
今後、さらに高齢化が進む日本の人口構成を考えれば、持続可能な社会保障制度を維持していくため、様々な角度から分析することで最も効果的な標準医療を確立していく必要があるのは言うまでもありません。
無論、政府もこれまで医療費の増大に手をこまねいてきたわけではありません。
例えば、薬価は改定のたびに引き下げられてきており、2001年の薬価を100とすれば2012は70.3と、3割近く引き下げられました。しかし、それでも実際の薬剤費は同じ期間に3割以上増えているのが現状で、高齢化による使用量の増加に加え新たに保険収載される新薬がその原因と考えられています。
また、各都道府県では2025年の医療の提供体制を示す「地域医療構想」をまとめており、今後の10年間で全国で計15万床以上の入院ベッドを減らす計画を立てています。医療の供給体制を見直し病床数を減らすことで、過剰な入院治療を抑えていこうという目論見です。
さて、対応を迫られているこうした医療費の状況を踏まえ、4月11日の日本経済新聞では、慶応義塾大学教授の印南一路(いんなみ・いちろ)氏が、持続可能な社会保障制度を確立する観点から「医療費が膨張を続ける理由」について興味深い考察を加えています。
日本の国民医療費はそのまま市場規模を示すものであり、つまり言い換えれば医療は40兆円を超える「巨大産業」に他ならないと、印南氏はこの論評で指摘しています。
そのうち製薬産業、医療機器・材料産業だけでも10兆円超の規模があり、自動車産業と納税額を競っているということです。こうしたマーケットに介護市場の10兆円を加えると、医療・介護の市場規模は50兆円を超え、医師、看護師、介護士をはじめとする従事者も600万人に上ります。
因みに、日本の主要な産業の市場規模を見ると、食品産業でおよそ18兆円、通信産業が29兆円、銀行業が21兆円、機械が26兆円といったところですので、経済的に見ても「産業」としてのこの分野が、日本の経済(そして、社会や政治)に及ぼす影響の大きさが判ります。
当然これらの関係者は、基本的には医療費の増加を歓迎し、既得権益を守るために業界団体を通じて関係機関に働きかけると印南氏は説明しています。
医療政策は政府の審議会などで議論され決められていくわけですが、そこには(あまりに)専門的で一般国民には理解し難い部分があるのも事実です。さらに、民主主義国家では基本的に合意形成が重視されるので、政策が採用されるまで長い時間がかかるのも(ある程度は)やむを得ないことかもしれません。
しかしながら、(そうした理由ばかりでなく)産業としての影響力の大きさや専門家に独占された議論が、制度改革を阻む要因となっていることもあながち否定はできません。
例えば、医師の地域・診療科偏在問題は指摘されてから40年以上も解決されていないことを見ても、その難しさはよくわかります。印南氏によれば、強力な政策が採用されても激変緩和の名の下に経過措置が設けられ、中にはそのまま長期間継続しているものも少なくないということです。
一方、国民はと言えば、健康・医療が国民の最大の関心事であるにもかかわらず、自分が払う自己負担額や保険料には関心はあっても、制度全体の持続性に関心を持つ人は決して多くないと印南氏は指摘しています。
国民皆保険は世界に誇れる素晴らしい制度だが、作られてから既に半世紀が経過し、これまで制度を維持するために払われた血のにじむような努力が忘れ去られているのではないかというのが、こうした問題に対する印南氏の認識です。
例えば、1973年の老人医療費の無料化で過剰に医療費が増えその修正に10年近い年月を要したのに、今度は未就学児・就学児の医療費無料化措置が全国で拡大していると氏は指摘しています。
また、3.8兆円に及ぶ生活保護費の約半分が医療扶助で占められている現状を見ても、無料化がいかに医療費の無駄使いを助長するかがわかるということです。
社会全体のコストを無視し、財源の手当てを考えない政策は「無責任」だと、印南氏はこの論評で強調しています。
高齢者や小中学生や低所得者など、一見、社会的に弱い立場にある人々に優しく見える政策を拡大するヒューマニスティックな力が、実は医療費問題の解決を難しくしていると氏は考えています。
内外からの拡大圧力に耐え切れず(世界に誇る)国民皆保険制度自体が破綻するようなことがあれば、結局、そのツケを払わなければならないのはそうした立場にある人々であることは言うまでもありません。
医療費の分析から得られる抑制策はどれも重要ですが、少なくとも現時点では「決定的」な対策とまでは言えないようだと、この論評の最後に印南氏は述べています。
そうした中、診療報酬の単価を一律に切り下げるような極端な措置に訴えずに、(制度への極力少なくするような形で)医療費の伸びを抑えていくにはどうしたら良いのか。
社会の状況に合わせ将来世代に負担を残さないよう、利害関係者自らがそれぞれ(地道に)知恵をしぼっていく必要があると、この論評から私も改めて心に留めたところです。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます