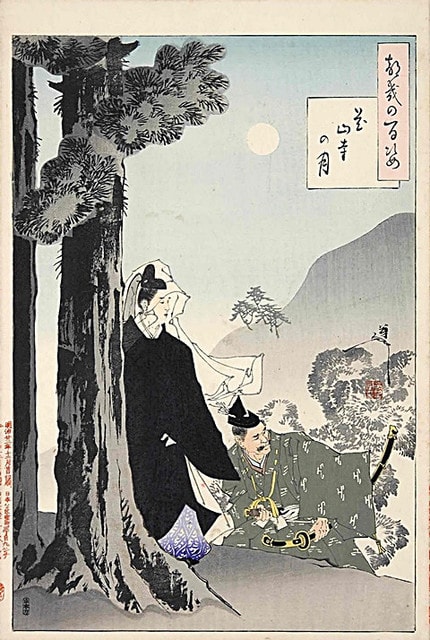月岡芳年 月百姿
『世尊寺乃月』 少将義孝
明治二十一年印刷

藤原義孝(ふじわらのよしたか)は 平安時代中期の公家・歌人
天暦8年(954年)~天延2年(974年)
摂政・太政大臣 藤原伊尹の四男 母は醍醐帝の孫 恵子女王
京都郊外の世尊寺の庭で物思いに耽る義孝

国立国会図書館デジタルコレクション 030
天然痘にかかった義家は天延二年九月十六日
朝に亡くなった兄挙賢(たかかた)に続き夕に亡くなった。
世尊寺は京都一条の北、大宮の西にあった寺院
貞純親王の桃園邸の地に長保3年(1001年)藤原行成が建立した
藤原行成は義家の息子!! しからば こ、これは。。。
小倉百人一首 50番歌

『君がため 惜しからざりし 命さえ 長くもがなと 思ひけるかな』