2次障害をおった状態の生徒が高等部等へ入学した場合
<4月の出会い>
・「俺はやらない」「やすむ」「やめる」「いかない」と言う。
・机につっぷしている。あいさつをしない。無視。
・注意をすると険悪な空気になる。
・強く注意の後,家庭で学校にいかないと言う。
○学校,大人,先生に高い不信感をもってしまっている。
<原因は自己肯定感の低下>
・ほめられていない。
・分からないのに叱られ続ける。
○これまで叱られ続け,2次障害の状態になっている。
<誘った場合>
・「やろうよ」→「やらない」
・「食べよう」→「まずい」
・「行こうよ」→「俺,その日休む」
○反抗する言葉が悪い形で習慣化されている。
<自己肯定感を高めるには>
マイナスに働く対応
・説得をしようとすること。(行事の参加等)
・叱ること。(当番,掃除をやらない等)
・大声で怒ること。(態度の悪さ等)
プラスに働く対応
・できることを探しながら声をかける。(行事等)
・ほめること。(少しでもやれば)
・動揺しない。なぜかを話す。(態度面)
・笑顔(生徒の安定がまるで違う)
<必要な対応3つ>
1関係性の修復(人間関係を取り戻すこと)
2特性への対応(障害からくる特性を理解して適切な対応をすること)
3認知発達への対応(遅れた発達,知識量に応じて学習を進めること)
が必要となる。
なかでも優先しなければならないのは
「1関係性の修復」である。
関係性が修復されなければ,指導も支援も何も入らない。
関係性が修復されれば,素直になり,どんどん吸収が始まる。
関係性修復の達人である先輩は,
・グローブと軟球を教室に置き,キャッチボールから始まる。
・朝早く来て,たわいのない話をする。
そこから変化が生まれる。
3年後の就労。安定し,高評価を得ている。
<4月の出会い>
・「俺はやらない」「やすむ」「やめる」「いかない」と言う。
・机につっぷしている。あいさつをしない。無視。
・注意をすると険悪な空気になる。
・強く注意の後,家庭で学校にいかないと言う。
○学校,大人,先生に高い不信感をもってしまっている。
<原因は自己肯定感の低下>
・ほめられていない。
・分からないのに叱られ続ける。
○これまで叱られ続け,2次障害の状態になっている。
<誘った場合>
・「やろうよ」→「やらない」
・「食べよう」→「まずい」
・「行こうよ」→「俺,その日休む」
○反抗する言葉が悪い形で習慣化されている。
<自己肯定感を高めるには>
マイナスに働く対応
・説得をしようとすること。(行事の参加等)
・叱ること。(当番,掃除をやらない等)
・大声で怒ること。(態度の悪さ等)
プラスに働く対応
・できることを探しながら声をかける。(行事等)
・ほめること。(少しでもやれば)
・動揺しない。なぜかを話す。(態度面)
・笑顔(生徒の安定がまるで違う)
<必要な対応3つ>
1関係性の修復(人間関係を取り戻すこと)
2特性への対応(障害からくる特性を理解して適切な対応をすること)
3認知発達への対応(遅れた発達,知識量に応じて学習を進めること)
が必要となる。
なかでも優先しなければならないのは
「1関係性の修復」である。
関係性が修復されなければ,指導も支援も何も入らない。
関係性が修復されれば,素直になり,どんどん吸収が始まる。
関係性修復の達人である先輩は,
・グローブと軟球を教室に置き,キャッチボールから始まる。
・朝早く来て,たわいのない話をする。
そこから変化が生まれる。
3年後の就労。安定し,高評価を得ている。













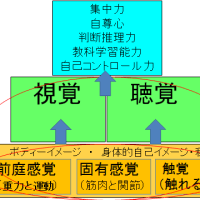






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます