一つ一つの行為に対して真剣に準備する
学年の始まり,最初の3日間は「黄金の3日間」と呼ばれる。その3日間のうちに学
級の組織作りをすることが,その1年間を決めるとも言われているためである。
これは,特別支援学校でも同様である。特別支援学校では緩やかな発達の中に子ど
も達の成長を見ていく。3日間はゆっくり過ごしがちであるが,そこで教師の気持ち
を伝え,学級の形や流れを見せていくことは,見通しを持ちづらい子ども達にとって
重要だからだ。
以下は小学部(小学生)の実践である。
1 前日までの準備
迎える備えはここから始まる。
① 名前テープ貼り
ビニールテープに書き,イス,タオルかけ,歯ブラシ賭け,ロッカー,下駄箱,雑
巾かけなどにつける。
② 児童名掲示
ラシャ紙いっぱいに6名の名前を書き,お花紙を飾って廊下に掲示。
③ スクールバス迎え担当きめ朝,どの子を誰が迎えるか決める
車椅子の児童,バスを降りるとすぐに走り出してしまう児童など,支援の体制をと
る。
④ 連絡帳・朝と帰りの会・給食介助の担当決め
⑤ 学年・クラス名簿作り
4月はじめの保健関係の提出物をチェックするために,早急に必要。
⑥ 児童のファイルチェック
児童のファイルをよく読む。児童の名前と顔を一致させるのは基本である。
⑦ 第1日目のシュミレーション
最初の出会いでなんと声をかけようか,また,1日どう過ごすか。自分なりに
目標を持つ。
2 第1日目
まずは「出会い」を印象付けたい。
そのために,
① 花を飾る
② 黒板にメッセージを書く
ということを行った。メッセージには,言葉「おはようございます。楽しい1年にし
よう!」・絵(笑っている先生の似顔絵)をかき,中央に昨年使っていた児童の名
前写真カードを並べた。
子ども達がスクールバスから降りてくる。笑顔で「おはよう」と声をかける。「おは
よう」と子どもが言ったら,すかさず,「すごいね。ちゃんとあいさつができるんだ
ね。さすが。」とほめる。
次に下駄箱を教える。「ここが新しい靴入れだよ。自分でちゃんと上履きに履き替
えられるかな。」と声をかけ,できたらすかさずほめちぎる。
一つ一つ子どもの動きを逃さず,声をかけていくことが,一緒にがんばっていこう
というメッセージにつながる。
3 第2日目
① クラスの目標を決める
子ども達に「クラスの目標は何がよいか」,とただ聞いてもなかなか出てこない。
素直に一人ひとり,「何をがんばりたいか」聞いて,つなげていき,全員の目標を作
る。「たいいく」「ずこう」と出たので,話し合う中で「走ったり,作ったり,一生
懸命がんばるクラス」となった。
② 係りを決める
知的障害のある子ども達にとって,「自分の役割を決める」ということはきわめて
重要である。自分の明確な役割を理解し,自分でできるようになることは,自立のま
ず第一歩となる。一人ひとりの実態に合わせた役割をみいだし,与えたい。
4 第3日目
3日目には楽しい授業を行いたい。このときにはまず音楽を行った。
① リズム運動
② 手遊び
③ ふれあい遊び
④ バルーン遊び
簡単にでき,友達同士のかかわりがあるものを重視した。
そして体育を行った。
① 去年のダンス
② 新しいダンス
③ 音楽に合わせて歩く,走る運動
去年のものを入れてすぐにでき,また,運動の基本となる歩く,走る力も見ていっ
た。
一つ一つの行為に対して,真剣に準備をし取り組むことで,子ども達も動き出し,
教師も意欲が高まった。最初の3日間を全力で取り組むこと,それが1年間の方向を決
めていく。
学年の始まり,最初の3日間は「黄金の3日間」と呼ばれる。その3日間のうちに学
級の組織作りをすることが,その1年間を決めるとも言われているためである。
これは,特別支援学校でも同様である。特別支援学校では緩やかな発達の中に子ど
も達の成長を見ていく。3日間はゆっくり過ごしがちであるが,そこで教師の気持ち
を伝え,学級の形や流れを見せていくことは,見通しを持ちづらい子ども達にとって
重要だからだ。
以下は小学部(小学生)の実践である。
1 前日までの準備
迎える備えはここから始まる。
① 名前テープ貼り
ビニールテープに書き,イス,タオルかけ,歯ブラシ賭け,ロッカー,下駄箱,雑
巾かけなどにつける。
② 児童名掲示
ラシャ紙いっぱいに6名の名前を書き,お花紙を飾って廊下に掲示。
③ スクールバス迎え担当きめ朝,どの子を誰が迎えるか決める
車椅子の児童,バスを降りるとすぐに走り出してしまう児童など,支援の体制をと
る。
④ 連絡帳・朝と帰りの会・給食介助の担当決め
⑤ 学年・クラス名簿作り
4月はじめの保健関係の提出物をチェックするために,早急に必要。
⑥ 児童のファイルチェック
児童のファイルをよく読む。児童の名前と顔を一致させるのは基本である。
⑦ 第1日目のシュミレーション
最初の出会いでなんと声をかけようか,また,1日どう過ごすか。自分なりに
目標を持つ。
2 第1日目
まずは「出会い」を印象付けたい。
そのために,
① 花を飾る
② 黒板にメッセージを書く
ということを行った。メッセージには,言葉「おはようございます。楽しい1年にし
よう!」・絵(笑っている先生の似顔絵)をかき,中央に昨年使っていた児童の名
前写真カードを並べた。
子ども達がスクールバスから降りてくる。笑顔で「おはよう」と声をかける。「おは
よう」と子どもが言ったら,すかさず,「すごいね。ちゃんとあいさつができるんだ
ね。さすが。」とほめる。
次に下駄箱を教える。「ここが新しい靴入れだよ。自分でちゃんと上履きに履き替
えられるかな。」と声をかけ,できたらすかさずほめちぎる。
一つ一つ子どもの動きを逃さず,声をかけていくことが,一緒にがんばっていこう
というメッセージにつながる。
3 第2日目
① クラスの目標を決める
子ども達に「クラスの目標は何がよいか」,とただ聞いてもなかなか出てこない。
素直に一人ひとり,「何をがんばりたいか」聞いて,つなげていき,全員の目標を作
る。「たいいく」「ずこう」と出たので,話し合う中で「走ったり,作ったり,一生
懸命がんばるクラス」となった。
② 係りを決める
知的障害のある子ども達にとって,「自分の役割を決める」ということはきわめて
重要である。自分の明確な役割を理解し,自分でできるようになることは,自立のま
ず第一歩となる。一人ひとりの実態に合わせた役割をみいだし,与えたい。
4 第3日目
3日目には楽しい授業を行いたい。このときにはまず音楽を行った。
① リズム運動
② 手遊び
③ ふれあい遊び
④ バルーン遊び
簡単にでき,友達同士のかかわりがあるものを重視した。
そして体育を行った。
① 去年のダンス
② 新しいダンス
③ 音楽に合わせて歩く,走る運動
去年のものを入れてすぐにでき,また,運動の基本となる歩く,走る力も見ていっ
た。
一つ一つの行為に対して,真剣に準備をし取り組むことで,子ども達も動き出し,
教師も意欲が高まった。最初の3日間を全力で取り組むこと,それが1年間の方向を決
めていく。













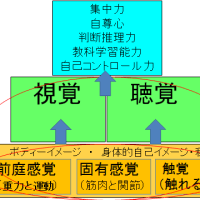






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます