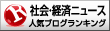平成16年11月27日付けで、「朝日選書「女性天皇論 象徴天皇制とニッポンの未来」について」という記事を書いたのだが、その時点の筆者の視野はかなり狭いものであり、十分な感想となっていなかったので、今回、改めて再読し、感想を書くことにする。
この本の特徴としては、皇室に関する様々な論点について、非常に網羅的であるということがある。
著者自身の価値観を前面に出すのではなく、様々な議論を、一見、女性天皇とは直接関係のないような議論についてまで、幅広く紹介するというスタイルになっている。
このことが、前回読んだときに、「つまらない」という感想を抱いてしまった原因であった。
ただ、その後、このブログにおけるコメント欄のやりとりにより、著者は、皇室というご存在について、非常に真っ正直に取り組もうとされている方であり、網羅的に議論を紹介するというのは、その正直さ故であるのだろうと、今にしてみれば、理解できるところである。
また、網羅的な議論の紹介においては、イデオロギー的な、固定観念に対する懐疑という視点があるように感じられたので、この点、筆者としては、伝統的な価値に対する相対主義であるというようにも、思い込んだ。
今にしてみれば、著者の真意は、おそらく、皇室の歴史というものをリアルに捉えようとする場合、固定観念というのは妨げになるということなのであろう。
固定観念にとらわれることなく、リアルに見つめ理解することが大切だという考えに立脚されているのだろう。
そして、その考えの背後には、非常に人間主義的な価値観があるように感じられた。
もっとも、このことは、著者によって、体系的、かつ、ストレートには語られていない。
それは、この本が、著者自身の謎解きの過程の記録であり、あるいは、正直なる弁明の書であって、読者を説得しようという意図によるものでないことに、由来しているのかもしれない。
そこで、何かを説得してもらうことを期待している受け身の読者にとって、物足りなさを感じるところがあるかもしれないが、既存の皇室をめぐる議論について何か欺瞞的なものを感じ、リアルに皇室というご存在を理解したいという積極的な読者にとっては、有益な書なのではないか。
以上が、筆者として、改めて再読した感想である。
なお、若干の指摘をさせていただくと、著者は、象徴天皇制とは何かということは、一種の神学論争であり、とりあえずは皇位継承の安定性に議論の的を絞るべきと主張する。
しかし、この本自体において、象徴天皇制について幅広く論じているところであり、内容紹介にても、「女性天皇を論じることは、パンドラの箱を開けることになる。天皇とは何か、天皇制とは何かという根元的な問題にぶつかる」とあり、読者もとまどってしまうのではないか。
この点については、象徴天皇制についての固定観念をめぐっての議論はあまり実益がないのだということが著者の真意であると推測しているが、そこまで読み取らなければいけないというのは、少々酷なのではなかろうか。
この本の特徴としては、皇室に関する様々な論点について、非常に網羅的であるということがある。
著者自身の価値観を前面に出すのではなく、様々な議論を、一見、女性天皇とは直接関係のないような議論についてまで、幅広く紹介するというスタイルになっている。
このことが、前回読んだときに、「つまらない」という感想を抱いてしまった原因であった。
ただ、その後、このブログにおけるコメント欄のやりとりにより、著者は、皇室というご存在について、非常に真っ正直に取り組もうとされている方であり、網羅的に議論を紹介するというのは、その正直さ故であるのだろうと、今にしてみれば、理解できるところである。
また、網羅的な議論の紹介においては、イデオロギー的な、固定観念に対する懐疑という視点があるように感じられたので、この点、筆者としては、伝統的な価値に対する相対主義であるというようにも、思い込んだ。
今にしてみれば、著者の真意は、おそらく、皇室の歴史というものをリアルに捉えようとする場合、固定観念というのは妨げになるということなのであろう。
固定観念にとらわれることなく、リアルに見つめ理解することが大切だという考えに立脚されているのだろう。
そして、その考えの背後には、非常に人間主義的な価値観があるように感じられた。
もっとも、このことは、著者によって、体系的、かつ、ストレートには語られていない。
それは、この本が、著者自身の謎解きの過程の記録であり、あるいは、正直なる弁明の書であって、読者を説得しようという意図によるものでないことに、由来しているのかもしれない。
そこで、何かを説得してもらうことを期待している受け身の読者にとって、物足りなさを感じるところがあるかもしれないが、既存の皇室をめぐる議論について何か欺瞞的なものを感じ、リアルに皇室というご存在を理解したいという積極的な読者にとっては、有益な書なのではないか。
以上が、筆者として、改めて再読した感想である。
なお、若干の指摘をさせていただくと、著者は、象徴天皇制とは何かということは、一種の神学論争であり、とりあえずは皇位継承の安定性に議論の的を絞るべきと主張する。
しかし、この本自体において、象徴天皇制について幅広く論じているところであり、内容紹介にても、「女性天皇を論じることは、パンドラの箱を開けることになる。天皇とは何か、天皇制とは何かという根元的な問題にぶつかる」とあり、読者もとまどってしまうのではないか。
この点については、象徴天皇制についての固定観念をめぐっての議論はあまり実益がないのだということが著者の真意であると推測しているが、そこまで読み取らなければいけないというのは、少々酷なのではなかろうか。