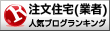「あげる」とは与えることであり、「もらう」とは受け取ることである。英語ではそれぞれ「give」と「take」になる。日本語では、「あげる」と「もらう」を動詞の下につけて、例えば「遊んであげる」とか「遊んでもらう」といった使い方をする。「遊んであげる」のは単に遊ぶのではない。遊ぶことが相手に対する恩恵の供与である、という意味合いがある。逆に「遊んでもらう」のは遊ぶという行為以上に恩恵を受ける、という気持ちを示している。いずれの場合も、遊んでいる当事者の関係が対等でないという意識が根底にある。
商売ではどうか。顧客との関係では、買ってもらうのだろうか、それとも売ってあげるのだろうか。あるいは、社長は従業員に対し、働いてもらうのだろうか、それとも働かせてあげるのだろうか。その言葉は微妙な心理の違いを表している。その心理は状況に応じて変わるから、不景気で物が売れず、仕事が少ないときは、買ってもらい、働かせてあげる感じが強まる反面、逆の場合には、売ってあげ、働いてもらう意識が強まる傾向がある。
私たちは、あげるのかもらうのか、それを使い分けながら仕事をすることが多い。相手の年齢や社会的地位への配慮が敬語という形で表現されるとすれば、あげるともらうは、利害損得を意識した表現である。その背後にあるのは計算だ。より多く得ていると感じるときには、もらうとなり、より多く与えていると思うときには、あげるとなる。顧客や従業員に対して感謝の気持ちが強い社長の場合、買ってもらう、働いてもらうという意識になりがちだ。もちろんそれで間違いはない。しかしそれだけでいいのかどうか。
あげるともらうという言葉は、当該行為が等価交換ではないという心理を表している。しかしもし適正な価格が付与されていれば、顧客は商品・サービスの購入で十分な満足を得、反面売り手は必要な収入を得る。どちらかがより多く恩恵を受けることはなくて、顧客と売り手は対等だ。同様に社長と従業員の関係も、適正な給与が支給されていれば、どちらかがより多く恩恵を受けることはないという意味で対等だ。逆に言えば、価格・給与にふさわしい品質、職場環境が必要だ。
感謝の気持ちは忘れるべきではない。しかしあげるともらうという言葉を多用しない経営を心がけてみよう。恩着せがましくもないし、卑屈にもならない凛とした姿勢が生まれるはずである。
平成20年6月2日発行 ㈱ちばぎん総合研究所
「あげる」と「もらう」、たった3文字の言葉だけど意味が深いですね。腰の低い私は、もらうという意識が強いです。社長として間違いではないと言っておりますが・・。
お客様との関係は、やはり建てさせてもらうという気持ちが強いです。価格にあった建物・サービスを提供し、必要な収入を得る。この必要な収入を得るのがなかなか難しいんですよね。より良いものを提案したいし、物価は上がる、しかし、お客様の予算は決まっている・・・。だからといって、職人の手間を下げればよい商品が出来ない。手間を下げたからと言って、手をぬく職人はいないと解ってはいるのですが、それが出来ないのは元職人だったからですかね。
お客様、従業員、職人、そして家族、私に係わる全員が、満足する建物に住んで、満足できる仕事・収入を得られる、経営を目指して、感謝の気持ちを忘れずに、これからも『dd-cube』 「design cube / dream cube」を造り上げていきます。
基礎工事完了

土台敷き

5月28日 上棟

雨も降らずに無事上棟が終りました。Y様おめでとうございます。
毎日、大工さんによって夢が築かれて行きますので、見に行ける時は是非よって
下さい。そして、疑問に思ったことは何でも聞いて下さい。家主となるのですから
中身を知って住んで頂きたいのです。中身を知らないで家主と言えるのでしょうか。
仕上りだけを見て「良い家ですね」とは言えないはづです。
10時か15時のお茶の時間に行って、一緒にお茶をしながら色々大工さんに質問して
下さい。たとえば「この金物は何の為に付いてるの?」 「この木は何という木?」
「どうしてこんな所に木を付けるの?」など色々聞いて下さい。
次回打合せよろしくお願い致します。