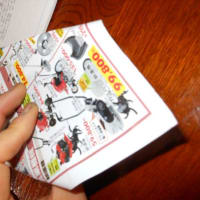この世の儚さを謳いあげたような立原道造氏ですが、私が彼の詩を読んで思い出すのがこの真幸駅です。

昔は、駅のある場所というのは人も集まり繁栄したものですが、今では自動車の普及に伴い東京のような大都市でないとその効果もなくなってきました。
これも常に移り変わる時代の流れで、良い悪いの二元論の判断では出来ないのですが、こういった一昔前の繁栄の面影をみるといつも立原道造氏の詩が思い出されます。 あと、箱根とかの廃屋をみた時も氏の詩を思い出しましたね。
真の幸せ、真幸は意志堅固な18画。 十八画の数意はと言いますと、
【十八画】:強固な意志をもち、権威と共に知力・才謀を具有し、ひとたび志を立てれば万難を排して進み、遂には成功し名誉と利益を収めることがあるが、しかし、他面に於て、自我心が強いため、狭量で抱擁力が乏しく、非難を蒙って、種々の障碍に出くわすことがありがちで、そのため頓挫することがある。 相当の年配になって、自らを戒めて柔軟であることを心掛け、目的を貫徹し成功している人があるが、それは本人に十六の吉数があるか、配偶者に吉数が働いているかする場合が多い。
となっております。

“真の幸せ=真幸” に向う道は、人それぞれで未知(道)であり、18画の数意にあるように、基本としてはその人が打ち立てた理想(IDEAL)に向って意志強固に進まなくてはならないが、しかし、わき目もふらずそちらに向い過ぎると今度は頑固な面が出がて凶となり、意志強固に進みつつも柔軟に周りの状況も汲み取る俯瞰的な視点も必要とされるのかも知れません。
下に、私のいちばんのお気に入りの “のちのおもひに” と写真をアップしておきたいと思います。 重くなるといけないのでリンクつきで貼り付けておきます。
【のちのおもひに】
夢はいつもかへつて行つた 山の麓のさびしい村に
水引草に風が立ち
草ひばりのうたひやまない
しづまりかへつた午さがりの林道を
うららかに青い空には陽がてり 火山は眠つてゐた
――そして私は
見て來たものを 島々を 波を 岬を 日光月光を
だれもきいてゐないと知りながら 語りつづけた……
夢は そのさきには もうゆかない
なにもかも 忘れ果てようとおもひ
忘れつくしたことさへ 忘れてしまつたときには
夢は 真冬の追憶のうちに凍るであらう
せきれう
そして それは戸をあけて 寂寥のなかに
星くづにてらされた道を過ぎ去るであらう