
満年齢・・・生れた時は0歳
誕生日が来るごとに1歳年を重ねる
数え年・・・生れた時は1歳
毎年1月1日で1歳年を重ねる
この差が満年齢と数え年の根本ですね。
この数え年の決まりに従うと、12月31日生まれの赤ちゃんは次の日の1月1日で2歳になるわけです。
少し驚きですが、これはこれでそういうことです。(?)
数え年は、母親の胎内で命を授かった時が0歳という仏教に由来する考え方です。
確かにその時すでに命はありますからね。
厄年は一般的に数え年の計算で決まりますが、満年齢で当てはめる神社やお寺もあります。
厄年そのものの定義や由来がはっきりしないので、こういうことになりますが、厄払いに行くときは確かめておいた方がいいですね。
せっかく厄年の厄払いをしてもらおうと訪ねても、年齢が当てはまらず厄払いを受けられないことになりかねませんから。
厄払いは立春までぐらいでひとつの目途とする時期です。
弘法大師(空海)を開祖とする真言宗の3つの寺が、厄除け三大師と呼ばれています。
千葉県の観福寺には日本厄除三大師の看板があります。
他の二つは神奈川県の川崎大師と東京の西新井大師。
⇒OFFICE SOME
川崎大師では厄年を満年齢で使っています。
⇒川崎大師
千葉県の観福寺と西新井大師では数え年で厄年を決めています。
⇒妙光山 観福寺
厄年というのは、陰陽道に由来し、古くから日本に伝わる風習ですが、仕事や病気、結婚、出産など大きな枠でそれなりの人生の節目に当たる年に合致することが多いですね。
人間ドッグを進められる年齢を見ると、女性は30代男性は40代が一般的です。
厄年もそうなっていますね。
単なる迷信だと思わず、人生の流れが変わる節目に違いないのですから、やはり尊重してもいように思えます。
(厄という漢字は、木の節という意味があります)
前厄は、本厄の前兆で、これから本厄に入っていきますよ言っているわけです(まったくその通りですね)
本厄が最も悪い年とされていますが、本厄の最重要注意事項が「健康」であるのに対して前厄は「お金」とされています。
後厄は、厄が徐々に薄れていく年ですが、ここで気をつけなければならないことは「油断」することです。
油断大敵というやつです。
また厄年でないから大丈夫ということもありませんね。
本当に人生って何がいつ起こるかわかりませんから、神頼みした後も常に気を付けるに越したことはないと思います。
ただ、気を付けていても起こることは起こるし、ずっと気にして毎日過ごすのもやや気が重いですね。
心のどこかで「あとは野となれ山となれ」といった開き直りが必要かもしれません。










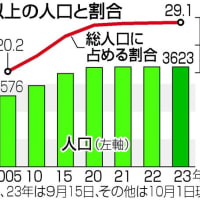
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます