自動ドアはいつも開け放たれていた。荻窪駅を下車しいくばくかも歩かぬところにその古書店は在していた。家路につく為にその前を通る人達は目を配ることはするのだが、中に入ることはなく通り過ぎてゆく。
外に突き出されたスチールの白い棚にはすっかり風化がすすんでいる文庫達が所狭しと並べられていた。背表紙を見て回る限りにそれほど年代の古い感じはない。売れ残ってどうしようもなくなった数々の古書が、日々風や陽にさらされていた。
中川は高校からの帰り道にその古書店へと立ち寄るのを日課にしていた。といっても店内には入らずもっぱら棚に並ぶ文庫本の背表紙を見て回るのだ。サッカー部を2年生の秋に辞めたことで、できてしまった途方もない無意味な時間に苦しめられていた。3年生の新学期も始まったというのにその心模様は曇天そのものであり、大学の付属高校の詰襟の制服の内で冷たくくすぶっていた。
伝統や気高さの裏返しである冷たい雰囲気の校舎にその日の終了のチャイムが響く。生徒達は皆ぞろぞろと席を立ち教室から何処かへと消えて行った。
中川は池袋のサンシャイシティーで取り残された子供のように所在無い感情を抱いた。座席の硬さをでん部に感じながらただその様子を見送っていた。
中央線に乗り換え、急行で荻窪駅へと急ぐ。付属高校の上の大学は世間でもあまりなの知られていないものであり、級友のほとんどは、他大学への受験を控え勉学に励んでいた。いわゆる落ちこぼれである中川は、他大学への受験という苛烈極まる競争に恐れを感じていた。
がらんとした車内には背広のサラリーマンはいなかった。幼児を抱えて銀の手摺りにもたれかかって座っている女性は疲れているように見えた。恐らく自分は無業者になるなと中川は思った。
白いスチール棚でほこりをかぶってしまっている文庫はこの前と全く同じ配列で並んでいた。棚の上部には、太字のサインペンで3冊 100円と書かれたダンボールの切れはしが付けてあった。
家に帰ると制服を脱ぎベージュのチノパンを履きライムグリーンのトレーナーを着て図書館へと自転車に乗り向かった。散った桜の花びらの上を滑走して坂を登りきると図書館に着いた。
自習ルームで天文学に関するハードカバーの本を読んでいたが曇天の胸の内は重く沈んだままであった。
トイレに立ち寄り引き返す道すがら水飲み機のボタンを押して放物線を描くカルキの多い水で口を湿らせた。天文学の本などに微塵もの興味も中川にとってはなかったのだかこうして難解そうなものを読んで自分が図書館の自習ルームという幾ばくかの知的空間の風景の一部としていられることが学校では無意味な存在にすぎない自己の存在を証明する為の唯一の方策だった。
下の書庫へ行き中川は天文学の本を戻そうと棚の乱立する狭い通路をウロウロしていた。量子力学と分子生物学の棚の下の段に中川が持っている本に割り振られている番号と一致する背表紙がずらっと並んでいたので少し腰を落とし本をそこにしまった。
屈伸したように曲がった身体を直立させながら後ろを振り返った。何かとぶつかり図書館のカーペットの床に尻もちをついた。甘い匂いがしていた。
目の前には自分と同じように座している決して派手ではない女性がいた。
「すいません」と中川は言った。
「いやこちらこそすいません」と女性は言った。履いているパンプスは自力で立ち上がるのには難しいことを示しているように思えたので、中川はまず自分が起き上がると女性もそう出来るようにと背中と腕を支えた。女性はなんとか立ち上があがる事ができた。
「ありがとう」と言いと麗しき笑みを浮かべると女性はハンカチを差し出した。どうやら中川は鼻血を出していたらしい。
「すいません」と言って鼻血を拭いしばらく女性に見とれていた。
「それじゃあ」と女性は去ろうとしたので、中川は
「このハンカチはどうすれば?」と半ば焦り気味に尋ねた。
女性は振り返ると、
「あなたにあげるわ」と言って図書館からいなくなってしまった。
薄く血の滲むピンクと青のグラデーションのハンカチを持ち書棚の通路に立ち尽くしていた。
中川は家に帰ると母親にハンカチを洗濯してくれるように頼んだ。
「何処から持ってきたのこのハンカチは?」と聞く母親に中川は、
「3年に進級したクラスは担任が英語の女性教諭で鼻血をホームルームの出してしまい貸してくれたのだ」と言った。
坂野は焼きたて直達便シリーズのデニッシュを食べながら、バックヤードで休憩をとっていた。友達の葉子からメールがきていた事に気付いて携帯を開く。他愛もないやり取りに熱中し終わると、洗面所で手を洗いいつもジーパンの後ろポケットに入れてあるハンカチで手を拭おうとしたが無かった。そういえば昨日、いつも行かないのに図書館に寄って館内をうろついていたらぶつかってしまいずっこけて鼻血を出した少年にあげてしまったのだった。
レジから呼び出し音が鳴って坂野は手をジーパンの太ももの部位にこすりつけ水滴を減らすと、ドアを開けて
「いらっしゃいませー」と言いながら
休止中のつい立てのある奥のレジに入り、オレンジのカゴをもって並んでいる客たちに、
「2番目にお並びのお客様どうぞ」と言いつい立てを台の下のスペースへとしまった。右隣りではフリーター4年目のベテランアルバイターがせわしなくバーコードリーダーに商品をかざしていた。台の上にカゴを無造作に乗せると男は、携帯を弄りながらそっぽを向いていた。素早く商品をレジに読み込ませて「1230円になります」とまだ新しい薄い紺色のスーツを着た20代くらいの髪をジェルで逆立てている男に言った。男は携帯を打つ手を止めポケットからすこしヨレた千円札2枚を釣銭トレーに置いた。「770円のお返しになります」と言って坂野は男の手に釣銭を渡した。ベテランアルバイターの素早い客さばきにより客の渋滞という難を逃れる事が出来たようだ。
「坂野さんまだ休憩中でしたよね」と銀フチの眼鏡を掛けたベテランアルバイターは言った。
「では戻ります」とだけ言うと、坂野はそそくさとバックヤードに引き返した。
金曜日の17時までのシフトを終えると帰宅した。
次の日、足は自然と図書館へと向かっていた。
中川にとってその日のホームルームは酷く落ち着かないものであった。担任の話しも上の空である。金曜日の終了のチャイムが鳴ると堰を切ったかのようにクラスメイトたちは外へと駆け出して行った。中川はしばらく待ち教室を出て賑わう帰りの通学路を1人歩いた。帰宅してハンカチが乾いていることを確認すると、夕食を食べてしばしゲームをすると眠りについた。
土曜日になっていた。正午に目を覚まして、髪を軽く整えてブルーのチェックのネルシャツに白のチノパンというあまりひねりのないスタイルで図書館へと自転車に乗って出掛けた。
図書館に入ると、この前通路でぶつかってしまった女性が雑誌コーナーのソファーでノンノを読み座っていた。中川は女性に近付くとハンカチを差し出して、
「この前はぶつかってしまいすいませんでしたハンカチ洗ったので返します」と言った。
女性は、
「気にしなくていいのそんなことより少し話しでもしない?」と言ってソファーに中川が座るスペースを開けてくれた。
中川はそこに座すと、
「あの、名前はなんというのですか?」と顔と声を引きつらせながら聞いた。
「坂野って言うんだ」と女性は言った。
「坂野さん、ぼく 中川って言います」と言い体を強張らせると、
「中川君ね。わかった」と言って雑誌をまた読み出す女性の横で中川は小さくなっていた。
立ち上がると中川は、「また来週この図書館で会えますか?」と聞いた。
女性は笑顔で頷きまた雑誌を読み出した。
図書館から出て風をきりながら自転車を漕ぎ、散る桜の花びらの上を滑走して行き、駅前の古書店に着いた。
中川はスチールの白い棚を通り過ぎると開け放たれた自動ドアの入口から店内へと足を踏み入れた。その古書店の中へと入ったのは中川にとって初めての事だった。そして図書館から古書店へ自転車を滑走させた事により額に滲んでいた汗をピンクと青色のグラデーションのハンカチで拭いた。
外に突き出されたスチールの白い棚にはすっかり風化がすすんでいる文庫達が所狭しと並べられていた。背表紙を見て回る限りにそれほど年代の古い感じはない。売れ残ってどうしようもなくなった数々の古書が、日々風や陽にさらされていた。
中川は高校からの帰り道にその古書店へと立ち寄るのを日課にしていた。といっても店内には入らずもっぱら棚に並ぶ文庫本の背表紙を見て回るのだ。サッカー部を2年生の秋に辞めたことで、できてしまった途方もない無意味な時間に苦しめられていた。3年生の新学期も始まったというのにその心模様は曇天そのものであり、大学の付属高校の詰襟の制服の内で冷たくくすぶっていた。
伝統や気高さの裏返しである冷たい雰囲気の校舎にその日の終了のチャイムが響く。生徒達は皆ぞろぞろと席を立ち教室から何処かへと消えて行った。
中川は池袋のサンシャイシティーで取り残された子供のように所在無い感情を抱いた。座席の硬さをでん部に感じながらただその様子を見送っていた。
中央線に乗り換え、急行で荻窪駅へと急ぐ。付属高校の上の大学は世間でもあまりなの知られていないものであり、級友のほとんどは、他大学への受験を控え勉学に励んでいた。いわゆる落ちこぼれである中川は、他大学への受験という苛烈極まる競争に恐れを感じていた。
がらんとした車内には背広のサラリーマンはいなかった。幼児を抱えて銀の手摺りにもたれかかって座っている女性は疲れているように見えた。恐らく自分は無業者になるなと中川は思った。
白いスチール棚でほこりをかぶってしまっている文庫はこの前と全く同じ配列で並んでいた。棚の上部には、太字のサインペンで3冊 100円と書かれたダンボールの切れはしが付けてあった。
家に帰ると制服を脱ぎベージュのチノパンを履きライムグリーンのトレーナーを着て図書館へと自転車に乗り向かった。散った桜の花びらの上を滑走して坂を登りきると図書館に着いた。
自習ルームで天文学に関するハードカバーの本を読んでいたが曇天の胸の内は重く沈んだままであった。
トイレに立ち寄り引き返す道すがら水飲み機のボタンを押して放物線を描くカルキの多い水で口を湿らせた。天文学の本などに微塵もの興味も中川にとってはなかったのだかこうして難解そうなものを読んで自分が図書館の自習ルームという幾ばくかの知的空間の風景の一部としていられることが学校では無意味な存在にすぎない自己の存在を証明する為の唯一の方策だった。
下の書庫へ行き中川は天文学の本を戻そうと棚の乱立する狭い通路をウロウロしていた。量子力学と分子生物学の棚の下の段に中川が持っている本に割り振られている番号と一致する背表紙がずらっと並んでいたので少し腰を落とし本をそこにしまった。
屈伸したように曲がった身体を直立させながら後ろを振り返った。何かとぶつかり図書館のカーペットの床に尻もちをついた。甘い匂いがしていた。
目の前には自分と同じように座している決して派手ではない女性がいた。
「すいません」と中川は言った。
「いやこちらこそすいません」と女性は言った。履いているパンプスは自力で立ち上がるのには難しいことを示しているように思えたので、中川はまず自分が起き上がると女性もそう出来るようにと背中と腕を支えた。女性はなんとか立ち上があがる事ができた。
「ありがとう」と言いと麗しき笑みを浮かべると女性はハンカチを差し出した。どうやら中川は鼻血を出していたらしい。
「すいません」と言って鼻血を拭いしばらく女性に見とれていた。
「それじゃあ」と女性は去ろうとしたので、中川は
「このハンカチはどうすれば?」と半ば焦り気味に尋ねた。
女性は振り返ると、
「あなたにあげるわ」と言って図書館からいなくなってしまった。
薄く血の滲むピンクと青のグラデーションのハンカチを持ち書棚の通路に立ち尽くしていた。
中川は家に帰ると母親にハンカチを洗濯してくれるように頼んだ。
「何処から持ってきたのこのハンカチは?」と聞く母親に中川は、
「3年に進級したクラスは担任が英語の女性教諭で鼻血をホームルームの出してしまい貸してくれたのだ」と言った。
坂野は焼きたて直達便シリーズのデニッシュを食べながら、バックヤードで休憩をとっていた。友達の葉子からメールがきていた事に気付いて携帯を開く。他愛もないやり取りに熱中し終わると、洗面所で手を洗いいつもジーパンの後ろポケットに入れてあるハンカチで手を拭おうとしたが無かった。そういえば昨日、いつも行かないのに図書館に寄って館内をうろついていたらぶつかってしまいずっこけて鼻血を出した少年にあげてしまったのだった。
レジから呼び出し音が鳴って坂野は手をジーパンの太ももの部位にこすりつけ水滴を減らすと、ドアを開けて
「いらっしゃいませー」と言いながら
休止中のつい立てのある奥のレジに入り、オレンジのカゴをもって並んでいる客たちに、
「2番目にお並びのお客様どうぞ」と言いつい立てを台の下のスペースへとしまった。右隣りではフリーター4年目のベテランアルバイターがせわしなくバーコードリーダーに商品をかざしていた。台の上にカゴを無造作に乗せると男は、携帯を弄りながらそっぽを向いていた。素早く商品をレジに読み込ませて「1230円になります」とまだ新しい薄い紺色のスーツを着た20代くらいの髪をジェルで逆立てている男に言った。男は携帯を打つ手を止めポケットからすこしヨレた千円札2枚を釣銭トレーに置いた。「770円のお返しになります」と言って坂野は男の手に釣銭を渡した。ベテランアルバイターの素早い客さばきにより客の渋滞という難を逃れる事が出来たようだ。
「坂野さんまだ休憩中でしたよね」と銀フチの眼鏡を掛けたベテランアルバイターは言った。
「では戻ります」とだけ言うと、坂野はそそくさとバックヤードに引き返した。
金曜日の17時までのシフトを終えると帰宅した。
次の日、足は自然と図書館へと向かっていた。
中川にとってその日のホームルームは酷く落ち着かないものであった。担任の話しも上の空である。金曜日の終了のチャイムが鳴ると堰を切ったかのようにクラスメイトたちは外へと駆け出して行った。中川はしばらく待ち教室を出て賑わう帰りの通学路を1人歩いた。帰宅してハンカチが乾いていることを確認すると、夕食を食べてしばしゲームをすると眠りについた。
土曜日になっていた。正午に目を覚まして、髪を軽く整えてブルーのチェックのネルシャツに白のチノパンというあまりひねりのないスタイルで図書館へと自転車に乗って出掛けた。
図書館に入ると、この前通路でぶつかってしまった女性が雑誌コーナーのソファーでノンノを読み座っていた。中川は女性に近付くとハンカチを差し出して、
「この前はぶつかってしまいすいませんでしたハンカチ洗ったので返します」と言った。
女性は、
「気にしなくていいのそんなことより少し話しでもしない?」と言ってソファーに中川が座るスペースを開けてくれた。
中川はそこに座すと、
「あの、名前はなんというのですか?」と顔と声を引きつらせながら聞いた。
「坂野って言うんだ」と女性は言った。
「坂野さん、ぼく 中川って言います」と言い体を強張らせると、
「中川君ね。わかった」と言って雑誌をまた読み出す女性の横で中川は小さくなっていた。
立ち上がると中川は、「また来週この図書館で会えますか?」と聞いた。
女性は笑顔で頷きまた雑誌を読み出した。
図書館から出て風をきりながら自転車を漕ぎ、散る桜の花びらの上を滑走して行き、駅前の古書店に着いた。
中川はスチールの白い棚を通り過ぎると開け放たれた自動ドアの入口から店内へと足を踏み入れた。その古書店の中へと入ったのは中川にとって初めての事だった。そして図書館から古書店へ自転車を滑走させた事により額に滲んでいた汗をピンクと青色のグラデーションのハンカチで拭いた。














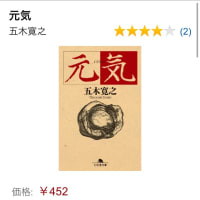




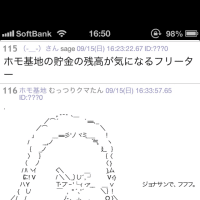





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます