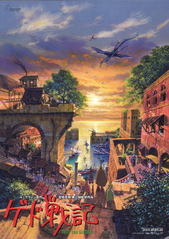1996年 イギリス映画
この映画、本当に好きで何度も何度も観てます。好きすぎて、感想を書くのが本当に難しい。
1992年。舞台はイングランド北部のヨークシャー州リムリー。100年の歴史を誇る炭鉱夫たちの名門ブラスバンド「グリムリー・コリアリー・バンド」も、炭鉱閉鎖の問題に頭を抱えていた。炭鉱閉鎖、生活苦、失業。全英選手権出場権を手に入れたが、出場するための資金が無い。さらに炭鉱閉鎖が決定される。そこでメンバーは解散を決意するが・・・。
90年代のイギリスの不況、特に炭鉱閉鎖によるあおりを受けた市民生活をテーマにした映画、何本かありますよね。『フルモンティー』や『リトル・ダンサー』(どちらも大好きな映画です)もそう。この『ブラス!』はその中でも、炭鉱閉鎖によって苦境に立たされた人々を真正面から捉えています。観ていて胸が苦しくなるほど。私の父は九州出身で、炭鉱の閉鎖を実際に見ているだけだけに、この映画は見ていて辛くなる、と言います。
とにかく俳優たちの演技がすばらしいんです。それぞれの登場人物たちの状況がきちんと丁寧に描かれていて、すぐに引き込まれます。
特に印象に残っているのが、バンドの指揮者であるダニーを演じたピート・ポスルスウェイト。ピート・ポスルスウェイトは、さすがアカデミー賞ノミネート経験者。数々のヒット作に出ている俳優ですが、この作品の演技も圧巻です。本当に引き込まれてしまうんです。彼が演じるダニーという人物が本当に魅力的で、ブラスバンドを心から愛し、彼の中にある情熱や怒り、悲しみが見事なまでに表現されています。彼のスピーチ、最高です。実話を基にした映画ですが、このスピーチは実際のものなのかしら。もしそうだとしたら、鳥肌ものです。映画のための台詞だったとしたら、良くぞこんな名台詞と生み出した!と脚本家に拍手を送りたいくらい。
そしてもう一人。ダニーの息子のフィルを演じたスティーヴン・トンプキンソン。この人、私はこの映画以外では見たことありませんが、この映画の中の彼はもう圧倒的です。演技だともちろんわかっていますが、これほどまでに本物の、もしかしたら本物以上の「涙」を流す俳優を見たことがありません。たくさんの複雑な感情が一気に押し寄せてきた涙を、見事に表現しています。映画にはたくさんの感動的な場面がありますが、この映画の中で一番印象に残ったシーンは?、と言われたら、私は迷わず「フィルの流した涙」と答えることができるくらい。
フィルの奥さんが買い物でお金が足りなかった時に、「がんばって」と握手を差し出したレジ係の手には彼女に渡すための紙幣が。誰もが苦しんでいる時代。それを象徴したワンシーンだと思います。
ダニーの入院先の病院の庭で、「ダニーボーイ」(選曲もニクイ!)を演奏するブラスバンドの姿。
少しでも小銭を稼ごうと、ピエロになって誕生会に呼ばれたフィルが人生の屈辱を子供相手に罵るシーン。
本当に観ているのが辛くなる。目を逸らしたくなるのではなく、胸に迫ってくる。だからといって「泣かせよう」としていないのがいい。「ここで泣いてね」という感動ポイントを作りこまないところが、私はイギリス映画のいいところだと思います。さらに、細かいことろにちょっと笑いを入れてあるところ。このさじ加減が最高。ロイヤル・アルバート・ホールで、ほかの出演者たちの演奏中は全く聴く耳持たず、編み物を始める主婦たち。夫たちの晴れ舞台を観にロンドンまで来たはいいけど、別に音楽やブラスバンドに興味があるわけではない、というこの姿勢!編み物持参って、始めから編む気満々だし。別にこういうシーンが無くても映画は成立するのだけど、あえてこういう部分を入れてくるイギリス映画の「遊び」部分が、私は好きでたまりません。
演技者が物語りの中に漂う悲壮感を、映画全体としてだけではなく、一人ひとりがかもし出し表現しているその演技力の高さ。ため息が出ます。楽しめる娯楽として映画を見たい人には向かないと思いますが、私の中では「必見」といえる一本です。
おすすめ度:☆☆☆☆☆+α
この映画、本当に好きで何度も何度も観てます。好きすぎて、感想を書くのが本当に難しい。
1992年。舞台はイングランド北部のヨークシャー州リムリー。100年の歴史を誇る炭鉱夫たちの名門ブラスバンド「グリムリー・コリアリー・バンド」も、炭鉱閉鎖の問題に頭を抱えていた。炭鉱閉鎖、生活苦、失業。全英選手権出場権を手に入れたが、出場するための資金が無い。さらに炭鉱閉鎖が決定される。そこでメンバーは解散を決意するが・・・。
90年代のイギリスの不況、特に炭鉱閉鎖によるあおりを受けた市民生活をテーマにした映画、何本かありますよね。『フルモンティー』や『リトル・ダンサー』(どちらも大好きな映画です)もそう。この『ブラス!』はその中でも、炭鉱閉鎖によって苦境に立たされた人々を真正面から捉えています。観ていて胸が苦しくなるほど。私の父は九州出身で、炭鉱の閉鎖を実際に見ているだけだけに、この映画は見ていて辛くなる、と言います。
とにかく俳優たちの演技がすばらしいんです。それぞれの登場人物たちの状況がきちんと丁寧に描かれていて、すぐに引き込まれます。
特に印象に残っているのが、バンドの指揮者であるダニーを演じたピート・ポスルスウェイト。ピート・ポスルスウェイトは、さすがアカデミー賞ノミネート経験者。数々のヒット作に出ている俳優ですが、この作品の演技も圧巻です。本当に引き込まれてしまうんです。彼が演じるダニーという人物が本当に魅力的で、ブラスバンドを心から愛し、彼の中にある情熱や怒り、悲しみが見事なまでに表現されています。彼のスピーチ、最高です。実話を基にした映画ですが、このスピーチは実際のものなのかしら。もしそうだとしたら、鳥肌ものです。映画のための台詞だったとしたら、良くぞこんな名台詞と生み出した!と脚本家に拍手を送りたいくらい。
そしてもう一人。ダニーの息子のフィルを演じたスティーヴン・トンプキンソン。この人、私はこの映画以外では見たことありませんが、この映画の中の彼はもう圧倒的です。演技だともちろんわかっていますが、これほどまでに本物の、もしかしたら本物以上の「涙」を流す俳優を見たことがありません。たくさんの複雑な感情が一気に押し寄せてきた涙を、見事に表現しています。映画にはたくさんの感動的な場面がありますが、この映画の中で一番印象に残ったシーンは?、と言われたら、私は迷わず「フィルの流した涙」と答えることができるくらい。
フィルの奥さんが買い物でお金が足りなかった時に、「がんばって」と握手を差し出したレジ係の手には彼女に渡すための紙幣が。誰もが苦しんでいる時代。それを象徴したワンシーンだと思います。
ダニーの入院先の病院の庭で、「ダニーボーイ」(選曲もニクイ!)を演奏するブラスバンドの姿。
少しでも小銭を稼ごうと、ピエロになって誕生会に呼ばれたフィルが人生の屈辱を子供相手に罵るシーン。
本当に観ているのが辛くなる。目を逸らしたくなるのではなく、胸に迫ってくる。だからといって「泣かせよう」としていないのがいい。「ここで泣いてね」という感動ポイントを作りこまないところが、私はイギリス映画のいいところだと思います。さらに、細かいことろにちょっと笑いを入れてあるところ。このさじ加減が最高。ロイヤル・アルバート・ホールで、ほかの出演者たちの演奏中は全く聴く耳持たず、編み物を始める主婦たち。夫たちの晴れ舞台を観にロンドンまで来たはいいけど、別に音楽やブラスバンドに興味があるわけではない、というこの姿勢!編み物持参って、始めから編む気満々だし。別にこういうシーンが無くても映画は成立するのだけど、あえてこういう部分を入れてくるイギリス映画の「遊び」部分が、私は好きでたまりません。
演技者が物語りの中に漂う悲壮感を、映画全体としてだけではなく、一人ひとりがかもし出し表現しているその演技力の高さ。ため息が出ます。楽しめる娯楽として映画を見たい人には向かないと思いますが、私の中では「必見」といえる一本です。
おすすめ度:☆☆☆☆☆+α