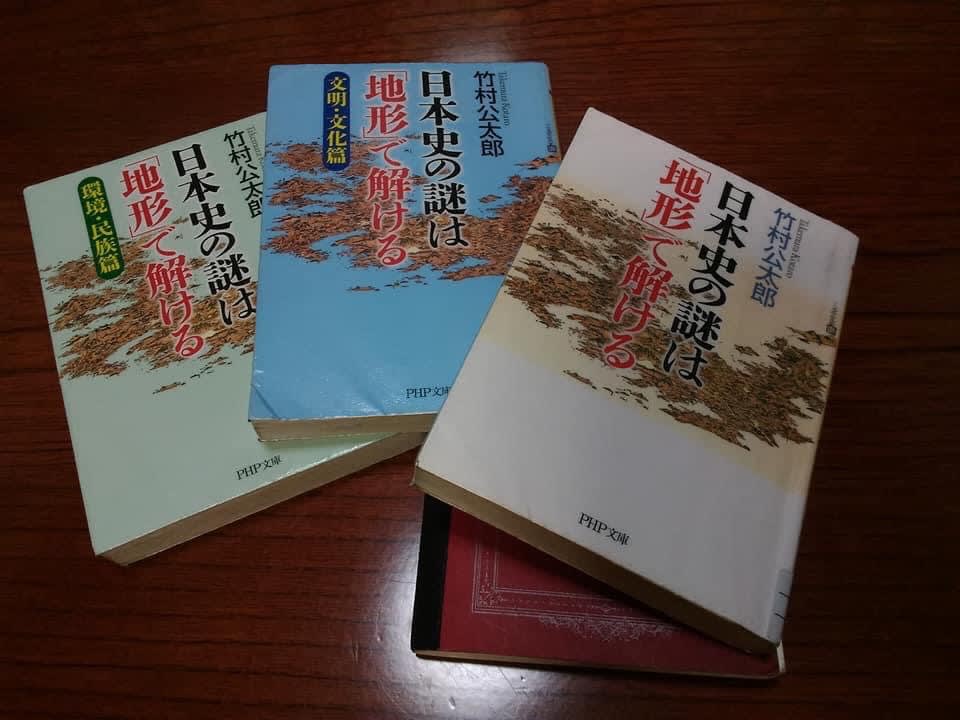
#竹村公太郎 #日本史の謎は地形で解ける 1巻、2巻文明・文化篇
おもしろい!
学生だったら夏休みの宿題にまるまるパクリたいぐらいです(笑)
飲み友達の先輩に教えてもらった本。更に奇遇なことには竹村公太郎さんは
僕の母校の、その上お隣の土木工学科卒業の大先輩だと!
今日の暑さにピッタリ納得する著述があった。
第14章 なぜ日本の国旗は太陽の図柄になったか
熱帯の太陽の下での激しい動作や長時間労働は極めて危険で、倒れたりすれば死に至る。昼間の労働は健康を損なう行為なのだ。昼間は注意深く必用最小限の動作だけをしなくてはならない。--
日本には3.4か月の長い冬がある、半年間という限られた中で1年分の食糧を生産し蓄積する必要があった、日本人は勤勉にならざるを得なかった。
昼の太陽の下で働き、夜の闇の中で眠り疲れを癒す。
いつも太陽の下で活動し続けた。日本伝統文化はすべて太陽の下で生まれ育っていった。
太陽の下で働くことは、日本人にとって生きている証、健康の証、生きる喜びであった。
このように熱帯の人々と温帯の人々は昼間の労働に関して正反対の思いを持つに至った。危険で苦役な熱帯の労働と、健康で喜びの温帯の労働である。
この違いは文明の成熟と富の蓄積の競争の優越を決定づけた。苦役の労働と喜びの労働が競争すれば喜びの労働が勝るに決まっている。どの分野でも楽しむ人が勝つ。楽しむ人が努力を継続し忍耐と持続性を保っていく。近代産業革命以来、温帯の人々が世界を席巻したのは必然だった。イギリス、フランス、ドイツ、北米、そして日本。これらの国々において勤勉は生きるための必要条件であり常に善であった。
うむ なるほど だから真夏日は活発な活動は控えてダラダラしましょうってことね・・(笑)












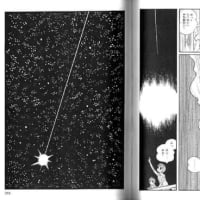
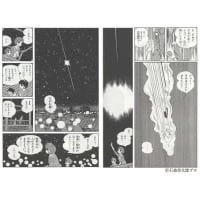
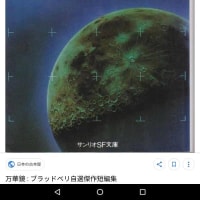

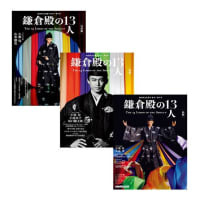

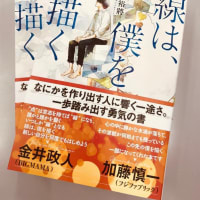
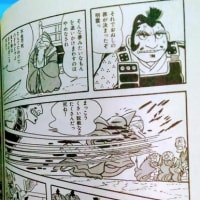
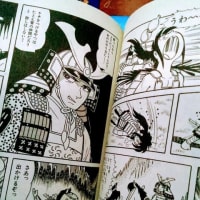
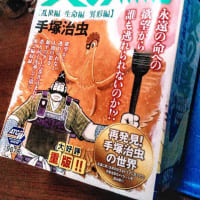
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます