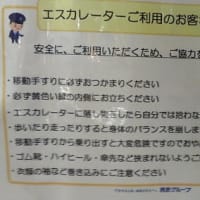11月6日(金)チョン・ミョンフン指揮 東京フィルハーモニー交響楽団
~第778回サントリー定期シリーズ~
サントリーホール
【曲目】
◎ブラームス/ドイツ・レクイエム op.45

S:林 正子/Bar:チェ・ウンジョ/合唱:東京オペラシンガーズ
ドイツ・レクイエムをミョンフンが指揮し、しかも合唱が東京オペラシンガーズとくればすごい演奏を聴けそう! と期待して出かけた東フィルの定期。弦バスの分厚く熱い響きに乗ってビオラとチェロが心の底から熱のこもった歌を静かに歌い始めたのを聴いたその時から、これは熱く深い「ドイツ・レクイエム」になると確信。"Selig sind"(祝福されている)というこのレクイエムのキーワードとも言える言葉が静寂の暗闇の中に、ささやかだが真っ直ぐな光に照らされて浮かび上がる姿に息を飲む。そんな感動的な始まりに胸が躍った。
様々な性格を持った7曲から成るこの大作全体を聴いて感じたのは、ミョンフンがこのレクイエムから常に地の底から沸き上がるような強く確かな生命力を呼び覚まそうとしているということ。使者の霊を慰めるためというより、残された人々の悲しみを癒すためのレクイエムと言われているこの曲だが、ミョンフンは悲しむ人々の心を癒すだけで終わらず、生きる力、勇気まで与えているのを感じた。
それは例えば第2曲「人は皆、草のようで」の前半は、命の儚さや無常を嘆く音楽だが、辛さをバネに希望を見い出して行くような能動的な力が感じられ、後半"Aber"(しかし)から一転して明るい曲調で歌われる喜ばしい気分が既に前半で見えているよう。
或いは安らかな天上の音楽のイメージが強い終曲にも、いずれ自分達も主のもとに召されることに安らぎを見い出すというより、「だから現世を精一杯生きて行こう」という命の賛歌のように感じた。
第5曲、「天国でまたいつか会えるのだからそんなに悲しまないでください」というソプラノ・ソロの清らかで優しい慰めのはずの歌を、林正子はオペラチックにエモーショナルなほどに朗々と歌い上げるのに最初違和感を覚えたが、これもミョンフンのアプローチの付箋だと思えば妙に納得してしまう。この曲が終わった直後に「ブラボー」の叫びとともに拍手を送った人がいてかなりひんしゅくものではあったが、そんな反応を喚起するような林さんの「励ましの歌」だった。
こんな林さんの歌唱に対して、バリトンのチェ・ウンジョが第3曲の端正な歌で敬虔に神に語りかけている姿にも心を打たれた。そんなバリトンの問いに導かれ、"Ich hoffe auf dich."「あなたに希望を託します」と感動的に歌い上げる合唱の高揚、そしてそれに続く壮大なフーガは神の威光を見せつけるような威圧的な音楽としてではなく、やはり生の活き活きとした躍動感が伝わってきた。
ミョンフンはこの大曲を、圧倒的な宗教音楽として高みから啓示のように伝えるのではなく、地上の側に立って生きている人々と共に「死んだ人達は決して不幸じゃない。だからみんな授かった命を大切に精一杯生きて行こうじゃないか!」と歌う熱き「人間賛歌」として伝えようとしているのを感じた。
ミョンフンのこうした意図にオーケストラも合唱団もとてもよく応えていたと思う。東フィルの感情のこもった熱くて深い音色と雄弁な歌が心に訴えかけ、東京オペラシンガーズの歌は、持ち前の輝きと透明感を兼ね備え、美しいハーモニーと明瞭なドイツ語の発音でアンサンブル全体をキリッと引き締め、色香を添えていた。指揮者、オーケストラ、合唱、そしてソリストが共感し合って実現した素敵なステージだった。
~第778回サントリー定期シリーズ~
サントリーホール
【曲目】
◎ブラームス/ドイツ・レクイエム op.45


S:林 正子/Bar:チェ・ウンジョ/合唱:東京オペラシンガーズ
ドイツ・レクイエムをミョンフンが指揮し、しかも合唱が東京オペラシンガーズとくればすごい演奏を聴けそう! と期待して出かけた東フィルの定期。弦バスの分厚く熱い響きに乗ってビオラとチェロが心の底から熱のこもった歌を静かに歌い始めたのを聴いたその時から、これは熱く深い「ドイツ・レクイエム」になると確信。"Selig sind"(祝福されている)というこのレクイエムのキーワードとも言える言葉が静寂の暗闇の中に、ささやかだが真っ直ぐな光に照らされて浮かび上がる姿に息を飲む。そんな感動的な始まりに胸が躍った。
様々な性格を持った7曲から成るこの大作全体を聴いて感じたのは、ミョンフンがこのレクイエムから常に地の底から沸き上がるような強く確かな生命力を呼び覚まそうとしているということ。使者の霊を慰めるためというより、残された人々の悲しみを癒すためのレクイエムと言われているこの曲だが、ミョンフンは悲しむ人々の心を癒すだけで終わらず、生きる力、勇気まで与えているのを感じた。
それは例えば第2曲「人は皆、草のようで」の前半は、命の儚さや無常を嘆く音楽だが、辛さをバネに希望を見い出して行くような能動的な力が感じられ、後半"Aber"(しかし)から一転して明るい曲調で歌われる喜ばしい気分が既に前半で見えているよう。
或いは安らかな天上の音楽のイメージが強い終曲にも、いずれ自分達も主のもとに召されることに安らぎを見い出すというより、「だから現世を精一杯生きて行こう」という命の賛歌のように感じた。
第5曲、「天国でまたいつか会えるのだからそんなに悲しまないでください」というソプラノ・ソロの清らかで優しい慰めのはずの歌を、林正子はオペラチックにエモーショナルなほどに朗々と歌い上げるのに最初違和感を覚えたが、これもミョンフンのアプローチの付箋だと思えば妙に納得してしまう。この曲が終わった直後に「ブラボー」の叫びとともに拍手を送った人がいてかなりひんしゅくものではあったが、そんな反応を喚起するような林さんの「励ましの歌」だった。
こんな林さんの歌唱に対して、バリトンのチェ・ウンジョが第3曲の端正な歌で敬虔に神に語りかけている姿にも心を打たれた。そんなバリトンの問いに導かれ、"Ich hoffe auf dich."「あなたに希望を託します」と感動的に歌い上げる合唱の高揚、そしてそれに続く壮大なフーガは神の威光を見せつけるような威圧的な音楽としてではなく、やはり生の活き活きとした躍動感が伝わってきた。
ミョンフンはこの大曲を、圧倒的な宗教音楽として高みから啓示のように伝えるのではなく、地上の側に立って生きている人々と共に「死んだ人達は決して不幸じゃない。だからみんな授かった命を大切に精一杯生きて行こうじゃないか!」と歌う熱き「人間賛歌」として伝えようとしているのを感じた。
ミョンフンのこうした意図にオーケストラも合唱団もとてもよく応えていたと思う。東フィルの感情のこもった熱くて深い音色と雄弁な歌が心に訴えかけ、東京オペラシンガーズの歌は、持ち前の輝きと透明感を兼ね備え、美しいハーモニーと明瞭なドイツ語の発音でアンサンブル全体をキリッと引き締め、色香を添えていた。指揮者、オーケストラ、合唱、そしてソリストが共感し合って実現した素敵なステージだった。