4月11日(火)アンネ・ソフィー・フォン・オッター(MS)/ベングト・フォシュベリ(Pf)/ニルス=エリク・スパーフ(Vn,Vla:1,3,5,9,10,アンコール1)


サントリーホール
【曲目】
1.ブラームス:アルトとヴィオラのための2つの歌 op.91
2.シューマン:歌曲集「女の愛と生涯」 op.42
3.コルンゴルト/「空騒ぎ」op.11~「花嫁の部屋の乙女」
4.「5つの歌」op.38~「古いスペインの歌」、「4つのシェイクスピアの歌」op.31~「デズデーモナの歌」
5.コルンゴルト/「空騒ぎ」op.11~「仮面舞踏会」
6.コルンゴルト/「道化の歌」op.29~「悪魔みたいな旦那」
7.アーン/「ラテンのエチュード」から「私がとりこになったとき」、「最高の贈り物」、「恋する乙女」、「春」
8.ドビュッシー/ビリティスの3つの歌
9.シベリウス/ヴァイオリンとピアノのための3つの小品op.116
10.ベルリオーズ/劇的物語『ファウストの劫罰』~「トゥーレの王」
11.カントループ:「オーヴェルニュの歌」第3集~「紡ぎ女」、「牧場を通っておいで」、「女房持ちはかわいそう」
【アンコール】
1.W.ピーターソン・ベルガー/As Pakers-Polska
2.アーン/クラリスに
3.サン・サーンス/La Dance Macabre
4.トム・ウェイツ/Take it with me
待ちに待ったオッターの来日公演は本当に素晴らしかった。溢れる音楽性、そして音に対しても言葉に対しても、枝葉末端のごくごく細い先端に至るまで細やかな神経が行き届いた繊細さは、これまでどの歌手からも聴いたことのないような境地に達している。
ブラームスのヴィオラのオブリガートを伴った歌が、何と自然に柔らかく始まったことか。「聖なる子守歌」では静かに慈しみ深く聖母の心を歌い綴っていた。「女の愛と生涯」は、このデュオのCDを愛聴している僕にとっては至福の時を与えてくれた。一人の女性の絵に描いたような美しい人生の場面場面の情景・心象が何の飾り気もなく、自然に湧き出るように綴られて行く。
ライブで聴くオッターはCDからはなかなか伝わってこないものまで伝えてくれる。微妙な音色と音量の変化で表現する細やかな心の綾や、一つ一つの言葉に命が吹き込まれたかのように、言葉の美しく生き生きとしたニュアンス。英独仏語を母国語としないオッターは言語に対してニュートラルな感覚で、何語の歌でも同じようにその言葉を最大限に生かす術を心得ており、それが幅広いレパートリーを獲得しているということを実感した。
多言語を自由に操り、ブラームスやシューマンでは清楚で慎み深い姿を歌ったかと思えば、ドビュッシーでは内面を官能的にくすぐるような妖しい魅力を放ち、コルンゴルトでの奔放さも実にハマっている。そして、アンコールの最後にマイク片手に地声で歌ったくれた”Take it with me”の心に響くこと響くこと!クラシックの歌手がポップス系を歌うと生真面目になり勝ちだが、オッターはポップスシンガーとしての魅力でもピカ一。最後は客席はスタンディングオヴェージョンでこの素晴らしい歌姫を称えた。
ピアノのフォシュベリはオッターの歌に影のように寄り添い、やわらかくサポート。シューマンの終曲「あなたははじめて私に苦しみを与えました」での、音量を抑えつつも心の奥底に突き刺さるような音が特に印象に残った。スパーフのヴィオラとヴァイオリンも、柔らかい音色と語り口が大変魅力。ソリストとしては弱いかも知れないが、こうしたコンサートでは彼のような音色で奏でる調べは理想的といっても良い。何から何まで魅力たっぷりのリサイタルだった。



サントリーホール
【曲目】
1.ブラームス:アルトとヴィオラのための2つの歌 op.91
2.シューマン:歌曲集「女の愛と生涯」 op.42
3.コルンゴルト/「空騒ぎ」op.11~「花嫁の部屋の乙女」
4.「5つの歌」op.38~「古いスペインの歌」、「4つのシェイクスピアの歌」op.31~「デズデーモナの歌」
5.コルンゴルト/「空騒ぎ」op.11~「仮面舞踏会」
6.コルンゴルト/「道化の歌」op.29~「悪魔みたいな旦那」
7.アーン/「ラテンのエチュード」から「私がとりこになったとき」、「最高の贈り物」、「恋する乙女」、「春」
8.ドビュッシー/ビリティスの3つの歌
9.シベリウス/ヴァイオリンとピアノのための3つの小品op.116
10.ベルリオーズ/劇的物語『ファウストの劫罰』~「トゥーレの王」
11.カントループ:「オーヴェルニュの歌」第3集~「紡ぎ女」、「牧場を通っておいで」、「女房持ちはかわいそう」
【アンコール】
1.W.ピーターソン・ベルガー/As Pakers-Polska
2.アーン/クラリスに
3.サン・サーンス/La Dance Macabre
4.トム・ウェイツ/Take it with me
待ちに待ったオッターの来日公演は本当に素晴らしかった。溢れる音楽性、そして音に対しても言葉に対しても、枝葉末端のごくごく細い先端に至るまで細やかな神経が行き届いた繊細さは、これまでどの歌手からも聴いたことのないような境地に達している。
ブラームスのヴィオラのオブリガートを伴った歌が、何と自然に柔らかく始まったことか。「聖なる子守歌」では静かに慈しみ深く聖母の心を歌い綴っていた。「女の愛と生涯」は、このデュオのCDを愛聴している僕にとっては至福の時を与えてくれた。一人の女性の絵に描いたような美しい人生の場面場面の情景・心象が何の飾り気もなく、自然に湧き出るように綴られて行く。
ライブで聴くオッターはCDからはなかなか伝わってこないものまで伝えてくれる。微妙な音色と音量の変化で表現する細やかな心の綾や、一つ一つの言葉に命が吹き込まれたかのように、言葉の美しく生き生きとしたニュアンス。英独仏語を母国語としないオッターは言語に対してニュートラルな感覚で、何語の歌でも同じようにその言葉を最大限に生かす術を心得ており、それが幅広いレパートリーを獲得しているということを実感した。
多言語を自由に操り、ブラームスやシューマンでは清楚で慎み深い姿を歌ったかと思えば、ドビュッシーでは内面を官能的にくすぐるような妖しい魅力を放ち、コルンゴルトでの奔放さも実にハマっている。そして、アンコールの最後にマイク片手に地声で歌ったくれた”Take it with me”の心に響くこと響くこと!クラシックの歌手がポップス系を歌うと生真面目になり勝ちだが、オッターはポップスシンガーとしての魅力でもピカ一。最後は客席はスタンディングオヴェージョンでこの素晴らしい歌姫を称えた。
ピアノのフォシュベリはオッターの歌に影のように寄り添い、やわらかくサポート。シューマンの終曲「あなたははじめて私に苦しみを与えました」での、音量を抑えつつも心の奥底に突き刺さるような音が特に印象に残った。スパーフのヴィオラとヴァイオリンも、柔らかい音色と語り口が大変魅力。ソリストとしては弱いかも知れないが、こうしたコンサートでは彼のような音色で奏でる調べは理想的といっても良い。何から何まで魅力たっぷりのリサイタルだった。
















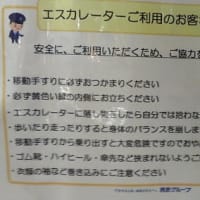









TBさせていただきました。
オッター、ほんとに素晴らしかったですね。
最後の”Take it with me”は、
ほんと涙ものでした。