
1991年(平成3年)に平和から登場した新要件ハネモノ「バットマン」
★賞球…7&13
★垂直の一穴回転体を採用
★ハネ開放時間…オトシ0.5秒、ヘソ0.5秒×2
★最高15ラウンド継続
★平均出玉…900~1000個(継続率は高め)
★当時の実戦店…新宿・歌舞伎町「オデヲン」、井の頭線・渋谷駅そば「大番」など
(旧・新宿コマ劇場前にあった「オデヲン」)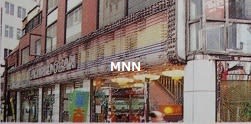
(井の頭線渋谷駅・ガード脇にあった「大番」)
平成3年初夏、新要件初期に登場したハネモノ。同年6月の段階で、文京区本郷「ニューときわ」に設置との資料もある。首都圏での普及率は、比較的高かったと記憶。
賞球数は「7&13」。平成2年10月の規則改正で、新要件機の最大賞球数は、旧要件時代の「13個」から「15個」にアップしたが、本機は始動チャッカーが7個戻し、その他が13個戻しと、やや抑えめになっていた。出玉量と遊び易さの「バランス」を考慮した結果だろう。
因みに、新要件機で最初に「13個戻し」を採用したのは、三共「道路工事GP」(6&13、平成3年1月発表)である(バットマンは平成3年3月発表)。
モチーフは文字通り「野球」で、盤面に描かれたゴリラ然としたバッターのイラストや、動物キャラのコミカルなハネが目を引いた。
一方、中央ヤクモノに目を移すと、クルクルと時計方向に回り続ける、銀色の「垂直回転体」が特徴だった。
本機の垂直回転体。直径は39.3ミリ。回転体の周期は約1.9秒。一穴式で、赤く色分けされた「STRIKE」穴(V穴)のみ入賞可能。V穴の真向いには、金色のボールを模した飾りがある。
V穴の入口幅は約13.4ミリと狭く、玉1個分(11ミリ)程度の余裕しかない。但し、V穴は左サイドに小さな「切り込み」があって、回転体にアプローチする玉の「受け」に一役買っていた。
ハネに拾われた玉は、上段ステージ奥から落下し、下段回転体上部の手前にアプローチする。
上段奥には、ステージに乗った玉を中央に寄せて下段に送る「ガイド」がある。このガイドの構造が左右非対称な為、上段から垂直に落下せず、下段で右方向に流れ易くなっていた(これが大当り中の継続率アップにも貢献…後述)。
上段から来た玉が回転体にアプローチした瞬間、赤いV穴が真上付近に来るとチャンス。玉がタイミング良くV穴に乗ると、そのまま下段へと運ばれて、真下のVゾーンに入賞、大当りとなる。
これ以外のタイミングでは、ほぼV入賞のチャンスはない。V穴に乗らず、回転体の左右にこぼれた玉は、回転体の側面に沿って落下、両脇のハズレ穴に入る。
ここで、V穴の幅は約13.4ミリと非常に狭く、また回転体の周期も約1.9秒と速い。したがって、回転体に向かう玉とV穴のタイミングは、そうそう合わない。よって、V入賞率は低め(ネカセやクセにもよる)。
首尾よく大当りすると、左右ハズレ穴がストッパーで塞がれ、回転体の両脇に玉を4個づつ貯留可能となる。
さらに、片側に5個目が貯留されると、5個目の玉は貯留スペースから溢れて回転体の上部に乗り上げる格好となり、V穴が真上に回って来た時点で確実に入賞する。
しかも、先述した上段奥の左右非対称な「ガイド」により、ヤクモノ内の玉は下段右サイドに流れ易く、大当り中も回転体の右側に貯留され易い(台のクセにもよる)。右側への5個貯留は比較的容易で、V継続も良好である。初当りが悪い分を、継続率の高さと出玉でカバーしていた。
このように、右サイドに貯留が偏ればV穴入賞は容易。但し、右側ばかり貯留されると、貯留5個で次ラウンドに行ってしまい、完走しても出玉は少ない。理想は片側5個、逆サイドに2~3個だが、ストロークや台のクセはもちろん、運に頼る部分も大きい。
ヤクモノ9カウントorハネ13回開閉で、貯留は解除される。入賞センサーが上段ステージにある為、9個目の入賞を感知した「瞬間」に、貯留解除となる。よって、9個目の玉が「5個目の貯留」となり、V穴に入賞する可能性は低い。その為、左右均等に4個づつ貯留された場合、貯留解除後にパンクする可能性が高い。
(運悪く、左右均等に4個づつ貯留された状態(8個貯留)。こうなるとパンク覚悟である。こうした「4個均等貯留」が起こり易い「クセ悪台」があった一方で、右に5個、左に2~3個貯留され易く、出玉が多い「お宝台」もあった訳で、貯留のクセはかなり微妙といえた。)
また、右に5個貯留されても、既に左に貯留が3個あると「8個貯留」となり、9個目が入賞した瞬間、全貯留が解除となる。当然、V穴が真上にやって来る前に解除されると、せっかくの5個貯留もフイになってしまう。
そこで、片側5個貯留の状態でヤクモノ8個入賞したら、いったん打ち出しをやめて、回転体が真上に来て5個目の貯留がV穴に入るのを待てば、不用意なパンクはなくなる。
さらに、ヤクモノに7個入賞したら「単発打ち」にして、同時に玉を2個ヤクモノに入れない「小技」も効いた。一瞬の判断ではあるが、こうした止め打ちが継続率アップに大きく寄与した。
もちろん、ハネ開放13回までに「片側5個貯留」の必要があるので、ヤクモノへの「寄り」が、V継続率にそのまま直結した。寄り釘のチェックや、ヤクモノに入り易いストロークを見つける事も重要となった。
このように、大当り中、ヤクモノの片側に貯留が偏ると継続し易く、左右均等に貯留されるとパンクし易いゲーム性は、まさに同社の名機「ビッグシューター」を踏襲していた。ただ、実際は片側貯留され易い台も多く、ビッグシューターのようにジリジリしっぱなし…という展開は少なかった。
(余談)
本機デビューと同年に出たパチンコVシネマ「二代目パチンコ物語・一発勝負必勝篇」(1991年12月公開、KSS)で、本機が登場する場面がある。
「打田パチンコ店」二代目オーナーの昇(美木良介)は、モダンでクリーンなホール経営を目指して奮闘するが、それを良しとしない先代オーナー(財津一郎)らの妨害で従業員達に造反され、経営が頓挫してしまう。
そんな時、女性証券ディーラーで常連客のレイコ(沖直美)は、失意の昇を励まそうと、別のパチンコ店に誘う。元来が生真面目な性格で、自分でパチンコすら打たない昇に、パチンコの楽しさや奥深さを教えようという訳だ。そこで、レイコが昇に打たせたのが、ハネモノの「バットマン」だった。
昇に好意を抱くレイコは、素人同然の昇にストロークなど懇切丁寧にレクチャーする。因みに、ロケ地は東京・足立区「ピーアーク谷中」(当時、全館禁煙やエコ推奨店として有名に)。
(C)KSS
バットマンを打つ昇と、横で「指導」するレイコ。二人の背後には、当時のピーアーク女性従業員のユニフォーム姿が映る。
(C)KSS
※盤面接写シーンでは、平和の初期・新要件ハネモノの象徴「’91 NEW VERSION」の円形ロゴが見える。但し、同時期の台でも、「ブンブン丸」にはこのロゴがない。
ちなみに、同社の初期・新要件デジパチには、「NEW VERSION 16 ROUND」の円形ロゴが入っていた(大当りラウンド数が、10Rから16Rに変わった事をアピール)。

(C)KSS
「ピーアーク谷中」の入口で会話する、昇とレイコ。










Vゾーン以外に穴がないのもねえ・・・その分鳴きは良かったですけど
ピエールって台のほうが好みだったが自分の行動範囲一件しか無くて・・・と思ったらしっかりここに記事ありましたね
打った記憶有りますよ。
大して出た記憶はないので、きっと遊んだだけなんでしょうけどね(^_^;)
ゲーム性すら忘れていたので、今回の記事はとても新鮮でしたよU+2728
羽根モノということもあり、台上ランプは光るだけのタイプですが、あそこに回転数とか大当たり回数表示が付き始めたのっていつ頃からなんでしょうねぇ。少なくとも95年くらいまでは、計数器やら元祖パチパチ君α(今でも販売中なのには驚き)などを持ち歩いていたと記憶しています。いつの間にやら豪華になりましたね。液晶付きなんて過剰なものもあるくらいですから・・