「絵本太功記」本能寺の変の発端から、その前夜6月朔日から10日、大詰、
と日にちを追った段での珍しい通しです。
通しでみるのは、初めてです。
歌舞伎でもよく上演されるのは、尼ヶ崎の段、
これだけ観ていると、悪役光秀と善い人秀吉、って印象でした。
でも、発端から描き出す光秀の人物像は、十分説得力あります。
よく知られた打擲、蘭丸との確執、知性派の光秀も、
領地お取り上げ、にこらえにこらえた堪忍袋が切れて、謀叛の決意に至る、
いまでは常識の、この筋書きは、この浄瑠璃が原点だった…、
当時はすごい批判だったわけですね、酷薄な主君×知的な臣下、ということは。
でも、謀叛の原因を私憤とせざるをえない、判官贔屓の庶民の心情にうったえる、
200年の年月を経て、あえて光秀を題材にするのはなんだったのでしょう。
歴史を大きく動かした人物です、
古来、謀叛の真意についていろいろな説があったであろうことは、容易に想像がつく。
下克上の天下取り、これは一説ではなく、常識かな?
朝廷の密かな勅命説、
一時もっとも有力だった、堺商人・利休・家康3者連合黒幕説、
ちなみに私なんか、絶対これだ!って思っています…。
浄瑠璃としては、私憤のほうが人間性を深くえぐれる、でしょうね。
光秀の時系列戦いが縦糸だとすれば、
横糸の男女・夫婦の情愛、親子・家族の情、が各段ごとに織りなしてゆきます。
でも、光秀一家以外は、一連のつながりのない人びとの悲劇だけが重なり合う…、
封建社会のさまざまな人間模様の悲憤をよりいっそう照らし出す演出なのでしょうか?
勘十郎さんの光秀はきびきびとした動きで、知的というより、スケールの大きな強面の戦国武将を
遺憾なく発揮していて、ホントに素敵でした。
その妻の蓑助操は、控えめな役をずーとためて演じてらっしゃいましたが、
尼ヶ崎の段で、文雀さんの母さつき、息子の十次郎を目の前で失う悲劇に、
あのとき謀叛を思いとどまるよう箴言したのに、と避けることができた悲運を、
泣き口説くとき、
しなやかな身のこなし、肩の震え、手から指先の反り、の細部に至るまで、
蓑助さんが魂を吹き込んでいって、血を吐くような叫びとなるのです。
ここにいたると、観客も魅入られてしまって、感激にふるえ、涙がでてしまいます。
この時の義太夫語りが住太夫さんだったら、どんなにいいでしょう!
でも、住太夫さんは感情がほとばしる語りではないのでしょうね。
杉の森の段、籠城する戦場(いくさば)で自害する夫となんとしてでも食い止めたい妻の一エピソード、
その切りを語りました。
低く静かに住太夫さんの語りがはじまります。
このときばかりは、人形ではなく、錦糸さんの三味線とともに右耳で聞き入ってしまいます。(右手に対座してます)
ホントに、ひとつひとつの言葉が、こころに沁みてくるのです。
文楽三味線は、私は燕三さんがなぜか好きなんです。違うんです、艶があるというか、メリハリがあって…、
人間国宝の寛治さんのが重厚で控えめ、きっとあまり目立ってはいけないのかもしれないのですが、
一の糸のなんともいえない音色、バックグラントとしてではなく、それとして味わいたいのです。
テレビで文楽観てもあまり感動しないのは、このお三味線が生でないから。
太夫・三味線は、口と奥、中と切と分かれていますが、どうちがうのでしょう?
切が重要な役どころのようです。
今回気がついたのですが、語りはじめるときの三味線の伴奏、独特の節、あれは同じなんですね。
浄瑠璃の世界に引き入れる、あの節、
デ・デ・デン、デーン…(ウーッ、って弾きながらかけ声でますよね)
あれが、ホントにいいんですね。
(2007/5/22 国立小劇場)
と日にちを追った段での珍しい通しです。
通しでみるのは、初めてです。
歌舞伎でもよく上演されるのは、尼ヶ崎の段、
これだけ観ていると、悪役光秀と善い人秀吉、って印象でした。
でも、発端から描き出す光秀の人物像は、十分説得力あります。
よく知られた打擲、蘭丸との確執、知性派の光秀も、
領地お取り上げ、にこらえにこらえた堪忍袋が切れて、謀叛の決意に至る、
いまでは常識の、この筋書きは、この浄瑠璃が原点だった…、
当時はすごい批判だったわけですね、酷薄な主君×知的な臣下、ということは。
でも、謀叛の原因を私憤とせざるをえない、判官贔屓の庶民の心情にうったえる、
200年の年月を経て、あえて光秀を題材にするのはなんだったのでしょう。
歴史を大きく動かした人物です、
古来、謀叛の真意についていろいろな説があったであろうことは、容易に想像がつく。
下克上の天下取り、これは一説ではなく、常識かな?
朝廷の密かな勅命説、
一時もっとも有力だった、堺商人・利休・家康3者連合黒幕説、
ちなみに私なんか、絶対これだ!って思っています…。
浄瑠璃としては、私憤のほうが人間性を深くえぐれる、でしょうね。
光秀の時系列戦いが縦糸だとすれば、
横糸の男女・夫婦の情愛、親子・家族の情、が各段ごとに織りなしてゆきます。
でも、光秀一家以外は、一連のつながりのない人びとの悲劇だけが重なり合う…、
封建社会のさまざまな人間模様の悲憤をよりいっそう照らし出す演出なのでしょうか?
勘十郎さんの光秀はきびきびとした動きで、知的というより、スケールの大きな強面の戦国武将を
遺憾なく発揮していて、ホントに素敵でした。
その妻の蓑助操は、控えめな役をずーとためて演じてらっしゃいましたが、
尼ヶ崎の段で、文雀さんの母さつき、息子の十次郎を目の前で失う悲劇に、
あのとき謀叛を思いとどまるよう箴言したのに、と避けることができた悲運を、
泣き口説くとき、
しなやかな身のこなし、肩の震え、手から指先の反り、の細部に至るまで、
蓑助さんが魂を吹き込んでいって、血を吐くような叫びとなるのです。
ここにいたると、観客も魅入られてしまって、感激にふるえ、涙がでてしまいます。
この時の義太夫語りが住太夫さんだったら、どんなにいいでしょう!
でも、住太夫さんは感情がほとばしる語りではないのでしょうね。
杉の森の段、籠城する戦場(いくさば)で自害する夫となんとしてでも食い止めたい妻の一エピソード、
その切りを語りました。
低く静かに住太夫さんの語りがはじまります。
このときばかりは、人形ではなく、錦糸さんの三味線とともに右耳で聞き入ってしまいます。(右手に対座してます)
ホントに、ひとつひとつの言葉が、こころに沁みてくるのです。
文楽三味線は、私は燕三さんがなぜか好きなんです。違うんです、艶があるというか、メリハリがあって…、
人間国宝の寛治さんのが重厚で控えめ、きっとあまり目立ってはいけないのかもしれないのですが、
一の糸のなんともいえない音色、バックグラントとしてではなく、それとして味わいたいのです。
テレビで文楽観てもあまり感動しないのは、このお三味線が生でないから。
太夫・三味線は、口と奥、中と切と分かれていますが、どうちがうのでしょう?
切が重要な役どころのようです。
今回気がついたのですが、語りはじめるときの三味線の伴奏、独特の節、あれは同じなんですね。
浄瑠璃の世界に引き入れる、あの節、
デ・デ・デン、デーン…(ウーッ、って弾きながらかけ声でますよね)
あれが、ホントにいいんですね。
(2007/5/22 国立小劇場)











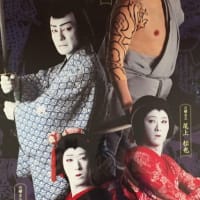



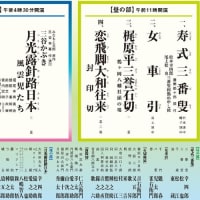

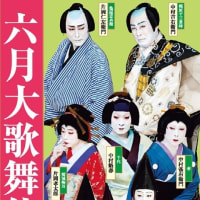


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます