
4月からNHKの古典講読で「西行をよむ」が始まった。
講師は、西澤美仁先生、角川ソフィア文庫の「西行 魂の旅路」の著者です。
西行をじっくり取り組みたいと買ってはみたものの、
拾い読み程度しかできていなかったので、とても期待しました。
と同時に、西行の歌をひとつひとつを取り上げて、解説していって、
それを聞くだけで一年間もつのかなー、と危惧もしていたのですが、
予想に反して、聞いているだけでも本当に面白い。
西行の歌に込められた、心の軌跡、とでもいうのでしょうか、
とても深いところを視聴者にもつたえようとする、
講師の先生の熱意が伝わってきます。
毎回、聞くだけでなく、ノートに整理し、
西行の和歌だけでなく、引用の和歌、出典の説話集などもあたり、
古典の講座を受けていたころの勉強が始まり、
それがとても楽しい。
4/19の回では、
文覚、恵心、明恵とのかかわりを、和歌と仏道、数寄ごころ、をキーワードに
西行の為さんとするところの真意が読み解かれていきます。
もろもろの西行の説話、伝説じみたエピソードも、
そこから派生するものであって、芯にあるものはゆるぎのない
風雅の道と仏法の道、
それは、明恵の残した言葉、のなかにあります。
「心の数寄たる人の中に、目出度き仏法者は、昔も今も出来(いできた)るなり。
詩頌を作り、歌連歌にたづさはることは、あながち仏法にてはなけれども、
かやうの事にも心数寄たる人が、やがて仏法にもすきて、智恵もあり、
やさしき心使ひもけだかきなり」(明恵上人遺訓より)
西行はその「心の数寄たる人」なのですね。
ところで、数寄、数寄者、心数寄たる人、とはどういうものなのでしょうか。
数寄は好きからきていて、中古文学でいうところの「色好み」に通じるものとか、
数寄も色好みも、その当時共有されていた風雅のこころを意味するわけですが、
現代の私たちにはほんとうのところ、理解できるのでしょうか。
数寄は数寄屋造りのように、削ぎ落された日本の美をイメージしますし、
色好みは好色と同義と解してしまいます。
後の世に着せられていくベールを剥がして本来の姿を見出さなければならないのでしょうね。
講師は、西澤美仁先生、角川ソフィア文庫の「西行 魂の旅路」の著者です。
西行をじっくり取り組みたいと買ってはみたものの、
拾い読み程度しかできていなかったので、とても期待しました。
と同時に、西行の歌をひとつひとつを取り上げて、解説していって、
それを聞くだけで一年間もつのかなー、と危惧もしていたのですが、
予想に反して、聞いているだけでも本当に面白い。
西行の歌に込められた、心の軌跡、とでもいうのでしょうか、
とても深いところを視聴者にもつたえようとする、
講師の先生の熱意が伝わってきます。
毎回、聞くだけでなく、ノートに整理し、
西行の和歌だけでなく、引用の和歌、出典の説話集などもあたり、
古典の講座を受けていたころの勉強が始まり、
それがとても楽しい。
4/19の回では、
文覚、恵心、明恵とのかかわりを、和歌と仏道、数寄ごころ、をキーワードに
西行の為さんとするところの真意が読み解かれていきます。
もろもろの西行の説話、伝説じみたエピソードも、
そこから派生するものであって、芯にあるものはゆるぎのない
風雅の道と仏法の道、
それは、明恵の残した言葉、のなかにあります。
「心の数寄たる人の中に、目出度き仏法者は、昔も今も出来(いできた)るなり。
詩頌を作り、歌連歌にたづさはることは、あながち仏法にてはなけれども、
かやうの事にも心数寄たる人が、やがて仏法にもすきて、智恵もあり、
やさしき心使ひもけだかきなり」(明恵上人遺訓より)
西行はその「心の数寄たる人」なのですね。
ところで、数寄、数寄者、心数寄たる人、とはどういうものなのでしょうか。
数寄は好きからきていて、中古文学でいうところの「色好み」に通じるものとか、
数寄も色好みも、その当時共有されていた風雅のこころを意味するわけですが、
現代の私たちにはほんとうのところ、理解できるのでしょうか。
数寄は数寄屋造りのように、削ぎ落された日本の美をイメージしますし、
色好みは好色と同義と解してしまいます。
後の世に着せられていくベールを剥がして本来の姿を見出さなければならないのでしょうね。











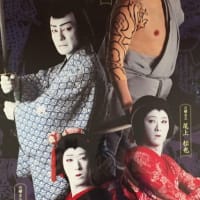



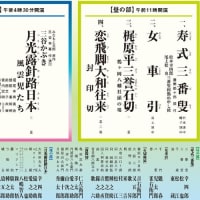

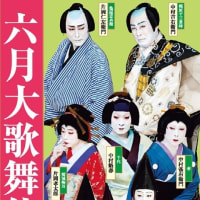


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます