毎年1曲、新たに暗譜する習慣として今年選んだのが、この曲。暗譜した曲は無意識のうちに作曲にも影響が出るので、その積りで選ぶ。
主題を最初、あまり感動的になり過ぎないように提示し、紆余曲折を経て再び登場する際、別人のように進化し、超然とした姿とさせる―古典音楽の普遍的なドラマ作法。
否、音楽に限らず、あらゆるジャンルに通じる「感動の原理」か…原理は一つだとしても、そのモチーフ、表現、展開の仕方によって、無限のドラマの可能性が広がる。
ショパン晩年の「舟歌」もまた。
序、いきなり傑作としてのご挨拶。日がゆっくり沈み、刻一刻と大気の色が変化していくような…沈み行く響き。
その響きを紐解けば、すでに曲全体を支配するモチーフが靄の中に隠れている。
単純な伴奏型に支えられ、そのモチーフは前半は3度、後半になると6度で平行するゆったりとした旋律となって船出する。
この基本の形を固執しながら、ジワジワと盛り上がっていく様は、後のラヴェルの「ボレロ」をも想起させる。
1つ目の山を越えると、突如それまでのドラマはまるで夢だったかのように、か細い紐のような、音楽の原初たる旋法が現れる。
それはA音の力強いオクターヴの一撃によって中断され、これもまた原初の音程、完全5度の木霊に導かれて第2の展開となる。
圧巻は後半。平穏なイ長調の「マニフィカト」はトリルによって遮られ、鼓動のリズムと共に、テーマが解体され半音階を上下するだけの、うめき声にも似た「迷路」に入り込む。
殆ど無の境地に達したかと思うや、パッと光が差す。その光は喜びに満ち、徐々に冒頭の、3度で平行する旋律にほぐれていく。
コーダでは、主音の鐘の音が鳴り響く中、トリルの錐もみに導かれて、ありとあらゆる和音が奔放に飛び込み、「バラード第3番」のクライマックスにも通じる、豊穣な不協和音を積み上げ、あの紐のようだった旋法も、ここでは目が眩む勢いで復活する。![]()











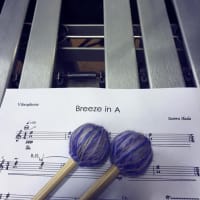

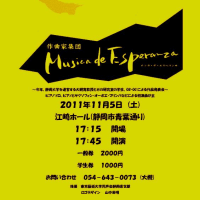
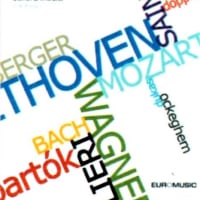

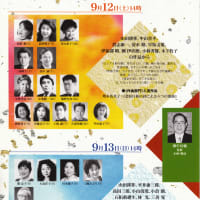
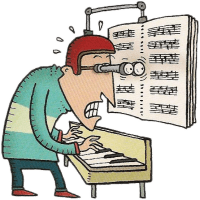

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます