僕は楽器本来の音色や、伝統的な奏法を尊重しながら作曲する。反対にそれらを排除し、徹底的にこれまでに無い音や奏法で作曲する、というタイプもある。現代音楽の分野では後者の方が注目されやすいように思う。
例えば、ヴァイオリンの弓の毛をべらぼうに緩め、弓の木の部分と毛の間に楽器を挟み、通常2本の弦しか同時に持続させられないところ、だらんと垂れた毛で、4本の弦を一斉に鳴らし続ける、という試み…もちろん微かな音しかしない。
管楽器でも、こんな風にやれば楽器が壊れたみたいな音が出るというのや、まるで吹き損なったように聴こえる音を確実に出すための運指、というのがごまんとあり、僕もセミナーに出席し、楽器法の本に書き込んだり専門書を購入したりした。
けれど、初めてやった作曲家はそこそこ意味があるとして、教えてもらって取り入れることに意味があるのか?しかも部分的に取り入れるのでは曲のコンセプトが曖昧になる。やるからには始めから最後まで徹底しないと…。
現代の作曲はテンポに支配される。テンポを指定し、演奏時間を申告することが義務付けられ、実際の演奏が大幅に食い違っていると、失格とされる。
昔は良かった…速く、とか重く、とか「歩く速さで」等と書くだけだ。素早い音型も、演奏家によって速さがまちまちで良いわけだ。
弦楽器や管楽器は同じように見える音型でも、半音と全音の組み合わせがちょっと変わるだけで可能だったり不可能だったりする。そこまでは分からないから演奏家に質問する。
パガニーニの「ヴァイオリンのためのカプリース」の譜面を見て、こんな運指で弾けるのか!と驚いたら、「これはごく普通の運指法で、何を疑問に思っているのかが分からない」と返事が来た。
逐一演奏家に聞いていたのでは仕事にならない。ヒンデミットはオーケストラの楽器をすべて演奏できたそうだ。![]()
学生時代ヴァイオリンが無かった頃、厚紙をヴァイオリンの指板の形に切り、指を押さえる所を記し、作曲する時、指が届くかどうか確かめた。
静大在学中は副科でトロンボーンを習った。先輩のお古を安く買ったからだ。マウスピースにはうっすらと緑青が付いていた。
藝大に入ってからオケなどを作曲する際、トロンボーンは、なまじ吹けたせいで自分の演奏能力を基準にしてしまい、却って楽器の能力を生かし切れなかった。
フルートのことは天野さんに教えてもらった。
学生時代は練習中の学生に突撃質問したり、楽器の先生に質問したり…。実践と失敗を繰り返しながら、楽器法の本は後から読んだ。
指揮も習っていたので指揮科の学生に混じって朝、オケのリハーサルを週2回見学した。リハは木管だけ、ビオラだけ、など部分的にやることが多いので、本番よりもずっと発見があった。
もちろん、楽器のことを良く知ってさえいれば良い曲が書ける、という訳ではない。演奏家が作曲した曲や、「管弦楽法」を著した作曲家の曲は、その点では長けている。
確かに「学生レベル」では、楽器の扱いの上手・下手で概ね作曲能力に優劣のふるい分けがされてしまうようだが…音楽史に残る「楽聖クラス」は、楽器の使い方など超越し、かつて無かった精神の高みにまで到達する。時には理論を無視した、無茶な、不可能な楽器の用法もあろうが、それは表現上の必然の結果。理解の触媒として歴史が加担する頃には、「狂気の沙汰」の迫力として、むしろポジティブに解釈されよう。
…などとじたばたチェロと格闘している間、ヴァイオリニストからカルテット改訂稿の、ヴァイオリンとビオラに関して「問題無し」の結果を頂いた。
借りたチェロは返す。代わりに紙のチェロを作った(写真)。![]()
最新の画像[もっと見る]
-
 アルトフルートのための"The Salutation" 再演
8年前
アルトフルートのための"The Salutation" 再演
8年前
-
 《Breeze in A》の指揮/YouTube
10年前
《Breeze in A》の指揮/YouTube
10年前
-
 島村楽器ピアノフェスティバル語録(第8回~第10回)
13年前
島村楽器ピアノフェスティバル語録(第8回~第10回)
13年前
-
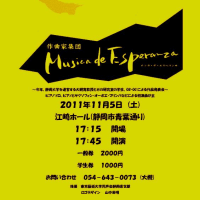 アルトサックスとピアノのための《詩篇》初演予定
13年前
アルトサックスとピアノのための《詩篇》初演予定
13年前
-
 ユーロミュージックから「ショパンのノクターン」楽譜出版
13年前
ユーロミュージックから「ショパンのノクターン」楽譜出版
13年前
-
 6手のための「ショパンのノクターン」編曲/初演予定
14年前
6手のための「ショパンのノクターン」編曲/初演予定
14年前
-
 バリトン歌曲《月》再演/奏楽堂
15年前
バリトン歌曲《月》再演/奏楽堂
15年前
-
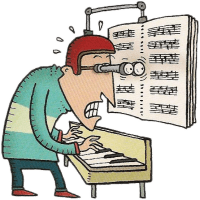 初見課題曲
17年前
初見課題曲
17年前
-
 ウィンドオーケストラ作品の委嘱
19年前
ウィンドオーケストラ作品の委嘱
19年前










気になる箇所を既成の曲の中から探し、楽譜を見ながら演奏(録音)を聴いて参考にすることもあります。
その時のためにも、僕はなるべくコンサートを聴きに行きます。
自分の作品についての具体的な疑問は、やはり演奏家に聞きます。
こちらの身分や事情を説明すれば、初対面の方でも親切に教えて下さいます。
Faxやメールなら、遠方の方とでも可能です。
自信の無い点だけ質問すれば、効率的です。
「一を聞いて十を知る」くらいの直感力も必要です。
教えていただいたら、「全く問題なし」の結論であってもお互いプロなので、気持ち程度は謝礼を差し上げます。
では、また。