最近お稽古にお伺いすると何か気になりませんか?
入り口から入ると正面に一升瓶。
お稽古の机の上にも一升瓶。
そう、「明鏡止水」大巨先生が揮毫された書がラベルになっているお酒です。
新たなデザインと言いますか、ラベルを作成されたようです。

これはちょっと前の作だと思いますが・・・
そんなお話から5月最後のお稽古日は日本酒のラベルのお話になりました。
ご存知の方も多いかと思いますが

これは比田井天来先生が揮毫されたラベルです。
その昔 「会津の良さは酒の良さ 会津 ほまれ」 な~んてコマーシャルがテレビで放映
されていたことを思いだします。

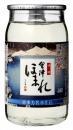
酒瓶に貼られるとこんな感じになります。
それから先程、大巨先生から「福小町」も比田井天来先生は揮毫されていると情報を頂き
調べてみるとありました、ありました。

これが基になって

こんなラベルになったのだと思います。
その他にも日下部鳴鶴先生が揮毫されているのが皆さんも良くご存知の

そう「月桂冠」ですね。
そして中村不折先生が揮毫されたのが


「真澄」に「日本盛」だそうです。
そして、桑原翠邦先生もやはり日本酒のラベルにと揮毫されているようです。
それがこれ

じゃ~ん。谷桜。山梨県のお酒です。
昨日お稽古に伺った際にこんな酒瓶が

谷桜です。


これは箱だけですが・・・

「山人魚目」間違いなく、さんじんぎょもく、桑原翠邦先生です。
これは、望月聴泉さんが前回のお稽古の際にラベルの話になったのを記憶されていて
山梨に行かれた際に見つけられて購入されたものだそうです。
今までも日本酒のラベルは色々と気にはなっていましたが、こうしてちょっと調べただけでも
かなりの銘柄に先生方は揮毫されていることが分かりました。
因みに

これは「白鹿」ですが、これも比田井天来先生が揮毫されたものに
年月を経るにつれて、少しづつ手が加えられたものだそうです。
この様に年月を経て、微妙に手が加えられることもあるようですね。
そして

「蒲原」吉野大巨先生が揮毫されたお酒です。
確か桑原翠邦先生の板戸を訪ねて八王子の「鮨忠」に出向いたときに先生にお持ちいただいて
皆でいただいたように記憶しております。
冷酒でいただいてとっても美味しかったように記憶しております。





「明鏡止水」 これは既に説明もいらない吉野大巨先生揮毫の有名なお酒。
「DANCYU」というグルメ雑誌にも何度か紹介されているお酒です。
結局今日は何が言いたいのかわけの分からないブログになってしまいましたが
近々、天来先生、翠邦先生、大巨先生をはじめとする書家が揮毫したラベルのお酒をコレクション
してみようかと考えた次第なのです。
そして最後に、こんなお酒も見つけてしまいましたよ。

字は違いますが「鶴齢」・・・・私は「鶴嶺」一字違いますが「カクレイ」です。
もしかして、皆さんの雅号と同じラベルのお酒があるのかも?
銘酒 「豪鶴」・・・・いちばんありそうな・・・・
生一本「鶴城」・・・・こんなお酒は如何ですか?
これから夏に向けてマコガレイのお刺身を肴に冷酒でキュっと一杯。
こんなひと時が楽しみにな季節になりました。




















おぅ~凄い内容です。
随分調べられましたね。
“最近気になりませんか?”の質問に対して、“気になりません”が私の回答です。
だって、教室に行っていませんので・・・。
白鶴・谷桜・・・・。大巨先生の作品・・・。へぇ~でした。
我々も究極は酒のラベルが到達点かも知れませんね。
ヨシ!「萬鶴」と言う銘柄を作ろう。
先ずは、自家製の梅酒でね。
早速の書き込みありがとうございます。
実は私は気付かなかったのですが、同僚から
福小町の福の字が、額装の福は偏が右で旁が左
お酒にラベルになると偏が左で旁が右になっているのですが・・・・っと。
???額装は左から書いているから偏と旁で構成されている漢字はこのようにあべこべに書いていくのが書の世界の常識なのでしょうか???
最近気になる以上に気になりました。
なんと福の字だけが裏返しになっているとのことで、
てっきり編と旁が左右反対になっているのだとばかり思っていたのですが
良く見ると確かに先生のおっしゃるとおりでした。
デザイン関係であのような形になったのか?謎は深まるばかり・・・・