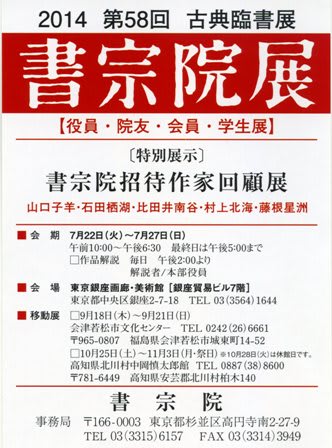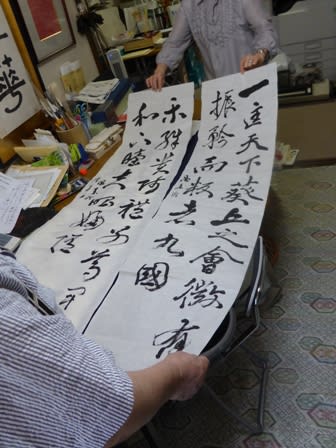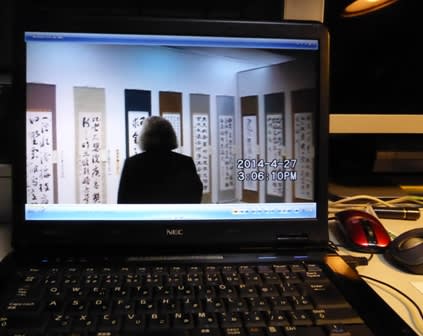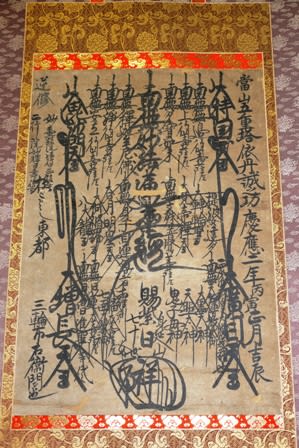6月も下旬になりました。
今日も東京地方は雨が降っています。
水滴の写真を撮りましたので、ご紹介いたします。
少し筆を休めてご覧になっていただければ幸いです。



何も変哲もない草花や葉っぱでも、水滴があるだけで絵になりますね。
何故でしょうか?




この水滴が次の動きを予測させるからでしょうか?
まんまるの不思議さもあります。

ついでに、プランターで育てているキュウリもご紹介いたします。
可愛いでしょ。
あと4~5日すれば収穫できます。


雨の日に、ビニール傘をさしてパチリしました。
気持ちが安らぐ画像かも知れません。


自作の蚊取り線香立て(外用)です。

家用もすでに活用していますよ。
梅雨明けはいつになるのでしょうか?
書道の紙もかなり湿り気を含んでいます。
この湿り気を利用するのも良いのでしょうね。
(萬 鶴)