@ブリジストン美術館
に行って参りました―!
いやあ、竹橋!いいところにありますね!
定期圏内とかまじうれしす^^
結構美術館に行くのには、交通費を気にしてしまってどうにもいけません。
こんばんは、ただけーまです(※2時)
水曜日にブリジストン美術館で行われていた「アンフォルメルとは何か?」という展覧会に行ってきました。
最終日にギリギリ滑り込みセーフ!です。
最近そんなんばっかです。あーやだ笑
「せんせー、あんふぉるめるってなんですかー?」
そう、例えば大橋のぞみちゃんのような。
そう、例えば芦田愛奈ちゃんのような。
そう、例えば不知火半袖のような。
そんな可愛い子に尋ねられたらどうしよう。
って思いますよね?←
「いや、ジャン・フォートリエっしょ、まじで。」
としか答えられなかったぼくは、もうここにはいなーい!!
あ、
わかりやすくて良い展覧会だったってことです。
わかりづらかったかな・・・^^;
(きもいねー)
いや、実際かなりわかりやすかったですよ。
ぼくが行ったのは最終日だったので、なんとギャラリートークつき。(Yahoo!)
そして展示のクオリティの高さwww
カタログ買おうと思ったらなくなってました(*^q^*)
てか、フォートリエの一番有名な「人質」があってもう涙が出そうでしたね。
断言してしまうと、アンフォルメルは現物を見るに限りますね。
確かに図録でも「人質」の有する玲玲とした悲しみが伝わるには伝わるわけですが。
彼の実践した圧倒的存在感のあるマチエール、そこから生まれる戦争の深い悲しみ。
その厚ぼったいマチエールは、本当に人肉が盛り上がっているかのようで。
観る者に本当に深い感動を与える作品だと思います。
彼の「人質」以外の作品は、割と図形的というか、若干フォルメルな部分もあるんじゃないかなぁとか思いました。
幾何学的とまで厳密ではないんだけど。
やはり図形という観点ではまだフォルメルでしたね。
いや、フォルメルである幾何学的図形が崩れているから、やっぱりアンフォルメルなのかな・・・
あうー・・・わからん。
でも「人質」は人の顔っていう有形が崩れてるものだから、やっぱり幾何学的図形っていう有形が崩れている一連の作品もアンフォルメルなのか・・・。
でも、やっぱり純粋なアンフォルメルとは違うと思うんだよなぁ・・・
グレーゾーンと言うか、描き方はもちろんフォートリエの厚ぼったいマチエールなんだけど。。
まあ、単純な2分法は良くないですよね。
そもそも、アンフォルメルがフォルメルから出発している時点で、若干の名残は残すものだもんね。
あー・・・よくわからんくなってきたwww
そしてジャン・デュビュッフェの「暴動」
こ れ は w w w
いやあ、超怖いな。
一瞬でアール・ブリュットの絵ってことはわかった!
と思ったら、アンフォルメルの画家なのねー。
あ、もちろんアール・ブリュットは意識したらしいですけど。
アール・ブリュットってのは「生の芸術」で。
しばしばプリミティブ・アートとか呼ばれたりもするんですが。
要するに、絵画「様式」というものを習ってない描き方で描かれた絵画のことですね。
原始時代の美術に通じるような、本能的な芸術。
それが、アール・ブリュット。
でも、最近はそれが差別的な表現を有するという意見もあったので。
エイブル・アートなんて呼ばれたりもします。
まあ、エネルギーはすごいですね、確かに。
ぼくはこういうの結構好きです(笑)
多角的な視点というか、ヴェルフリンの近視的な見方が想起されますドヤッ^^
あとは、ヴォルスの作品が数点。
彼はシュルレアリスム様式を用いた写真家だったんですが。
アンフォルメルの画家としてデビューします。
クレーの弟子だったみたいですね。
なんか馬肉に当たって亡くなってしまったようなんですが。
それを聞いて馬喰町を思い出したぼくは一体なんだったんだろうね。
あと、ザオ・ウーキーとかアンリ・ミショーとかカレル・アペルとか。
色々ありましたけど。
ぼくが感動したのは、ピエール・スーラージュの言葉でしたね。
あ、もちろんビデオですよ笑
「芸術は幻影ではなく、存在なんだ。」そう語ったスーラージュの哲学がぼくの心を捉えましたね。
彼は、現実を映し出し、内部に絵画空間を持ち、観客を沈潜させるような伝統的絵画に否定的見解を示すのです。
そして、彼が考える、存在としての芸術とは、光の反射まで考えて作られた絵画であるとのこと。
絵画に光が当たって、見え方が変わる。その反射した光の内部までが、作品の世界なのだと。
かれは作品の世界をタブローの内にとどめず、外部にまで拡張しようとした画家なんですね。
いやあ、こんなのもはや存在論ですよね。哲学ですよね。
とまあ、思想的コンテクストにからめとられてしまっている芸術の現状について考えさせられました。
うむうむ。
ではこんな感じで!
hona-☆
に行って参りました―!
いやあ、竹橋!いいところにありますね!
定期圏内とかまじうれしす^^
結構美術館に行くのには、交通費を気にしてしまってどうにもいけません。
こんばんは、ただけーまです(※2時)
水曜日にブリジストン美術館で行われていた「アンフォルメルとは何か?」という展覧会に行ってきました。
最終日にギリギリ滑り込みセーフ!です。
最近そんなんばっかです。あーやだ笑
「せんせー、あんふぉるめるってなんですかー?」
そう、例えば大橋のぞみちゃんのような。
そう、例えば芦田愛奈ちゃんのような。
そう、例えば不知火半袖のような。
そんな可愛い子に尋ねられたらどうしよう。
って思いますよね?←
「いや、ジャン・フォートリエっしょ、まじで。」
としか答えられなかったぼくは、もうここにはいなーい!!
あ、
わかりやすくて良い展覧会だったってことです。
わかりづらかったかな・・・^^;
(きもいねー)
いや、実際かなりわかりやすかったですよ。
ぼくが行ったのは最終日だったので、なんとギャラリートークつき。(Yahoo!)
そして展示のクオリティの高さwww
カタログ買おうと思ったらなくなってました(*^q^*)
てか、フォートリエの一番有名な「人質」があってもう涙が出そうでしたね。
断言してしまうと、アンフォルメルは現物を見るに限りますね。
確かに図録でも「人質」の有する玲玲とした悲しみが伝わるには伝わるわけですが。
彼の実践した圧倒的存在感のあるマチエール、そこから生まれる戦争の深い悲しみ。
その厚ぼったいマチエールは、本当に人肉が盛り上がっているかのようで。
観る者に本当に深い感動を与える作品だと思います。
彼の「人質」以外の作品は、割と図形的というか、若干フォルメルな部分もあるんじゃないかなぁとか思いました。
幾何学的とまで厳密ではないんだけど。
やはり図形という観点ではまだフォルメルでしたね。
いや、フォルメルである幾何学的図形が崩れているから、やっぱりアンフォルメルなのかな・・・
あうー・・・わからん。
でも「人質」は人の顔っていう有形が崩れてるものだから、やっぱり幾何学的図形っていう有形が崩れている一連の作品もアンフォルメルなのか・・・。
でも、やっぱり純粋なアンフォルメルとは違うと思うんだよなぁ・・・
グレーゾーンと言うか、描き方はもちろんフォートリエの厚ぼったいマチエールなんだけど。。
まあ、単純な2分法は良くないですよね。
そもそも、アンフォルメルがフォルメルから出発している時点で、若干の名残は残すものだもんね。
あー・・・よくわからんくなってきたwww
そしてジャン・デュビュッフェの「暴動」
こ れ は w w w
いやあ、超怖いな。
一瞬でアール・ブリュットの絵ってことはわかった!
と思ったら、アンフォルメルの画家なのねー。
あ、もちろんアール・ブリュットは意識したらしいですけど。
アール・ブリュットってのは「生の芸術」で。
しばしばプリミティブ・アートとか呼ばれたりもするんですが。
要するに、絵画「様式」というものを習ってない描き方で描かれた絵画のことですね。
原始時代の美術に通じるような、本能的な芸術。
それが、アール・ブリュット。
でも、最近はそれが差別的な表現を有するという意見もあったので。
エイブル・アートなんて呼ばれたりもします。
まあ、エネルギーはすごいですね、確かに。
ぼくはこういうの結構好きです(笑)
多角的な視点というか、ヴェルフリンの近視的な見方が想起されますドヤッ^^
あとは、ヴォルスの作品が数点。
彼はシュルレアリスム様式を用いた写真家だったんですが。
アンフォルメルの画家としてデビューします。
クレーの弟子だったみたいですね。
なんか馬肉に当たって亡くなってしまったようなんですが。
それを聞いて馬喰町を思い出したぼくは一体なんだったんだろうね。
あと、ザオ・ウーキーとかアンリ・ミショーとかカレル・アペルとか。
色々ありましたけど。
ぼくが感動したのは、ピエール・スーラージュの言葉でしたね。
あ、もちろんビデオですよ笑
「芸術は幻影ではなく、存在なんだ。」そう語ったスーラージュの哲学がぼくの心を捉えましたね。
彼は、現実を映し出し、内部に絵画空間を持ち、観客を沈潜させるような伝統的絵画に否定的見解を示すのです。
そして、彼が考える、存在としての芸術とは、光の反射まで考えて作られた絵画であるとのこと。
絵画に光が当たって、見え方が変わる。その反射した光の内部までが、作品の世界なのだと。
かれは作品の世界をタブローの内にとどめず、外部にまで拡張しようとした画家なんですね。
いやあ、こんなのもはや存在論ですよね。哲学ですよね。
とまあ、思想的コンテクストにからめとられてしまっている芸術の現状について考えさせられました。
うむうむ。
ではこんな感じで!
hona-☆










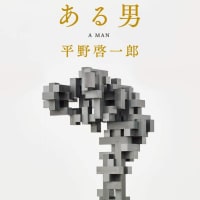









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます