こんばんは。いよいよ秋も深まり肌寒くなって来ましたね。
今回も前回の続きで、上田岳弘さんの『太陽・惑星』を紹介します。前回更新した「太陽」と対となる、後半に収録された「惑星」についての所感です。
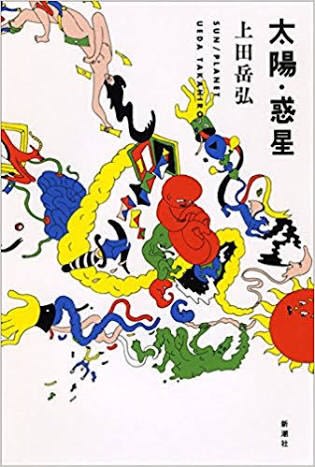
《Story》
アフリカの赤ちゃん工場、新宿のデリヘル、パリの蚤の市、インドの湖畔。地球上の様々な出来事が交錯し、飽くなき欲望の果て不老不死を実現した人類が、考えうるすべての経験をし尽くしたとき、太陽による錬金術が完成した。三島賞選考会を沸かせた新潮新人賞受賞作「太陽」と、対をなす衝撃作「惑星」からなるデビュー小説集!(新潮社ウェブサイトより)
惑星
最新のデバイスを使って、人々を次のステージへと導こうとする最強人間(或いは、悪魔・鬼)であるフレデリック・カーソン氏と、時間軸という概念に捉われず人類の運命を知る最終結論である内上用蔵の対談に至るまでの物語です。
Knopute社の社長を務めるフレデリックは、接続することで全てのことを体験することができる(個性がなくなる)製品を開発し、発売をする未来が確定している人物です。
すべての体験を共有することができる夢のような製品ですが、その製品に接続すると人間は個性を喪失し、緑色のゲルとして「肉の海」となってしまうという対価がありました。シュタインズゲートのゲルマユみたいなイメージですかね(伝わらない)しかし、人々はそれを厭わず新製品との接続を選択し、ゲル化する未来を選択します。
では、何故人類は個性を捨てることを選んだのか。それは、技術革新によって何が価値のあるものなのか、という評価軸の変遷によって説明されるのですが、そのロジックが非常に面白い。
産業革命以前、単純な労働力は非常に価値のあるものでしたが、産業革命の蒸気機関によって動力が自動化すると、労働力の価値が低下するようになります。そして、代わりに、如何に効率的に「動力を使うか」という事務処理能力(ホワイトカラー的素養)が価値を持ち始めます。90年代、PCの登場(同著者『私の恋人』に則ればWindows95の登場)でその事務処理能力も自動化されると、単純な処理能力から新しいものを生み出す能力(企画力/統率力/独創性)が求められるようになる……と言ったように、価値基準の変遷は昔からありました。
しかし、最近の世の中は、そうしたマーケティング手法も定型化/ノウハウ化されはじめ、今の個人的価値を図る尺度が、「いかに誰にも共感され得ないか」へと変遷していると本作では語られます。
そして、フレデリックの新製品は「いかに誰にも共感され得ないか」という価値基準が揺らぎはじめたところで登場するわけです。
人々は「いかに誰にも共感され得ないか」から「共感されること」を目指すようになり、そうした「共感されやすい自己」を形成・発信するようになります。
その例えとして引き合いに出されるのがFacebookです。個性を尊重しつつも人類の類型化を促す、即ち「自他の個性を系統的に把握」することができるメディアです。
しかし、そこには絶えず「他人からどう評価されているか」という外部の視点が絡んでおり、その点こそがFacebookが成功した要素であり、また、限界をもたらしている要素でもあると、新製品の開発者であるスタンリー・ワーカー氏が語ります。
「個性的である」ことの価値が霧散すると、次に訪れるパラダイムシフトは「無個性であること」です。宇宙観的に考えると、「一」から「全」へと人類が指向するようになるわけです。
そこで引用される一節が、端的にこの作品を巡る考えを説明していると言えるでしょう。
時があるのはすべてのことが同時には起こらないために、個があるのはすべてのことが同じ人に起こらないように
すべてのことを共有し、個の喪失を求める人類は、最終的にフレデリック・カーソン氏と内上用蔵を除きすべてがゲル化してしまいます。そしてゲル状となった人類は惑星と一体となり、あたかも個を失うことが惑星の意思であったかのように錯覚されるのです。
そこで、歯止めをかけようと働きかけるのが、最終結論である内上です。彼は時間軸を無視して行動ができる、時間を失った(すべてのことが同時に起きる)存在でした。丁度ドゥニ監督の『メッセージ』に出てきた地球外生命体に近いかもしれませんね。
そんな彼は未来を予知しながら、過去からフレデリックに警鐘のメールを送り続けます。しかし、ゲル化の未来は変えられない。
ここで矛盾している事実をフレデリックは指摘します。すべての時間軸にアクセスできる最終結論である内上であれば、結論は変えられるのではないか?では、何故変わっていないのか?つまり、最終結論もまた人類ゲル化の未来を選んでしまっているのではないか?と。
最終的に、フレデリックは内上に対し「肉の海が見る夢の代表人格」であると指摘します。つまり、一度ゲル化を選んだ結果、再び個を取り戻そうとするのが人類の、延いては惑星の意思であるというのです。
そうすると、すべての時を並列に扱うことのできる最終結論の説明もつき、人類が個性を選択するまで結末が変わらないのにも納得ができるわけです。
うーん、説明していてこの小説の構造のわかりづらさに辟易してしまいました。が!SF小説としては非常に読み応えがあります。
上田さんは技術の進歩とシンギュラリティに関心が高いのかもしれません。テクノロジーは私たちをどこへ導いていくのか……
今回も前回の続きで、上田岳弘さんの『太陽・惑星』を紹介します。前回更新した「太陽」と対となる、後半に収録された「惑星」についての所感です。
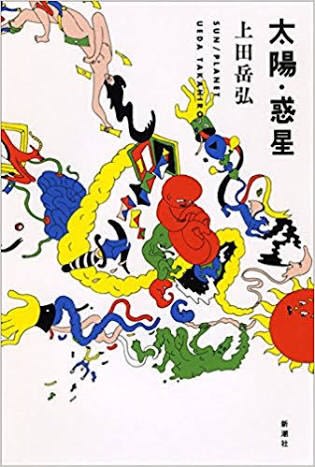
《Story》
アフリカの赤ちゃん工場、新宿のデリヘル、パリの蚤の市、インドの湖畔。地球上の様々な出来事が交錯し、飽くなき欲望の果て不老不死を実現した人類が、考えうるすべての経験をし尽くしたとき、太陽による錬金術が完成した。三島賞選考会を沸かせた新潮新人賞受賞作「太陽」と、対をなす衝撃作「惑星」からなるデビュー小説集!(新潮社ウェブサイトより)
惑星
最新のデバイスを使って、人々を次のステージへと導こうとする最強人間(或いは、悪魔・鬼)であるフレデリック・カーソン氏と、時間軸という概念に捉われず人類の運命を知る最終結論である内上用蔵の対談に至るまでの物語です。
Knopute社の社長を務めるフレデリックは、接続することで全てのことを体験することができる(個性がなくなる)製品を開発し、発売をする未来が確定している人物です。
すべての体験を共有することができる夢のような製品ですが、その製品に接続すると人間は個性を喪失し、緑色のゲルとして「肉の海」となってしまうという対価がありました。シュタインズゲートのゲルマユみたいなイメージですかね(伝わらない)しかし、人々はそれを厭わず新製品との接続を選択し、ゲル化する未来を選択します。
では、何故人類は個性を捨てることを選んだのか。それは、技術革新によって何が価値のあるものなのか、という評価軸の変遷によって説明されるのですが、そのロジックが非常に面白い。
産業革命以前、単純な労働力は非常に価値のあるものでしたが、産業革命の蒸気機関によって動力が自動化すると、労働力の価値が低下するようになります。そして、代わりに、如何に効率的に「動力を使うか」という事務処理能力(ホワイトカラー的素養)が価値を持ち始めます。90年代、PCの登場(同著者『私の恋人』に則ればWindows95の登場)でその事務処理能力も自動化されると、単純な処理能力から新しいものを生み出す能力(企画力/統率力/独創性)が求められるようになる……と言ったように、価値基準の変遷は昔からありました。
しかし、最近の世の中は、そうしたマーケティング手法も定型化/ノウハウ化されはじめ、今の個人的価値を図る尺度が、「いかに誰にも共感され得ないか」へと変遷していると本作では語られます。
そして、フレデリックの新製品は「いかに誰にも共感され得ないか」という価値基準が揺らぎはじめたところで登場するわけです。
人々は「いかに誰にも共感され得ないか」から「共感されること」を目指すようになり、そうした「共感されやすい自己」を形成・発信するようになります。
その例えとして引き合いに出されるのがFacebookです。個性を尊重しつつも人類の類型化を促す、即ち「自他の個性を系統的に把握」することができるメディアです。
しかし、そこには絶えず「他人からどう評価されているか」という外部の視点が絡んでおり、その点こそがFacebookが成功した要素であり、また、限界をもたらしている要素でもあると、新製品の開発者であるスタンリー・ワーカー氏が語ります。
「個性的である」ことの価値が霧散すると、次に訪れるパラダイムシフトは「無個性であること」です。宇宙観的に考えると、「一」から「全」へと人類が指向するようになるわけです。
そこで引用される一節が、端的にこの作品を巡る考えを説明していると言えるでしょう。
時があるのはすべてのことが同時には起こらないために、個があるのはすべてのことが同じ人に起こらないように
すべてのことを共有し、個の喪失を求める人類は、最終的にフレデリック・カーソン氏と内上用蔵を除きすべてがゲル化してしまいます。そしてゲル状となった人類は惑星と一体となり、あたかも個を失うことが惑星の意思であったかのように錯覚されるのです。
そこで、歯止めをかけようと働きかけるのが、最終結論である内上です。彼は時間軸を無視して行動ができる、時間を失った(すべてのことが同時に起きる)存在でした。丁度ドゥニ監督の『メッセージ』に出てきた地球外生命体に近いかもしれませんね。
そんな彼は未来を予知しながら、過去からフレデリックに警鐘のメールを送り続けます。しかし、ゲル化の未来は変えられない。
ここで矛盾している事実をフレデリックは指摘します。すべての時間軸にアクセスできる最終結論である内上であれば、結論は変えられるのではないか?では、何故変わっていないのか?つまり、最終結論もまた人類ゲル化の未来を選んでしまっているのではないか?と。
最終的に、フレデリックは内上に対し「肉の海が見る夢の代表人格」であると指摘します。つまり、一度ゲル化を選んだ結果、再び個を取り戻そうとするのが人類の、延いては惑星の意思であるというのです。
そうすると、すべての時を並列に扱うことのできる最終結論の説明もつき、人類が個性を選択するまで結末が変わらないのにも納得ができるわけです。
うーん、説明していてこの小説の構造のわかりづらさに辟易してしまいました。が!SF小説としては非常に読み応えがあります。
上田さんは技術の進歩とシンギュラリティに関心が高いのかもしれません。テクノロジーは私たちをどこへ導いていくのか……










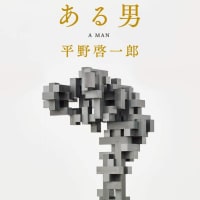









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます