
こんばんは、簿記の勉強を最近はじめましたただけーまです。
「勉強」が久しぶりすぎてなんだか少し楽しくさえ思います笑
来月の試験受かるといいなぁ・・・
さてさて。
一世を風靡している映画『レ・ミゼラブル』――
もう昨年になりますが、ぼくも公開してからすぐに観に行きました。
『英国王のスピーチ』で一躍有名になったトム・フーバー監督ですね。
これもかなり面白かった。吃音症に目をつけるあたり良い脚本だなあと。
観ていた最中に大きめの地震が来たことも今となっては良い思い出です笑
ミュージカル映画は『サウンド・オブ・ミュージック』以来で実はほとんど観たことがありません。
今調べたらディズニーの『美女と野獣』もミュージカル映画なんですね~。
そして、ずっと観たいと思ってる『ダンサー・イン・ザ・ダーク』も・・・
で、『レ・ミゼラブル』ですね。
正直めちゃめちゃ感動しました。二回泣いた。
『レ・ミゼラブル』の話自体はなんとなーくしか知らなかったので。
まさかあんなに悲しくて感動できるものだとは思ってませんでしたね。
話自体も感動的な上に、あんなに良い音楽が付されたらそれは感極まってしまいます笑
だから映画に負けたというよりは、脚本に負けたのかなぁと思うことにしてます笑
『英国王のスピーチ』もそうでしたけど、映画が良かったというよりも、脚本がよかったという印象の方が強いので、監督としての評価はまだ下さないことにします。
(評価と言っても好きとか嫌いレベルですけど)
しかし、ファンティーヌ(アン・ハサウェイ)とコゼット(アマンダ・サイフリット)めちゃめちゃ美人やな~。
調べたら、アン・ハサウェイって実写版アリスの白の女王とバットマンのキャットレディ役なのか!
日本でいうりょうみたいな雰囲気がありますよね笑
静かな美しさというか、貞淑な美しさというか。。。
アマンダ・サイフリットは『タイム』のシルヴィアか・・・髪型違うだけで全然印象違う。
この映画は、ミュージカル映画って何なんだろうって改めて考えさせられる契機になりました。
単にミュージカルを映画にしただけではない面白さがある。
そりゃあカメラの切り取った映像と遠くから眺めるミュージカルの感触なんて違うに決まっているのですが。
じゃあ、具体的にミュージカルを映画にすることってどういうことなんですかね。
映画は悪く言ってしまえば固定されたものです。
観る席の関係とか映画館の音響とか色々ありますけど、作品として完成したものが既に準備されている。
逆にミュージカルは、一回一回で出来が違う。キャストも公演ごとに異なるし、以前脇役だった俳優が次には主役をやるかもしれない。
同じ俳優だとしても疲労やその日のコンディションで全く同じ演技をすることはない。
俳優市場(←言い方悪い)の都合によってその出来が変わってしまうのがミュージカルなんですね。
そこがミュージカルの良さであるとも言えるのかもしれませんが。
生音の迫力というのもありますし・・・。
音楽と一緒でライブ感がとても大事な音楽なんですね。
「再生可能性」という点でミュージカルと映画が大きく違うことになりますね。
ベンヤミンの言葉を借りれば、それは複製芸術かそうでないかということになります。
「再生可能性」があるものは芸術なのか。
映画はもちろん芸術であると認知されているし、美術もその存在が持続する点で鑑賞の再生が可能ですね。
では、オーケストラ演奏を録音したものは果たして芸術なのでしょうか。
我々が普段耳にするCDから聞こえてくるものを指して芸術と言うでしょうか。
その「内容」が芸術かどうかではなく、そこから聞こえてくる「音」が芸術と言えるものなのでしょうか。
感覚としては「芸術」ではないですよね。
しかし、テープ音楽と呼ばれているジャンルでは、そうした再生可能性があるにも関わらず芸術と呼ばれうる。
すごく面白いことだと思いませんか?
テープ音楽が芸術たるゆえんは、録音しなければそれが成立しない音楽だからです。
再生機器が既に芸術の道具として機能してるからだと思うんですよ。
では、ミュージカルをそのまま録画したモノは芸術になりますか?
ある席から視点を変えずに、席でそのまま鑑賞したモノと同じ映像があったとして。
それを果たして芸術と呼べるのでしょうか。
少なくともぼくは芸術とは呼ばないです。
でも、ミュージカル映画は自信を持って芸術であると言える。
それは、それが映像をカットや編集、モンタージュを用いて作られているからです。
録画機器でしかできない手法によって作られた作品において、初めて再生機器が芸術の道具として機能しうるからなのです。
こういう小難しいうんちくみたいなのって正直芸術には必要ないと思いますけど笑
作品を鑑賞してそれが良ければ良いし、悪ければ悪い。
芸術に対する態度ってそんなもんで十分なんだと思います。
ただ、その良しあしがどこに担保されているのか、ということに目を向けるとまた違った面白さと言うものを芸術に見出すことができるような気がするのも事実です。
あー・・・最近こんな記事ばっかですね・・・
レミゼの話はどこに行ったwwwwという声、聞こえます・・・聞こえますよぉ・・・
次回からはもう少しくだけた感じの記事が更新出来たらなーと思います。
では、このあたりで。
hona-☆
「勉強」が久しぶりすぎてなんだか少し楽しくさえ思います笑
来月の試験受かるといいなぁ・・・
さてさて。
一世を風靡している映画『レ・ミゼラブル』――
もう昨年になりますが、ぼくも公開してからすぐに観に行きました。
『英国王のスピーチ』で一躍有名になったトム・フーバー監督ですね。
これもかなり面白かった。吃音症に目をつけるあたり良い脚本だなあと。
観ていた最中に大きめの地震が来たことも今となっては良い思い出です笑
ミュージカル映画は『サウンド・オブ・ミュージック』以来で実はほとんど観たことがありません。
今調べたらディズニーの『美女と野獣』もミュージカル映画なんですね~。
そして、ずっと観たいと思ってる『ダンサー・イン・ザ・ダーク』も・・・
で、『レ・ミゼラブル』ですね。
正直めちゃめちゃ感動しました。二回泣いた。
『レ・ミゼラブル』の話自体はなんとなーくしか知らなかったので。
まさかあんなに悲しくて感動できるものだとは思ってませんでしたね。
話自体も感動的な上に、あんなに良い音楽が付されたらそれは感極まってしまいます笑
だから映画に負けたというよりは、脚本に負けたのかなぁと思うことにしてます笑
『英国王のスピーチ』もそうでしたけど、映画が良かったというよりも、脚本がよかったという印象の方が強いので、監督としての評価はまだ下さないことにします。
(評価と言っても好きとか嫌いレベルですけど)
しかし、ファンティーヌ(アン・ハサウェイ)とコゼット(アマンダ・サイフリット)めちゃめちゃ美人やな~。
調べたら、アン・ハサウェイって実写版アリスの白の女王とバットマンのキャットレディ役なのか!
日本でいうりょうみたいな雰囲気がありますよね笑
静かな美しさというか、貞淑な美しさというか。。。
アマンダ・サイフリットは『タイム』のシルヴィアか・・・髪型違うだけで全然印象違う。
この映画は、ミュージカル映画って何なんだろうって改めて考えさせられる契機になりました。
単にミュージカルを映画にしただけではない面白さがある。
そりゃあカメラの切り取った映像と遠くから眺めるミュージカルの感触なんて違うに決まっているのですが。
じゃあ、具体的にミュージカルを映画にすることってどういうことなんですかね。
映画は悪く言ってしまえば固定されたものです。
観る席の関係とか映画館の音響とか色々ありますけど、作品として完成したものが既に準備されている。
逆にミュージカルは、一回一回で出来が違う。キャストも公演ごとに異なるし、以前脇役だった俳優が次には主役をやるかもしれない。
同じ俳優だとしても疲労やその日のコンディションで全く同じ演技をすることはない。
俳優市場(←言い方悪い)の都合によってその出来が変わってしまうのがミュージカルなんですね。
そこがミュージカルの良さであるとも言えるのかもしれませんが。
生音の迫力というのもありますし・・・。
音楽と一緒でライブ感がとても大事な音楽なんですね。
「再生可能性」という点でミュージカルと映画が大きく違うことになりますね。
ベンヤミンの言葉を借りれば、それは複製芸術かそうでないかということになります。
「再生可能性」があるものは芸術なのか。
映画はもちろん芸術であると認知されているし、美術もその存在が持続する点で鑑賞の再生が可能ですね。
では、オーケストラ演奏を録音したものは果たして芸術なのでしょうか。
我々が普段耳にするCDから聞こえてくるものを指して芸術と言うでしょうか。
その「内容」が芸術かどうかではなく、そこから聞こえてくる「音」が芸術と言えるものなのでしょうか。
感覚としては「芸術」ではないですよね。
しかし、テープ音楽と呼ばれているジャンルでは、そうした再生可能性があるにも関わらず芸術と呼ばれうる。
すごく面白いことだと思いませんか?
テープ音楽が芸術たるゆえんは、録音しなければそれが成立しない音楽だからです。
再生機器が既に芸術の道具として機能してるからだと思うんですよ。
では、ミュージカルをそのまま録画したモノは芸術になりますか?
ある席から視点を変えずに、席でそのまま鑑賞したモノと同じ映像があったとして。
それを果たして芸術と呼べるのでしょうか。
少なくともぼくは芸術とは呼ばないです。
でも、ミュージカル映画は自信を持って芸術であると言える。
それは、それが映像をカットや編集、モンタージュを用いて作られているからです。
録画機器でしかできない手法によって作られた作品において、初めて再生機器が芸術の道具として機能しうるからなのです。
こういう小難しいうんちくみたいなのって正直芸術には必要ないと思いますけど笑
作品を鑑賞してそれが良ければ良いし、悪ければ悪い。
芸術に対する態度ってそんなもんで十分なんだと思います。
ただ、その良しあしがどこに担保されているのか、ということに目を向けるとまた違った面白さと言うものを芸術に見出すことができるような気がするのも事実です。
あー・・・最近こんな記事ばっかですね・・・
レミゼの話はどこに行ったwwwwという声、聞こえます・・・聞こえますよぉ・・・
次回からはもう少しくだけた感じの記事が更新出来たらなーと思います。
では、このあたりで。
hona-☆










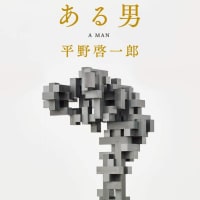









小林秀雄が、私たちが芸術に触れるきっかけは大抵「文学は翻訳で読み、音楽はレコードで聴き、絵画は複製で観る」時である、みたいなことを言っていたのを思い出した。
複製の芸術に人気が集まることは確かで、その人気がどこを起因として発生してるのか、が大事だと思う。。
美学には「キッチュ」とか「キャンプ」という概念があるんだけど、複製芸術の人気はそういう概念で説明されることが多いんだよね。
要は、「芸術を手元においておきたい」という気持ちなんだけど、複製品を果たして芸術として扱っていいのかどうかという問題はすごく繊細なものだから、なかなか一括りには出来ない難しさがあると思う。
K猫がこんなに芸術に興味あると思わなかったわ笑
今度ゆっくりお酒のみながら語ろう!!
そういう美学の概念分かんないんだけど
お薦めの本数冊挙げてmーーm
予習しときます。
K猫の連絡先わからないから、fbか何かで連絡するよー!
ぼくも全然読んでないけど基本的なのは、西村清和の「現代アートの哲学」とか小田部胤久の「西洋美学史」とかかな~。