ふはあ。
またもや美術に関する日記です。
すいません笑
えーっと。
大分前になりますが。
先週竹橋の国立近代美術館で、岡本太郎展に行って参りました。
いやはや。流石GWといいますか。
人多いわ!
やめてけろ。
人ゴミ苦手やん。
まあ、実は先々週にも行ったんですが。
そのときはあまりの人の多さに見事にとんぼ返りしてきましたよ!
笑
だって、チケット買うまでに15分の列が出来てるんだよ?
美術館ではかなり異例のことだよ!
まあ、これまでも、ゴッホ展とかモネ展とか。
めっちゃ込んでたことはありましたが。
流石に入場の列まではなかったわww
というわけで帰宅!
どうも、へたれです。
そして、4日間ほど四国旅行をしてまいりまして。
東京に戻ってすぐに竹橋へ。
バロスwwやすめ自分www
ん?
あれ?
長蛇の列がwww
うはー!!
やめれー!!
あれ?でもチケット販売所は混んでない。
寧ろストレートにいけた。
自「あの、あの列ってなんの列なんですか?」
警「ああ、あれは、ガチャガチャの列です。」
・・・
・・
・
ガwwチャwwガwwチャwwだwwとww
岡本太郎恐るべし!
展示自体は11時30分という食事どきに行ったせいか、割と普通の人気展覧会程度の混み具合ですみましたね。
いやはや・・・岡本太郎恐るべし。
肝心の展示内容はと言うと。
とってもとってもよかったですね!
流石GWにかぶせてきただけはある。
岡本太郎を概観する、素晴らしいラインナップでした。
「痛ましき腕」
や
「森の掟」
や
「夜」
などなど。
岡本太郎を語る上では欠かせない作品が多くありました!
そのほかにも、
「太陽の塔」の小さい複製品や。
「明日の神話」の下絵など。
もう、カタログも買ったし、おなかいっぱい。脳いっぱい。
でしたね。
最後にこんなお言葉を太郎先生から頂いてかえってきました。
「もっともっと悪条件のなかで闘ってみることだね。」
という台詞です。
心にしみじみしみじみしみております。
うん、元気の出る展示で本当によかった。
感想は・・・うーん。
岡本太郎ってダリに似てるかもね。
奇行とか、外見とか、世間に対する態度とか。
岡本太郎自身は、日本の伝統的な文化にかなり着目したみたいで。
縄文とか、琉球文化とか、東北の文化とか。
様々な文化を吸収して、今の作風になったようで。
それはダリもおんなじだなあ、と感じました。
ダリも、ミレーや、フェルメールの批判的習作を残しているわけで。
古さを評価しているあたりも、共通要素のように思えますね。
まあ、正しいかどうかは別として。
ぼくは似てると思いました^^
うーん。
自分、両方好きだなあ笑
hona-☆
またもや美術に関する日記です。
すいません笑
えーっと。
大分前になりますが。
先週竹橋の国立近代美術館で、岡本太郎展に行って参りました。
いやはや。流石GWといいますか。
人多いわ!
やめてけろ。
人ゴミ苦手やん。
まあ、実は先々週にも行ったんですが。
そのときはあまりの人の多さに見事にとんぼ返りしてきましたよ!
笑
だって、チケット買うまでに15分の列が出来てるんだよ?
美術館ではかなり異例のことだよ!
まあ、これまでも、ゴッホ展とかモネ展とか。
めっちゃ込んでたことはありましたが。
流石に入場の列まではなかったわww
というわけで帰宅!
どうも、へたれです。
そして、4日間ほど四国旅行をしてまいりまして。
東京に戻ってすぐに竹橋へ。
バロスwwやすめ自分www
ん?
あれ?
長蛇の列がwww
うはー!!
やめれー!!
あれ?でもチケット販売所は混んでない。
寧ろストレートにいけた。
自「あの、あの列ってなんの列なんですか?」
警「ああ、あれは、ガチャガチャの列です。」
・・・
・・
・
ガwwチャwwガwwチャwwだwwとww
岡本太郎恐るべし!
展示自体は11時30分という食事どきに行ったせいか、割と普通の人気展覧会程度の混み具合ですみましたね。
いやはや・・・岡本太郎恐るべし。
肝心の展示内容はと言うと。
とってもとってもよかったですね!
流石GWにかぶせてきただけはある。
岡本太郎を概観する、素晴らしいラインナップでした。
「痛ましき腕」
や
「森の掟」
や
「夜」
などなど。
岡本太郎を語る上では欠かせない作品が多くありました!
そのほかにも、
「太陽の塔」の小さい複製品や。
「明日の神話」の下絵など。
もう、カタログも買ったし、おなかいっぱい。脳いっぱい。
でしたね。
最後にこんなお言葉を太郎先生から頂いてかえってきました。
「もっともっと悪条件のなかで闘ってみることだね。」
という台詞です。
心にしみじみしみじみしみております。
うん、元気の出る展示で本当によかった。
感想は・・・うーん。
岡本太郎ってダリに似てるかもね。
奇行とか、外見とか、世間に対する態度とか。
岡本太郎自身は、日本の伝統的な文化にかなり着目したみたいで。
縄文とか、琉球文化とか、東北の文化とか。
様々な文化を吸収して、今の作風になったようで。
それはダリもおんなじだなあ、と感じました。
ダリも、ミレーや、フェルメールの批判的習作を残しているわけで。
古さを評価しているあたりも、共通要素のように思えますね。
まあ、正しいかどうかは別として。
ぼくは似てると思いました^^
うーん。
自分、両方好きだなあ笑
hona-☆










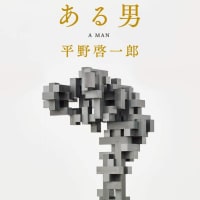









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます