おはようございます。すき家の新作がイマイチで少し悲しいただけーまです。にんにくの芽牛丼の復活を切に願います。
今回はパルムドール受賞作品ジャック・オーディアール監督の『ディーパンの闘い』で更新です。個人的には同年カンヌグランプリの『サウルの息子』の方が好みでしたね。

<Story>
主人公は、内戦下のスリランカを逃れ、フランスに入国するため、赤の他人の女と少女とともに“家族”を装う元兵士ディーパン。辛うじて難民審査を通り抜けた3人は、パリ郊外の集合団地の一室に腰を落ち着け、ディーパンは団地の管理人の職を手にする。日の差すうちは外で家族を装い、ひとつ屋根の下では他人に戻る日々。彼らがささやかな幸せに手を伸ばした矢先、新たな暴力が襲いかかる。戦いを捨てたディーパンだったが、愛のため、家族のために闘いの階段を昇ってゆく──。
仮面家族が本当の家族のように変わっていくストーリーは、ユーモラスに朝鮮半島の民族問題を描いたイ・ジュヒョン監督の『レッド・ファミリー』を思い出させます。
フランスの移民問題、麻薬横行、スリランカ内戦、PTSD、シェルショックなど、さまざまな要素が詰め込まれていて、話の軸がぼやけてしまったような気もしますが、家族を守るために再び戦闘に身を投じる再帰性はキャスリン・ビグローの『ハート・ロッカー』やクリント・イーストウッドの『アメリカン・スナイパー』、エリック・ポッペの『おやすみなさいを言いたくて』に通じる普遍的なものでしょうか。(これらの作品は家族より仕事を優先するわけですが、大事なものを天秤にかけるという意味でそのテーマには共通性があるような気がします)
前半夜のパリ郊外で安っぽいおもちゃを売り歩くディーパンの画が非常に鮮烈。それは上っ面の安っぽい幸せとディーパンの深い哀しみと怒りが対比されているかのようでもあります。

安物の玩具を売り歩くディーパン
節々に散りばめられた象のカットはガネーシャを意識したものなのでしょうか、ディーパンの中に残るインド的精神(戦闘員だった頃の記憶?)を喚び起す効果をもたらします。

要所に挿入される象のカット
クライマックスのこれこそジハード!と思わせるようなディーパンの戦闘シーンは、幕末に戻ってしまった緋村抜刀斎のようで単純にカッコよかったです。
戦闘中にディーパンは頭に弾丸を受けますが、死なずにヤリニの救出に向かいます。スローモーションになったのは生死の世界の切替えでしょうか、唐突に映されるヤリニとの幸福そうなラストシーンは天国のようにも見え、傍に並べられたガネーシャ像は彼岸的なアイコンのようにも映ります。
死んだはずなのに生かしてその先の物語を撮るという描き方は、最近ではイニャリトゥ監督の『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』やデイミアン・チャゼル監督の『セッション』なんかで目にしましたね。
まるで生前の理想は死後の妄想でしか到達しえないとでも言わんばかりの手法は、生者の希望を否定するようで少し残酷のようにも感じます。まあ、それだけ扱っているテーマが重いということなんでしょうけども。
今回はパルムドール受賞作品ジャック・オーディアール監督の『ディーパンの闘い』で更新です。個人的には同年カンヌグランプリの『サウルの息子』の方が好みでしたね。

<Story>
主人公は、内戦下のスリランカを逃れ、フランスに入国するため、赤の他人の女と少女とともに“家族”を装う元兵士ディーパン。辛うじて難民審査を通り抜けた3人は、パリ郊外の集合団地の一室に腰を落ち着け、ディーパンは団地の管理人の職を手にする。日の差すうちは外で家族を装い、ひとつ屋根の下では他人に戻る日々。彼らがささやかな幸せに手を伸ばした矢先、新たな暴力が襲いかかる。戦いを捨てたディーパンだったが、愛のため、家族のために闘いの階段を昇ってゆく──。
仮面家族が本当の家族のように変わっていくストーリーは、ユーモラスに朝鮮半島の民族問題を描いたイ・ジュヒョン監督の『レッド・ファミリー』を思い出させます。
フランスの移民問題、麻薬横行、スリランカ内戦、PTSD、シェルショックなど、さまざまな要素が詰め込まれていて、話の軸がぼやけてしまったような気もしますが、家族を守るために再び戦闘に身を投じる再帰性はキャスリン・ビグローの『ハート・ロッカー』やクリント・イーストウッドの『アメリカン・スナイパー』、エリック・ポッペの『おやすみなさいを言いたくて』に通じる普遍的なものでしょうか。(これらの作品は家族より仕事を優先するわけですが、大事なものを天秤にかけるという意味でそのテーマには共通性があるような気がします)
前半夜のパリ郊外で安っぽいおもちゃを売り歩くディーパンの画が非常に鮮烈。それは上っ面の安っぽい幸せとディーパンの深い哀しみと怒りが対比されているかのようでもあります。

安物の玩具を売り歩くディーパン
節々に散りばめられた象のカットはガネーシャを意識したものなのでしょうか、ディーパンの中に残るインド的精神(戦闘員だった頃の記憶?)を喚び起す効果をもたらします。

要所に挿入される象のカット
クライマックスのこれこそジハード!と思わせるようなディーパンの戦闘シーンは、幕末に戻ってしまった緋村抜刀斎のようで単純にカッコよかったです。
戦闘中にディーパンは頭に弾丸を受けますが、死なずにヤリニの救出に向かいます。スローモーションになったのは生死の世界の切替えでしょうか、唐突に映されるヤリニとの幸福そうなラストシーンは天国のようにも見え、傍に並べられたガネーシャ像は彼岸的なアイコンのようにも映ります。
死んだはずなのに生かしてその先の物語を撮るという描き方は、最近ではイニャリトゥ監督の『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』やデイミアン・チャゼル監督の『セッション』なんかで目にしましたね。
まるで生前の理想は死後の妄想でしか到達しえないとでも言わんばかりの手法は、生者の希望を否定するようで少し残酷のようにも感じます。まあ、それだけ扱っているテーマが重いということなんでしょうけども。










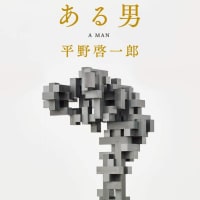









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます