こんにちは。春一番が吹きましたね。これから暖かくなってくるのが楽しみです。新居がようやく決まり、東京の果てで兄弟3人暮らしをすることになりましたただけーまです。ハウスコムのお兄さんありがとうございました。
今回はギレルモ・デル・トロ監督の最新作『クリムゾン・ピーク』で更新です。
友人に絶対好きだからと勧められて観ましたが、案の定好みドンピシャの作品でした。(大体美しいものとおぞましいものが混淆する作品は好きというわかりやすい好みです。今回であれば生娘とホラーのように!)

<Story>
10歳の時に死んだはずの母親を目撃して以来、幽霊を見るようになった女性イーディス。父親の謎の死をきっかけに恋人トーマスと結婚することになった彼女は、トーマスや彼の姉ルシールと一緒に屋敷で暮らしはじめる。その屋敷は、冬になると地表の赤粘土が雪を赤く染めることから「クリムゾン・ピーク」と呼ばれる山頂にあった。ある日、イーディスの前に深紅の亡霊が現われ、「クリムゾン・ピークに気をつけろ」と警告する。(映画.comより)
冒頭のイーディスの母親の葬式のシーン(雪と喪服による徹底された二色対立)から感じていましたが、もうとにかく色彩による美術効果が素晴らしい作品です。こと美術という観点から見た場合、もっとも優れている作品の1つと断言できるのではないでしょうか。それほどまでに、この映画の色彩効果は徹底して構築されています。

前半のイーディスとトーマスのダンスシーン(暖色による演出)

後半徐々に明らかになってくるトーマスとルシールの異常性(寒色による演習)
タイトルにもある「クリムゾン」を意識しているからか、クライマックスでアラデールの雪にクリムゾンレッドが血のように滲んでいくシーンは、かつて観たことが無いほどの美しいシーンに仕上がっています。

ラストの舞台となるアラデールの敷地
とまあ、美術がとても良かったのもそうなんですが、ストーリーとしても近代ヨーロッパでの古い洋館を舞台としたアンティークな雰囲気で、個人的にとても好きでした。この世界観がしっくりくるのは流石のミア・ワシコウスカといったところでしょうか。少女の表象であるアリス役をやってのけた彼女のファンタジックなかわいさならではでしょう。(アイオアディ監督『嗤う分身』のくすんだSF世界でも違和感なかったのも冷静に考えるとすごい…)

『クリムゾン・ピーク』

『嗤う分身』

『アリス・イン・ワンダーランド』
まあ、設定を簡単にまとめると、弟への異常な愛情で身を滅ぼしていくメンヘラブラコン(=ルシール)の話という感じなんですが、その屈折した愛情で身を滅ぼしていく設定も近代ロマンチシズム的で舞台にしっくりきます。
作中はよく蛾と蝶の比喩が多用されるのですが、そこでは蝶がイーディスの、蛾がルシールの暗喩となっています。海外のキービジュアルなんかはそれを端的に示していますね。

姉弟と夫婦、形式上は同じ異性間の愛情でありながらも、そのふたつの愛情は絶望と言って良いほどまでに隔絶されています。その、近似しつつも決して到達しえない姿こそ、蝶に憧れる蛾という暗喩につながっているのでしょう。同じ鱗翅目に属していながら、「鱗翅目の内、蝶でないもの」としか定義され得ない蛾。そして、蛾という忌まれる存在は、そのまま禁忌としての近親相姦に重なり、ルシールは引き返せない絶望へと身を堕としていくのです。
この記事を書いていて、蝶と蛾の間に明確な区別があるわけではないということを知り、少し衝撃的を受けました。うーん、この似て非なるものという概念は、まどマギでのメロンとカボチャの暗喩に通ずるものがありますね。カボチャは同じウリ科のメロンになりたくても決してなれない、その一方的な憧れの渇仰。
「ないものねだり」というのはいつだって人間の本質なのかもしれませんね。
今回はギレルモ・デル・トロ監督の最新作『クリムゾン・ピーク』で更新です。
友人に絶対好きだからと勧められて観ましたが、案の定好みドンピシャの作品でした。(大体美しいものとおぞましいものが混淆する作品は好きというわかりやすい好みです。今回であれば生娘とホラーのように!)

<Story>
10歳の時に死んだはずの母親を目撃して以来、幽霊を見るようになった女性イーディス。父親の謎の死をきっかけに恋人トーマスと結婚することになった彼女は、トーマスや彼の姉ルシールと一緒に屋敷で暮らしはじめる。その屋敷は、冬になると地表の赤粘土が雪を赤く染めることから「クリムゾン・ピーク」と呼ばれる山頂にあった。ある日、イーディスの前に深紅の亡霊が現われ、「クリムゾン・ピークに気をつけろ」と警告する。(映画.comより)
冒頭のイーディスの母親の葬式のシーン(雪と喪服による徹底された二色対立)から感じていましたが、もうとにかく色彩による美術効果が素晴らしい作品です。こと美術という観点から見た場合、もっとも優れている作品の1つと断言できるのではないでしょうか。それほどまでに、この映画の色彩効果は徹底して構築されています。

前半のイーディスとトーマスのダンスシーン(暖色による演出)

後半徐々に明らかになってくるトーマスとルシールの異常性(寒色による演習)
タイトルにもある「クリムゾン」を意識しているからか、クライマックスでアラデールの雪にクリムゾンレッドが血のように滲んでいくシーンは、かつて観たことが無いほどの美しいシーンに仕上がっています。

ラストの舞台となるアラデールの敷地
とまあ、美術がとても良かったのもそうなんですが、ストーリーとしても近代ヨーロッパでの古い洋館を舞台としたアンティークな雰囲気で、個人的にとても好きでした。この世界観がしっくりくるのは流石のミア・ワシコウスカといったところでしょうか。少女の表象であるアリス役をやってのけた彼女のファンタジックなかわいさならではでしょう。(アイオアディ監督『嗤う分身』のくすんだSF世界でも違和感なかったのも冷静に考えるとすごい…)

『クリムゾン・ピーク』

『嗤う分身』

『アリス・イン・ワンダーランド』
まあ、設定を簡単にまとめると、弟への異常な愛情で身を滅ぼしていくメンヘラブラコン(=ルシール)の話という感じなんですが、その屈折した愛情で身を滅ぼしていく設定も近代ロマンチシズム的で舞台にしっくりきます。
作中はよく蛾と蝶の比喩が多用されるのですが、そこでは蝶がイーディスの、蛾がルシールの暗喩となっています。海外のキービジュアルなんかはそれを端的に示していますね。

姉弟と夫婦、形式上は同じ異性間の愛情でありながらも、そのふたつの愛情は絶望と言って良いほどまでに隔絶されています。その、近似しつつも決して到達しえない姿こそ、蝶に憧れる蛾という暗喩につながっているのでしょう。同じ鱗翅目に属していながら、「鱗翅目の内、蝶でないもの」としか定義され得ない蛾。そして、蛾という忌まれる存在は、そのまま禁忌としての近親相姦に重なり、ルシールは引き返せない絶望へと身を堕としていくのです。
この記事を書いていて、蝶と蛾の間に明確な区別があるわけではないということを知り、少し衝撃的を受けました。うーん、この似て非なるものという概念は、まどマギでのメロンとカボチャの暗喩に通ずるものがありますね。カボチャは同じウリ科のメロンになりたくても決してなれない、その一方的な憧れの渇仰。
「ないものねだり」というのはいつだって人間の本質なのかもしれませんね。










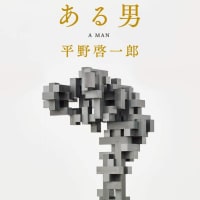









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます