とうとうゴールデンウィークに突入しましたね2018年も1/3終わったというおなじみのフレーズがこの歳になると笑えなくなってきます。
寄る年波に勝ちたいただけーまです。
久しぶりに小説で投稿します。今回は最年長の63歳で文藝賞(第54回)を、75歳黒田夏子さん(『abさんご』)に次ぐ高齢で芥川賞を受賞した岩竹千佐子さんの『おらおらでひとりいぐも』の読書感想文です。
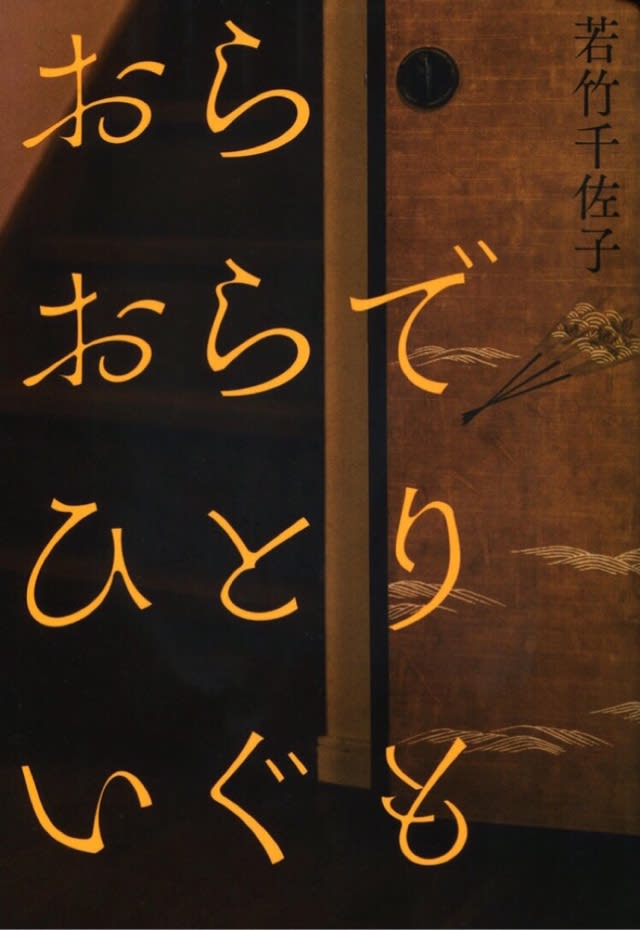
《Story》
74歳、ひとり暮らしの桃子さん。
おらの今は、こわいものなし。
結婚を3日後に控えた24歳の秋、東京オリンピックのファンファーレに押し出されるように、故郷を飛び出した桃子さん。
身ひとつで上野駅に降り立ってから50年――住み込みのアルバイト、周造との出会いと結婚、二児の誕生と成長、そして夫の死。
「この先一人でどやって暮らす。こまったぁどうすんべぇ」
40年来住み慣れた都市近郊の新興住宅で、ひとり茶をすすり、ねずみの音に耳をすませるうちに、桃子さんの内から外から、声がジャズのセッションのように湧きあがる。
捨てた故郷、疎遠になった息子と娘、そして亡き夫への愛。震えるような悲しみの果てに、桃子さんが辿り着いたものとは――(「河出書房新社ウェブサイト」より)
玄冬小説の傑作という触れ込みの本作。最初はなかなか読み進めるのが難しかったですが、後半になるにつれどんどん面白くなる。そんな小説でした。
人生には青春・朱夏・白秋・玄冬の四つのタームがあり、多くの名作は青春文学から生まれている気がしますが、本作は74歳の老婆が主人公の玄冬小説…にも関わらず、その熱量と言ったら青春文学に引けを取らない。
パーソナルな課題を普遍的なテーマへと昇華させ、解消させている点が見事でした。
一見すると東北でひとり暮らす桃子さんの女一代記のようでありながら、人生についての普遍的なテーマを多分に含んでいるように感じました。
桃子さんは、東北弁や地元を恥ずかしく思い上京した若かりし【青春】から、夫さえいればそれ以外何も要らないとさえ考える【朱夏】までを懐古し、当時の自分のことを見えるものしか見えない女であり、いつか終わりがあるのだとは夢にも思わない女だと振り返ります。
しかしながら、老いてから感じるのは、愛という名のもとにどちらも十全には生きられないということでした。愛を優先するあまり自由を蔑ろにしたと反省します。
夫を喪い、自身も老いて終わりがあることを知ることで、桃子さんの心境は徐々に変化していきます。
母親として過ごす中で、自分の人生の不全さを子供たちに仮託していた【白秋】を顧みるのです。
今になって思うのはそうした仮託に対する後悔と申し訳なさでした。
自分がやりたいことは自分がやる。簡単な理屈だ。子供に仮託してはいけない。仮託して、期待という名で縛ってはいけない。
母親として息子の人生に執着した結果、桃子さんの息子はかあさん、もうおれにのしかからないでと言って音信不通になったことがあったのでした。世話好きな母親が多いのはそういうことだと、桃子さんは考えます。
この過去を振り返るシーンが前半の盛り上がりで、後半は夫への墓参りの道中が舞台となります。夫に対する愛情や想いの変化を、道すがら考え、自らも彼岸へと足を運ぶような演出が巧みです。
子供の桃子さんから、青春期の桃子さん、中年の桃子さんが幻想として現れ、みなで足並みを揃えて夫周造の墓へと向かうのです。
身体の際があいまいになっていぐことで自身が全体でもあり部分でもあるという宇宙観的な感覚を引っさげながら、色んな年代の桃子さんと夫の墓前で弁当を食べます。
そのシーンは安らかな死を予感させますが、ふと目にしたカラスウリの赤色に心が躍動。生への新しい観念を手にします。
ただ待つだけでながった。赤に感応する、おらである。まだ戦える。おらはこれがらの人だ。
老いとは文化であり、年をとったらこうなるべきという思念が人を老いさせる。そうした柵から解放されれば、行けるところまで行けると桃子さんは感じたのです。
そして【玄冬】に入り、桃子さんは地元への愛に気づく。子供の頃忌んでいた八角山が今は心の拠り所になっており、ここで生まれた先人たちを愛しく感じます。
身体の動きも悪くなり、やがて訪れる死を心に受け入れ、夢想はアウストラロピテクスの初源へと至る。
マンモスの肉はくらったが。うめがったが
数え切れないほど多くの生に紡がれて今の自分がいると、壮大な夢想を繰り広げます。そして、自分の死を予感した今、その夢想は次の世代へ。
おらはちゃんとに生ぎだべが
女の一代記はどこに到達したのか。雛祭りの日に訪れた孫娘とのやり取りが本当に感動的で、思わず胸が高ぶります。
輪廻のミクロ的な呪いとマクロ的な希望を強く感じる作品でした。
寄る年波に勝ちたいただけーまです。
久しぶりに小説で投稿します。今回は最年長の63歳で文藝賞(第54回)を、75歳黒田夏子さん(『abさんご』)に次ぐ高齢で芥川賞を受賞した岩竹千佐子さんの『おらおらでひとりいぐも』の読書感想文です。
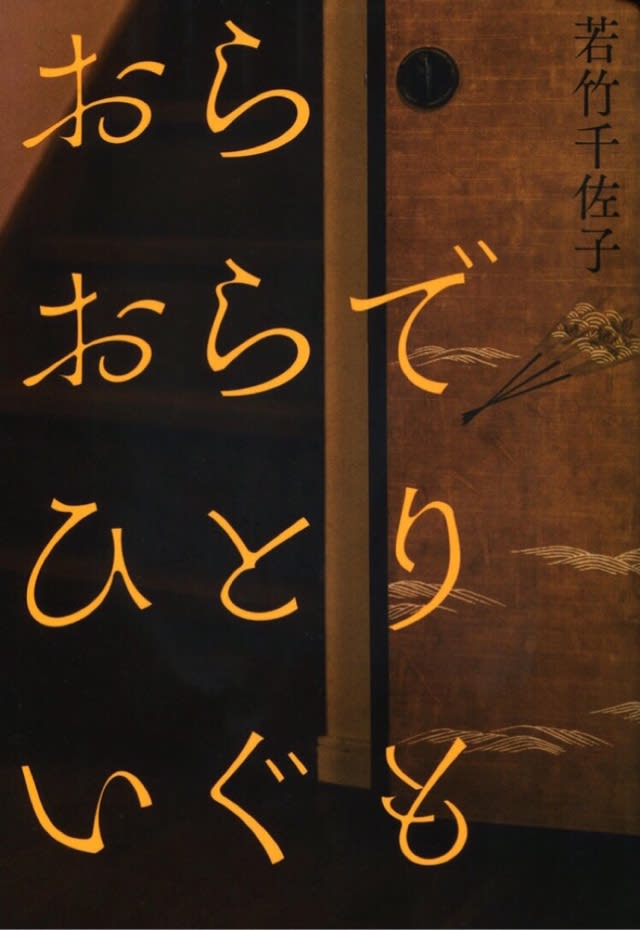
《Story》
74歳、ひとり暮らしの桃子さん。
おらの今は、こわいものなし。
結婚を3日後に控えた24歳の秋、東京オリンピックのファンファーレに押し出されるように、故郷を飛び出した桃子さん。
身ひとつで上野駅に降り立ってから50年――住み込みのアルバイト、周造との出会いと結婚、二児の誕生と成長、そして夫の死。
「この先一人でどやって暮らす。こまったぁどうすんべぇ」
40年来住み慣れた都市近郊の新興住宅で、ひとり茶をすすり、ねずみの音に耳をすませるうちに、桃子さんの内から外から、声がジャズのセッションのように湧きあがる。
捨てた故郷、疎遠になった息子と娘、そして亡き夫への愛。震えるような悲しみの果てに、桃子さんが辿り着いたものとは――(「河出書房新社ウェブサイト」より)
玄冬小説の傑作という触れ込みの本作。最初はなかなか読み進めるのが難しかったですが、後半になるにつれどんどん面白くなる。そんな小説でした。
人生には青春・朱夏・白秋・玄冬の四つのタームがあり、多くの名作は青春文学から生まれている気がしますが、本作は74歳の老婆が主人公の玄冬小説…にも関わらず、その熱量と言ったら青春文学に引けを取らない。
パーソナルな課題を普遍的なテーマへと昇華させ、解消させている点が見事でした。
一見すると東北でひとり暮らす桃子さんの女一代記のようでありながら、人生についての普遍的なテーマを多分に含んでいるように感じました。
桃子さんは、東北弁や地元を恥ずかしく思い上京した若かりし【青春】から、夫さえいればそれ以外何も要らないとさえ考える【朱夏】までを懐古し、当時の自分のことを見えるものしか見えない女であり、いつか終わりがあるのだとは夢にも思わない女だと振り返ります。
しかしながら、老いてから感じるのは、愛という名のもとにどちらも十全には生きられないということでした。愛を優先するあまり自由を蔑ろにしたと反省します。
夫を喪い、自身も老いて終わりがあることを知ることで、桃子さんの心境は徐々に変化していきます。
母親として過ごす中で、自分の人生の不全さを子供たちに仮託していた【白秋】を顧みるのです。
今になって思うのはそうした仮託に対する後悔と申し訳なさでした。
自分がやりたいことは自分がやる。簡単な理屈だ。子供に仮託してはいけない。仮託して、期待という名で縛ってはいけない。
母親として息子の人生に執着した結果、桃子さんの息子はかあさん、もうおれにのしかからないでと言って音信不通になったことがあったのでした。世話好きな母親が多いのはそういうことだと、桃子さんは考えます。
この過去を振り返るシーンが前半の盛り上がりで、後半は夫への墓参りの道中が舞台となります。夫に対する愛情や想いの変化を、道すがら考え、自らも彼岸へと足を運ぶような演出が巧みです。
子供の桃子さんから、青春期の桃子さん、中年の桃子さんが幻想として現れ、みなで足並みを揃えて夫周造の墓へと向かうのです。
身体の際があいまいになっていぐことで自身が全体でもあり部分でもあるという宇宙観的な感覚を引っさげながら、色んな年代の桃子さんと夫の墓前で弁当を食べます。
そのシーンは安らかな死を予感させますが、ふと目にしたカラスウリの赤色に心が躍動。生への新しい観念を手にします。
ただ待つだけでながった。赤に感応する、おらである。まだ戦える。おらはこれがらの人だ。
老いとは文化であり、年をとったらこうなるべきという思念が人を老いさせる。そうした柵から解放されれば、行けるところまで行けると桃子さんは感じたのです。
そして【玄冬】に入り、桃子さんは地元への愛に気づく。子供の頃忌んでいた八角山が今は心の拠り所になっており、ここで生まれた先人たちを愛しく感じます。
身体の動きも悪くなり、やがて訪れる死を心に受け入れ、夢想はアウストラロピテクスの初源へと至る。
マンモスの肉はくらったが。うめがったが
数え切れないほど多くの生に紡がれて今の自分がいると、壮大な夢想を繰り広げます。そして、自分の死を予感した今、その夢想は次の世代へ。
おらはちゃんとに生ぎだべが
女の一代記はどこに到達したのか。雛祭りの日に訪れた孫娘とのやり取りが本当に感動的で、思わず胸が高ぶります。
輪廻のミクロ的な呪いとマクロ的な希望を強く感じる作品でした。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます